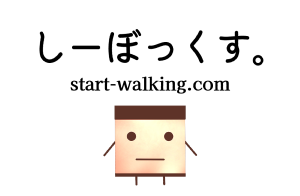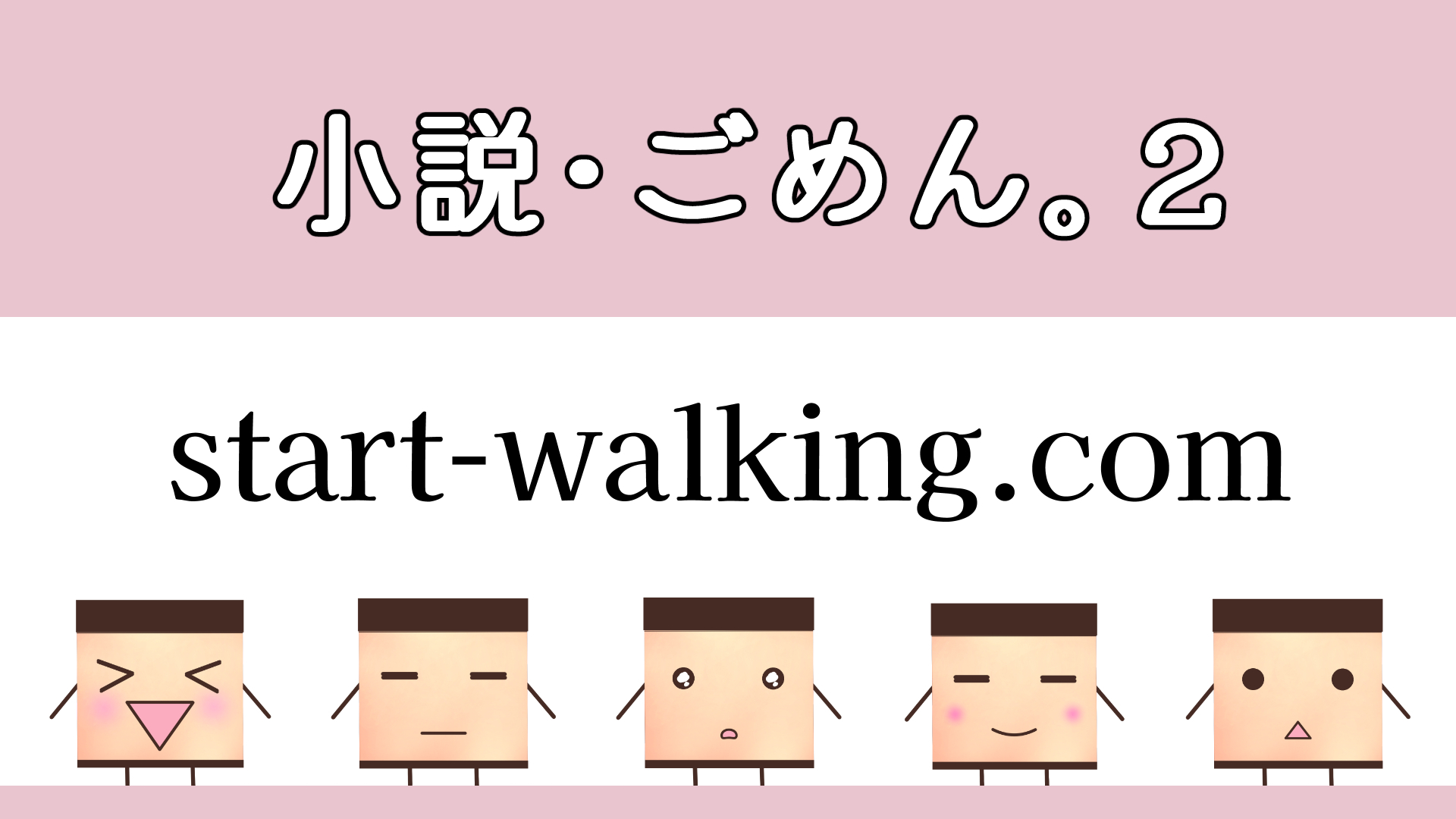第11話 うわ~、スライムがいっぱい~。
ハリアスが先頭を歩き、次にライツと愛那。その後ろにモランとナチェルが続く。
道から外れ、端に草の生い茂る小道の坂を下るとその先に川原が見えてきた。
そこが今回の彼等の目的地だった。
「ここにスライムや他の弱い魔物が生息している。マナ、足場が悪いから転ばないように気をつけて」
「はい」
愛那はそう答えつつ、ナチェルが用意してくれた靴がしっかりしているので小石や砂利はそんなに気にならなかった。それよりあちらこちらに見える綺麗な色をした物体に意識がいく。
(・・・・・・2、4、6、8、10、12、14。うわ~、スライムがいっぱい~)
愛那が立つ場所から見えているだけでも岩の上や川の中に様々な色のスライムがいる。
「ずいぶん多いですね」
モランがそう言うと、ハリアスが「あぁ」と頷く。
「動きが遅く、触れなければ危険が低い魔物という理由で、この時期にこの場所に来る者などいないのだろう」
魔物の大量発生という今だからこそ、こんなにスライムがいるらしい。
気分を高揚させた愛那がライツへと話しかける。
「これだけいたら討伐の練習がたくさん出来そうですね!」
相変わらず魔物討伐に前向きな愛那にライツが笑う。
「頼もしいな。よし。じゃあ行こうか。まずは俺がやってみせるから、マナは見ていてくれ」
「はい! よろしくお願いします!」
歩き出したライツの後を追い、全員が同じ場所へと移動する。
最初の討伐対象は岩の上にいる緑色のスライムだ。
「魔物討伐の基本として重要なのは、いかに少ない魔力量で相手を倒すか、だ。……マナの魔力量は大きいから他の者達に比べて魔力切れの心配は少ないかもしれないが、魔力には限りがあり、いつ、どんな状況に陥るかわからない。たくさんの魔物を討伐するには、たくさんの魔力が必要になるということだ。だからスライムみたいな魔物に対して、無駄に過剰な魔力を使わないことが大事なんだ」
ライツの言葉に愛那が「はい」と応える。
「まずは魔力操作の初級。スライムを討伐するのに必要な魔力量は……このくらいか」
そう言ったライツの右手から炎が出現する。
通常、攻撃魔法を習得したい者が初めに挑戦するのが、このように魔力を具現化させることである。
自分と相性の良い属性を探り、魔力を具現化できたら、それを大きくしたり小さくしたりして魔力量を意のままに調節することを覚えるのだ。
愛那が初めて使った冒険ギルドでの攻撃魔法は、その初心者の過程を飛び越え、魔法使いとして中級以上の実力を認められるレベルのものだった。
順番は逆になってしまったが、愛那はナチェルの指導の下、この初級の魔力操作もさして苦労することなく習得した。
今は見ているだけと言われている愛那の手がうずく。
(私も早くやってみたいー!)
愛那の視線の先に、ライツの手と同じくらいのサイズの炎が浮かんでいる。
その炎が緑色のスライムへと勢い良く飛んでいくと、ボフッ! と音を立てスライムが炎に包まれた。
そして次の瞬間には、炎ごとスライムの体内にある魔石が輝き、全てを吸い込んでいく。
(うわあああ! 本当に自分の体を吸収してる!)
話には聞いていたが、その様子を実際に見て感動する愛那。
ライツがそこに残された緑色の魔石を拾うと愛那へと差し出した。
受け取って、その綺麗な魔石をマジマジと見つめる愛那にライツが告げる。
「魔力量は今くらいの大きさで、マナの使える六属性全てで討伐可能か試してみよう」
第12話 初討伐の戦利品
愛那はライツからもらった魔石を腰に引っかけた袋の中へ落とすと、次の討伐対象へと移動する。
黄色のスライムだ。
「炎よ」
先程ライツが見せてくれた火魔法で挑戦する。
愛那がイメージした炎が手の平から浮かび上がる。
(これじゃあ小さ過ぎるから……魔力量を調整)
皆に見守られながら真剣な表情で炎を見つめ大きさを調節する。
(よし! これで……)
「行け!」
炎が勢いよく対象のスライムへと飛んでいく。
ボフッ!
黄色のスライムが炎に包まれ次の瞬間には中央の魔石に全て吸収された。
「やっ、たー!」
ピョンピョン跳ねながら満面の笑顔で喜ぶ愛那。
ライツはそんな愛那に微笑み「おめでとうマナ」と言うと、討伐した黄色いスライムの魔石を拾うように促す。
「初討伐の戦利品だ。マナ自ら手に取るといい」
愛那は頷くと黄色の魔石を拾い上げ、それを見つめる。
(よかった。問題なく討伐出来た。……神様。ようやく私、救世主としての第一歩を歩き始めました!)
「マナ様、初討伐おめでとうございます」
愛那は声をかけられたナチェルへと笑顔を向ける。
「ありがとうございます!」
「その魔石は袋の内ポケットに入れて他の石と別にしておくといいですよ。初めての討伐で手に入れた魔石は、討伐者にとって特別なものとなりますので」
「特別?」
ナチェルは頷き自分の首にかけられたペンダントを取り出した。
「特別と言っても気持ちだけのものですが、これが私の初討伐の時の魔石です。初心を忘れないよう討伐の際はお守りとしていつもかけるようにしています」
ペンダントトップに緑色の魔石。
「わぁ。いいですね」
そう言って愛那は自分の黄色の魔石を見る。
(初心忘るべからず。だね)
「私もナチェルさんみたいにペンダントにしたいです!」
「わかりました。帰ったらそのように手配いたしましょう」
ナチェルが微笑んで応える。
「皆さんも初めての魔石はお守りとしてペンダントにしてるんですか?」
愛那が男性陣に訊ねると微妙な笑顔を返された。
(?)
「マナ。男の場合は愛する女性にプレゼントする、というのが一般的なんだ」
ライツの答えに愛那が驚く。
「えっ?」
「ハリアスは結婚の時に指輪にして奥方に贈ったのだろう?」
「はい」
ハリアスが微笑んで答える。
「そ、そうなんですね」
(……これは、私、訊いてはいけない質問をしてしまったのでは?)
ライツの初討伐の魔石は今どこにあるのか?
(もしかしたら他の女性にプレゼントしたって可能性だってあるじゃない!)
固まったままそんなことをグルグル考えていた愛那の頭にライツの手がポン、と乗せられた。
「えっ……」
「何て顔をしてるんだ? マナ」
「ラ、ライツ様?」
顔を上げるとライツが楽しげに笑っている。
「俺の魔石はちゃんとルザハーツ城に保管されてあるはずだから」
愛那の表情がパアッと明るくなる。それを見たライツの口からクッ、と笑い声がこぼれた。
「マナ。そんな可愛い反応されると困ってしまうから、二人きりの時にしてくれないか?」
ライツの台詞に愛那の頬が瞬時に赤く染まった。
第13話 聖魔法
愛那は黄色の魔石を袋の内ポケットの中へ入れ、先程ライツにもらった緑色の魔石も同じ内ポケットへと移動させる。
(これもライツ様から初めていただいた特別な石だから、私の初めての魔石と一緒に大事にとっておこう)
俯いて小さく笑んだ愛那は顔を上げて、次のスライム討伐に気合いを入れる。
それから愛那は危なげなく次々と魔法を使いスライムを討伐していった。
ライツとナチェルがそんな愛那をすぐ近くで助言をしながら見守り、少し距離を取った場所でハリアスとモランがそんな彼らを二人並んで見つめていた。
「流石というか、魔法を習って数日とは思えないな」
感心したようにハリアスが言うと、モランが大きく頷いた。
「同感です。魔力操作をあんな簡単そうに……。自分の学生時代を思い出して、乾いた笑いがこみ上げてきますよ」
「確かに。学生時の同じ学年に、もし彼女がいたらと想像すると、とんでもないことになるな」
「六属性にライツ様を超える魔力量、そして天才的な魔力操作。救世主様だからと言われれば納得出来ますが……。あ、そういえばハリアスさん、聖魔法について、リオルート様から聞いていますか?」
愛那は聖魔法以外の六属性の魔法を使えるということを公表したが、正確には聖魔法を使えるかどうかの確認はまだしていなかった。
聖魔法使いは稀少で、もし愛那が聖魔法も使えるとしたら、魔物を討伐するという救世主に求める以上のことを人々に期待され、望まれてしまう。
そのことを危惧したナチェルは、愛那が聖魔法を使えるかどうかの確認は保留にしてライツに判断を仰いだ。
そのライツも、その判断は兄のリオルートに相談してからにすると話していたので、モランはリオルートに近いハリアスなら知っているのではと訊ねてみた。
「いや。だが、もしマナ様が聖魔法使いであったとしても、すぐに公表されることはないだろう」
「そうですよね。少なくともこの異常事態が緩和されるまでは……。ライツ様はマナ様への負担を出来るだけ軽くしたいでしょうし。……だけど、マナ様が聖魔法も使えるとしたら、すごく心強い」
「モラン。気持ちはわかるが、そんなことを口に出すな」
「はい。すみません」
そんな会話をしていた二人はスライム以外の魔物の気配を感じて、そちらへと視線を投げた。
姿は見えない草むらの中。
魔物の気配といっても弱い魔物のものだ。スライムの気配は弱すぎて気づけない者もいるが、このくらいの気配なら誰でも気づくといったレベルのもの。
その時、突然「ひぃあああああぁ」という悲鳴にもならない弱々しい声が聞こえてきてそちらへ顔を向ける。
皆の視線先には愛那がいて、その愛那は顔を強ばらせ、魔物がいる草むらを見つめながら自分の身体を抱きしめていた。
「マナ?」
「マナ様?」
ライツとナチェルが心配そうに愛那の名を呼ぶ。魔物の気配を感じ取っただけにしては様子がおかしい。
「き……」
「き?」
「気持ち悪いぃいいいいいいい!!」
愛那の上げた悲鳴に、皆の表情が唖然となった。
第14話 ばれないとお思いでしたか。
ルザハーツ城のリオルートの元に、予定のない訪問者が到着していた。
相手が相手だけに謁見の間ではなく、防音の魔道具の置かれた一室へと案内される。
「これはこれは、神官長。お久しぶりですね」
扉が開きリオルートが部屋に入ると、ソファから立ち上がった神官長サーゼンが深く一礼をした。
「お久しぶりでございます、リオルート様」
神官長の後ろに控え立つ二人の神官も同時に一礼をする。
その内の一人は王太子であるレディルだったが、神官の帽子が彼の顔をうまく隠していた。
レディルは今以上の関係悪化を防ぐため、まずはライツと愛那の現在の様子を探り、話が出来るタイミングを計るつもりだった。
「ライツから話は聞いています。なので、まさかこんな早くにこのルザハーツ領へ貴方がおいでになるとは、思いもしませんでしたよ」
ソファに座った二人が話し始める。
「突然の訪問になってしまい、大変申し訳ありません。実は御神託を賜りまして、一刻も早く救世主様へお伝えしなくてはという思いで来させていただきました」
「御神託・・・・・・なるほど、そうですか」
「あの、ライツ様と救世主様はどちらに? このルザハーツ城に滞在していると聞いて来たのですが」
「共に魔物の討伐に出ています。マナ様の初めての討伐になりますので、練習を兼ねた初心者用の場所です。夕刻には戻ってくるでしょう」
「マナ様。それが救世主様のお名前でしたね。ライツ様のお話では17歳だとか。リオルート様は直接お話しされましたか? 救世主様は一体どのようなお方なのでしょう? 今もまだお怒りでしょうか?」
「それを私に訊かれましても……しかし、異世界召還をしておきながら、救世主様に一言も声をかけることなく放置したというのは本当でしたか」
笑顔で嫌味を言うリオルートに、神官長は神妙な様子で「お恥ずかしい限りです」と答えた。
「ところで」
リオルートの視線が後ろに控える一人の神官へと向けられる。
「そちらの神官に扮した王太子殿下は、一体どんな用事があってこのルザハーツ領に?」
「!!」
レディルがビクッと身体を震わせる。
「……ばれていたか」
「ばれないとお思いでしたか」
呆れた声で言い返され、レディルは帽子を取った。
そして気まずげな顔で髪をかきあげると、数秒思案し、勢いをつけてリオルートの方へと近づいた。
「リオルート!」
「何です?」
「俺、いや、私は反省している! とても深く深く反省しているのだ!」
「反省は当然です。だが、それを私に言われても」
「謝罪がしたい! 救世主であるあの少女に! ライツの怒りも解きたいのだ! 協力してくれ! 頼む!」
そう言ったレディルは、真剣な顔でいとこであるリオルートに頭を下げた。
第15話 ちょっと待て
「マナ、そんなに落ち込まないでくれ」
帰りの馬車の中には愛那とライツ、この二人が乗っていた。
気落ちしている愛那の傍にいたいと、ライツがナチェルに頼んで交代したのだ。
横並びしているライツの手が俯いている愛那の頭を撫でる。
そのライツの優しさが愛那の涙腺を刺激したがグッとこらえる。
「ごめんなさい。情けなくて……。救世主だからって、自分を過信していました」
「マナは頑張っている。異世界から来たばかりの君が、この国のために何故そんなに頑張ってくれるのか不思議なくらいだ」
(何故?)
愛那は顔を上げてライツを見る。
(それは、あなたがいるから……)
ライツが愛那の【運命の恋人】だから。
救世主としての役目を果たさなくては、ライツの傍にいる資格がないような気がしていた。
(それに、神様がもし……)
愛那が再び俯く。
ライツは「俺がいるんだから、大丈夫だ。マナは急がなくていい。ゆっくりでいいんだ」と告げ、愛那の肩を引き寄せた。
ルザハーツ城へ帰り着くと、ナチェルが馬車から降りてきたライツと愛那へと近づく。
「マナ様。練習をお約束していた馬の二人乗りの件ですが、今日は止めておきましょう。お疲れでしょうからゆっくり部屋で休まれて……」
「ちょっと待て」
ナチェルの言葉をライツが遮った。
「何でしょう?」
「何だ、その馬の二人乗りの練習というのは?」
「マナ様が馬に乗ったことがないという話から、いざという時のために、せめて二人乗りの経験をしておいた方がいいということになりましたので……」
「マナと、誰とが、だ?」
「は、私とですが」
「……」
落ち込んでいた愛那だったが、様子のおかしい二人の会話に顔を上げて首を傾げる。
「マナの二人乗りの練習は俺がする」
「……ライツ様」
無言だったが(女の私相手になにをそんな心の狭いことを……)というナチェルの視線の意味をライツは正確に読み取った。
「……マナの初めては全部俺がもらいたい。当然だろう」
その台詞にナチェルは呆れたような顔になったが、愛那は顔を真っ赤に染めて体を硬直させた。
そこにリオルートの側近がライツへと近づき、耳元で何かを告げた。
「……わかった。すぐに行く」
ライツは愛那に優しく微笑む。
「……兄さんに呼ばれたから、マナは部屋で休んでいてくれ」
愛那が「はい」と頷くのを確認したライツは、表情を少し厳しいものに変えた。
「モラン! ナチェルと共にマナの警護を」
「はい!」と離れた場所にいたモランが応え、ライツはハリアスと共に城の中へと消えていく。
そんな後ろ姿を見送った愛那は、ライツの様子がおかしかったように感じ首を傾げた。
(何か、あったのかな?)
第16話 新たな御神託を賜りましたので。
「俺は、救世主の居場所を誰からも悟らせぬよう気をつけてくれと伝えたつもりでしたが?」
部屋に入った挨拶無しの開口一番、ライツが怒気を込めてそう問いかけると、神官長は青ざめた顔で深く頭を下げた。
「だ、大丈夫です。身代わりを置いてきました。私は王城の神殿にいることになっておりますので」
「大体、何をしに来たんですか?」
「新たな御神託を賜りましたので、それを救世主様にお伝えしたく」
「御神託?」
ライツは土下座をして神に謝罪し、それ以後、神の間に足を運び続けている愛那のことを思い出し怒気をおさめた。
ライツ自身、愛那と出会うことが出来て以後、神託付きだった【鑑定】が【鑑定】のみになったため、神の言葉をきくことが出来なくなっていた。
「神は何と?」
「申し訳ございません。今回の御神託は救世主様のみに伝えるよう、いわれてますので」
「……マナを悲しませるような内容ではないだろうな?」
「それは……大丈夫でございます」
「ライツ」
そこにソファに座るリオルートから声がかけられた。
「とりあえず、座れ。緊急の内容ではないようなので、御神託は後にさせてもらう。ルザハーツ家当主として、今後の方針について話し合いが必要だと感じていたところだ」
部屋の中には四人のみ。
リオルートと神官長、ライツとハリアスだ。
レディルは正体を明かさないまま、とりあえず別室に隠れているよう言われていた。
「そういえばマナの初討伐はどうだった?」
「……それが、スライムの討伐までは順調だったのですが」
「何か問題が?」
「草むらの中にいて姿が見えず、はっきりとは言えませんが、おそらくラグマッツだと思います」
「ラグマッツ? あの? いきなり突進してくるのはやっかいだが、危険性は低いし、討伐に苦労するような魔物ではないだろう?」
「ええ。討伐はしたのです。したのですが……」
「?」
首をかしげるリオルートへ、ライツがその時の状況を話す。
「マナが魔物の気配に異常に反応して、魔法を暴発……というか、それこそ通常騎士十名で討伐するメディラルを仕留める位の魔力で一撃。……その後、その場の形状が少し変わってしまったので、元に戻すのに少々時間がかかってしまいました。まあ、地の魔法に長けたハリアスがいたので殆ど任せてしまったが」
ライツの視線を受け、ハリアスが微笑みを返す。
「……そうか」
「マナの魔法の才能はとても高いものです。魔力操作の覚えも早い。平常心であれば、どんな魔物でも討伐は容易だと感じます。しかし……」
「魔物の気配に異常な反応、だったか?」
「えぇ。魔物の気配の殆ど感じないスライムでは全く問題なかったのですが、あの反応は異常です。おそらく、俺達が感じているものとは違うのではないかと思います。すごく気持ち悪く感じるらしく。全身で拒否反応を示していました」
リオルートが拳を口元に当て、眉を顰める。
「……それは、困ったな」
第17話 こういうことは、理屈じゃないのね。
着替えを終えた愛那は自室へと戻っていた。
一人になりたいと伝え、ナチェルとモランには部屋の中にいてもらっている。
そして自分はバルコニーの椅子に座って夕暮れ時の空を見上げていた。
(どうしよう……)
救世主だからという驕りか、楽しみにしていた初の魔物討伐にこんな結果が待っていようとは……。
あんなに気持ち悪く、おぞましい思いをしたのは生まれて初めての経験だった。
もし自分が猫だったら、あの時全身の毛を逆立てていたことだろう。
(今だったら、あの時のみんなの気持ちがよくわかる……)
以前愛那は、部活の合宿所で現れたゴキブリに、みんなが阿鼻叫喚する姿に驚かされたことがあった。あの時はまかせろとばかりに率先して退治し、ヒーローのようにみんなに尊敬され感謝されたものだ。
(ゴキブリなんて、特に害があるわけでもなし、直接触るのは病原菌があるかわからないから遠慮したいけど、あそこまで嫌われる意味がまったくわからなかった。けど、こういうことは、理屈じゃないのね)
スライムの時は気配があまりに微弱なものだったので、上手く魔物の気配を感じることが出来るか不安だったというのに……。
(本当にどうしよう……。訓練すればあの気配に慣れて平気になることが出来るのかな?)
愛那は憂鬱な気分でがっくりと肩を落とし、溜め息を吐いた。
「というわけで、マナは今すごく落ち込んでいるんです。明日も行く予定でしたが、今日のような暴発の危険を考えると、中止した方がいいかもしれません」
「人的被害の可能性を考えれば、その方がいいだろうな」
ライツの意見にリオルートが同意する。
「こういった前例はないので、魔物の気配に慣れてもらうまでにどれくらいの時間がかかるのか、わかりませんね」
ハリアスの言葉にライツが頷く。
「救世主としての役目を果たすということに前向きなマナのことだから、頑張ってはくれるだろうが、正直、俺としては彼女に無理はさせたくない」
「あの……」
そこに、ずっと無言で聞いていた神官長がおずおずとした口調で会話に参加してきた。
「ということは、救世主様の活躍は当分先のことになると、理解しておいた方がいいということですか」
神官長として、魔物被害が長引くだろうというこの重要な情報は、国王へと持ち帰らなくてはならない。
「いや……」
そこで何か考えついたのか、神官長に否定の言葉を吐いたのはライツだ。
「その必要はないだろう。マナに無理を強いることなく、救世主としての役目を果たす方法がある」
「え?」
「本当ですか!?」
第18話 マナの魔力量
「簡単な話だ。マナが直接魔物を討伐する必要はない。俺がやる。俺とマナには共通スキル【供給】がある」
ライツの言葉に「そうか」とリオルートが頷く。
「マナの魔力を使うことが出来るなら、おまえが一日に討伐出来る数を増やせるということだな」
「そうですね。私もそのようにするのが一番かと思います。マナ様を危険からお守りする上でも」
「お待ちください」
そこに神官長が声を上げた。
「その、救世主様の魔力量はどれほどのものなのでしょう? すでに数値を確認済みですか? ライツ様やレディル様と同等か、それ以上の魔力をお持ちなのでしょうか?」
ライツがスキル【鑑定】を持っているということを神官長は知らない。
神官長の言う数値確認とは【鑑定】での数値ではない。
現在の魔力量を数値化する手段は、同じ魔力量と定められた魔法を魔力切れの症状が出るまでひたすら繰り返す。その繰り返した数がその者の持つ魔力量とされている。
つまりそのやり方で自身の魔力量を数値化しようとすれば、魔力量の大きい者ほど時間がかかるということになる。しかも単調ゆえに精神力が削られる作業となるのだ。
「……マナの魔力量は、俺とレディルの魔力を合わせても届かない程、膨大なものだ」
ライツの言葉に神官長は「おお!」と感嘆の声を上げた。
「神官長。間違ってもマナの魔力量を調べようなんて考えないでくれ。俺やレディルでさえ音を上げかけたあれをマナにさせようなんて、拷問にも等しいのだから」
ライツからの威圧に神官長は従順な態度で「はい」と答えた。しかしその後、ふと首をひねった。
「……あの、では、数値確認をされていないとなると、なぜ救世主であるマナ様の魔力量が、ライツ様とレディル様を合わせたものよりも大きいとわかったのでしょう?」
「…………」
ライツは口を噤み、兄へと視線をやった。
リオルートはそれに小さく首を振って応え、神官長へと言葉を投げた。
「神官長、その答えは後回しにさせてもらおう。それよりも、ルザハーツ家当主として、この国の住人の一人としても、今回の異世界召還を実行した国王陛下と王太子、そしてあなたにお訊きしたいことがある」
「は……何でしょうか?」
緊張した顔で神官長が姿勢を正す。
「魔物が大量発生し、危機的状況のこの国を救うため、禁止されていた異世界召還が強行された。そして無事救世主様を召喚。その際のあなた方の不手際に関しては今回は置いておきます。私がお訊ねしたいのはその先。無事救世主様のお力でこの国の危機を防げたとしましょう。さて、あなた方はその後、どうするおつもりだったのでしょう?」
「どうする、とは?」
「救世主様のお立場を、どのようにするおつもりだったのかと訊いているのです。周知の通りこの国では魔力量の大きい者こそ国の王として相応しいとされています。ということは、現状、救世主であるマナ様こそがこの国の王に相応しく、彼女を女王として望む者達が今後大勢出てくるだろうということです。……そのことをあなた方はどうお考えだったのか、ぜひお聞かせ願いたい」
第19話 ……何故?
「…………」
神官長サーゼンはしばらく口を噤んだまま考え俯いていた。そして、顔を上げリオルートへと口を開いた。
「その問いに対する私の答えはありません。国王陛下と王太子殿下からの命令で異世界召還の手はずを整え実行したのは私です。が、そのことについてのお考えは何も聞かされておりません」
「進言もしなかったと? まさかと思うがまったくの考え無しだったとは思いたくないな。……大体、異世界召還をするのであれば最低でも公爵家の同意を得るのが道理ではないのか?」
「……陛下はずっと魔物被害に関する王家としての対応、特にバリンドルからの催促に頭を悩ませている御様子でした。禁止されていた異世界召還を強行したことを考えれば、もしかしたら精神的に追い込まれ、正常な判断能力を欠いていたのかもしれません」
「バリンドル家か……」
御三家の一つ、バリンドル公爵家と王家とは他の御三家に比べ一番結びつきが弱い。
元々一国の主だったバリンドル家が今の王家の臣下となったのは、初代国王である救世主の力、魔力があってこそ。その当時と同じこの国難に対応する力なくして王家といえるのかという精神的重圧が国王にあっただろうことは推測出来る。
「レディルは何も考えてなかった可能性が高い。魔物の異常発生のせいで延期されているルーシェとの結婚のことばかり気にしていたようだしな。……しかし、だとしたら、考え無しにも程がある」
ライツは眉間を寄せ、片手で頭を抱えた。
そんなライツへとリオルートが声をかける。
「ライツ、そのレディル王太子のことだが……」
「?」
「現在この城内にいらっしゃる」
「……は?」
その低音に神官長は背筋を正した。
「この部屋を出て左正面の部屋にいる」
「何故?」
一緒に来ただろう神官長へとライツは問うた。
「わ、私はお止めしたのだが、どうしても救世主様とライツ様に謝罪がしたいとおっしゃって! もちろん身分を隠し、変装してきているのでそこはご安心ください!」
「……何故?」
納得がいかないのか、ライツは同じ台詞を繰り返した。
「お、おそらく、ライツ様がこちらの領地へお帰りになった後、登城し今回の経緯を知ったルーシェ嬢に長くお説教を受けたご様子でしたので、それが理由かと」
「…………」
しばらくの沈黙の後、ライツはリオルートへと一礼し、無言で部屋を出て行った。
それを見送ったリオルートが息を吐き「やれやれ」と言って背もたれに体を預けた。
「頭の痛い問題が山積みだな」
第20話 痛い!
「いだッ! いだだだたたたッ! やめっ! すまな……ッ! 痛い! ライツっ!」
あまりの痛みにレディルが悲鳴を上げた。
レディルの頭をライツの拳が左右に挟み、グリグリと押しつけている。
つい先程までレディルは、リオルートが用意したこの部屋で大人しく一人待機していた。
そこに突然扉が乱暴に開かれ、レディルは驚き、見るとそこには無表情のライツが立っていた。
(ひッ!)
「ラッ……ライツ」
慌てて立ち上がったレディルの元へスタスタと入室してきたライツは、無言のまま近づいてきて……今の状態である。
「痛い! 痛ッ! ライッ!」
しばらくして気が済んだのか、ライツが拳を離すとレディルは崩れ落ちるようにソファへと倒れ込んだ。
「っう~。……おまえ、仮にも……王太子に対して……」
それを無視してライツは一人掛けのソファに座ると「レディル」と声をかける。
「俺は昔からずっと、おまえを次期国王にするために動いてきた」
レディルが顔を上げてライツを見る。
「だが、これから先も同じと思うな」
「……それは、召還された救世主のせいか」
「おまえ、何も考えてなかっただろう? 救世主を召還するということは、自分の立場を揺るがすことになるだろうことを。……どうせルーシェに言われて気づいたんじゃあないのか?」
「…………」
その通りだったので返す言葉がない。
『レディル様! あなたはその覚悟があって救世主様を召還されたのですか!?』
ルーシェに言われた声が再びレディルを責める。
「……あの少女は、この国の王になることを望んでいるのか?」
レディルのその問いに、ライツは一瞬思考が止まった。
(何を言っているんだこいつは)
「……それを彼女が望むなら、俺は彼女の望むようにするだろう。だが、おそらくマナはそんなことに興味は無い」
「そんなこと……。だが、先程おまえはもう俺のためには動かないと言ったではないか!」
レディルはそう叫んで悔しげに唇を噛んだ。
ライツが溜め息を吐く。
「レディル。おまえは本当に反省しているのか? ここには何をしに来た? マナはこの国のために頑張ってくれているというのに……」
「すっ! ……すまない」
怒気をはらんだライツのそれに、レディルは体勢を正して頭を下げた。
「それに、理解してなかったようだな。俺は彼女に暴言を吐いたおまえとマナを会わせるつもりはなかったんだが?」
「ル、ルーシェに、一刻も早く誠心誠意、頭を下げて謝罪してこいと言われて……。それに、王家と救世主とが仲違いした状態のままではまずいと。このままでは王家はライツ、おまえやルザハーツ家とも距離を置くことになる。……父上もそのことをすごく気にしている様子だった」
「……召還された救世主については、俺なりの考えがあった。まずは兄に相談した上で陛下に連絡を取ろうと思っていたんだ。だが、まさかこんな早くにおまえと神官長が、このルザハーツ城まで来るとはな」
「考え?」
ライツは立ち上がると「二人で話す内容じゃない。移動するぞ」と言ってレディルを促す。
そして部屋を出る前に言い忘れたことがあったとばかりにライツは振り返った。
「言っておくが、謝罪がしたいからといってマナに勝手に会おうとするな。おまえと会うか会わないかは、彼女に決めてもらう」