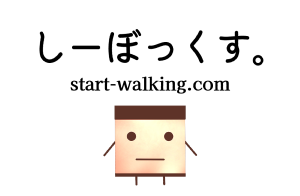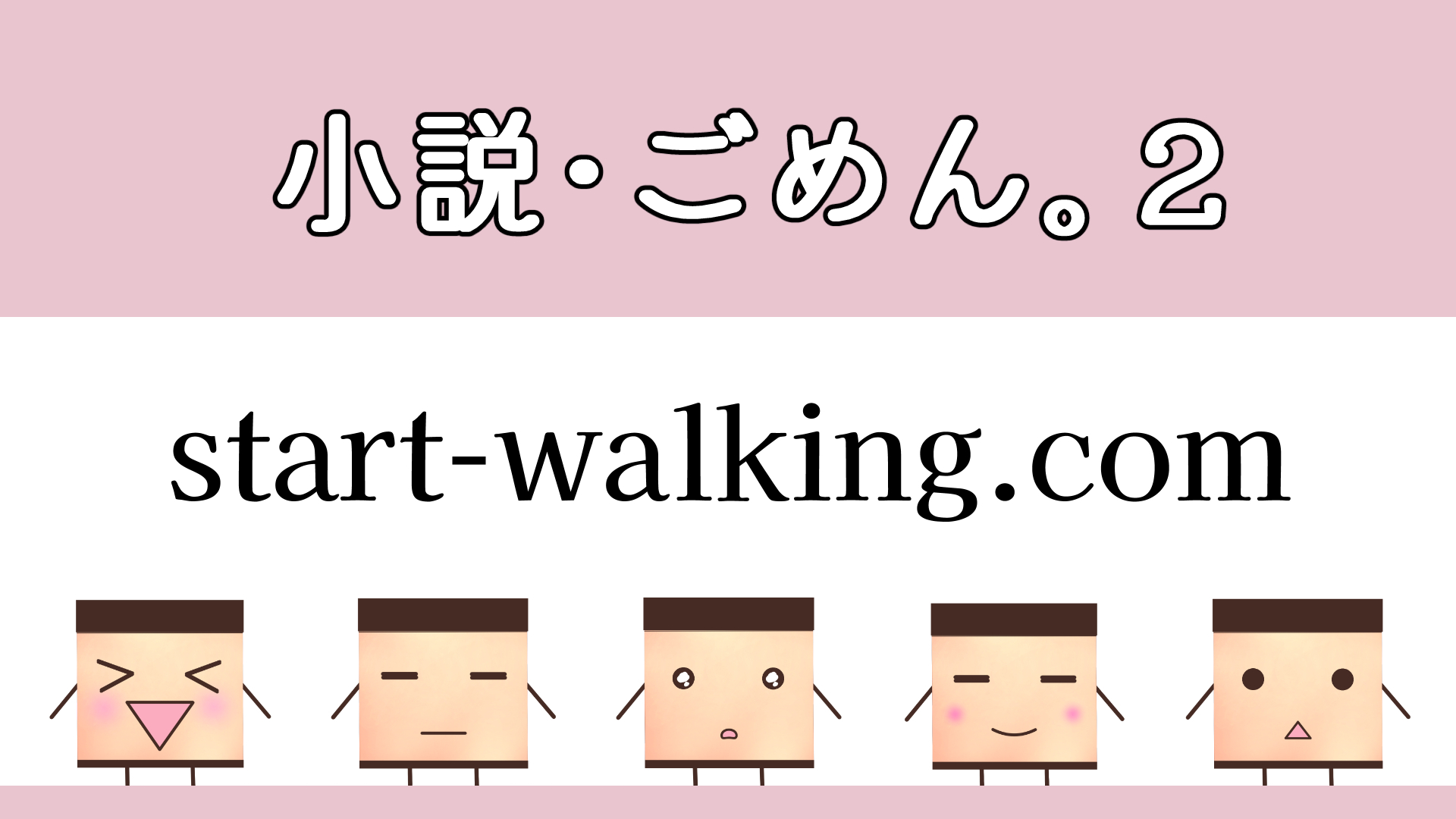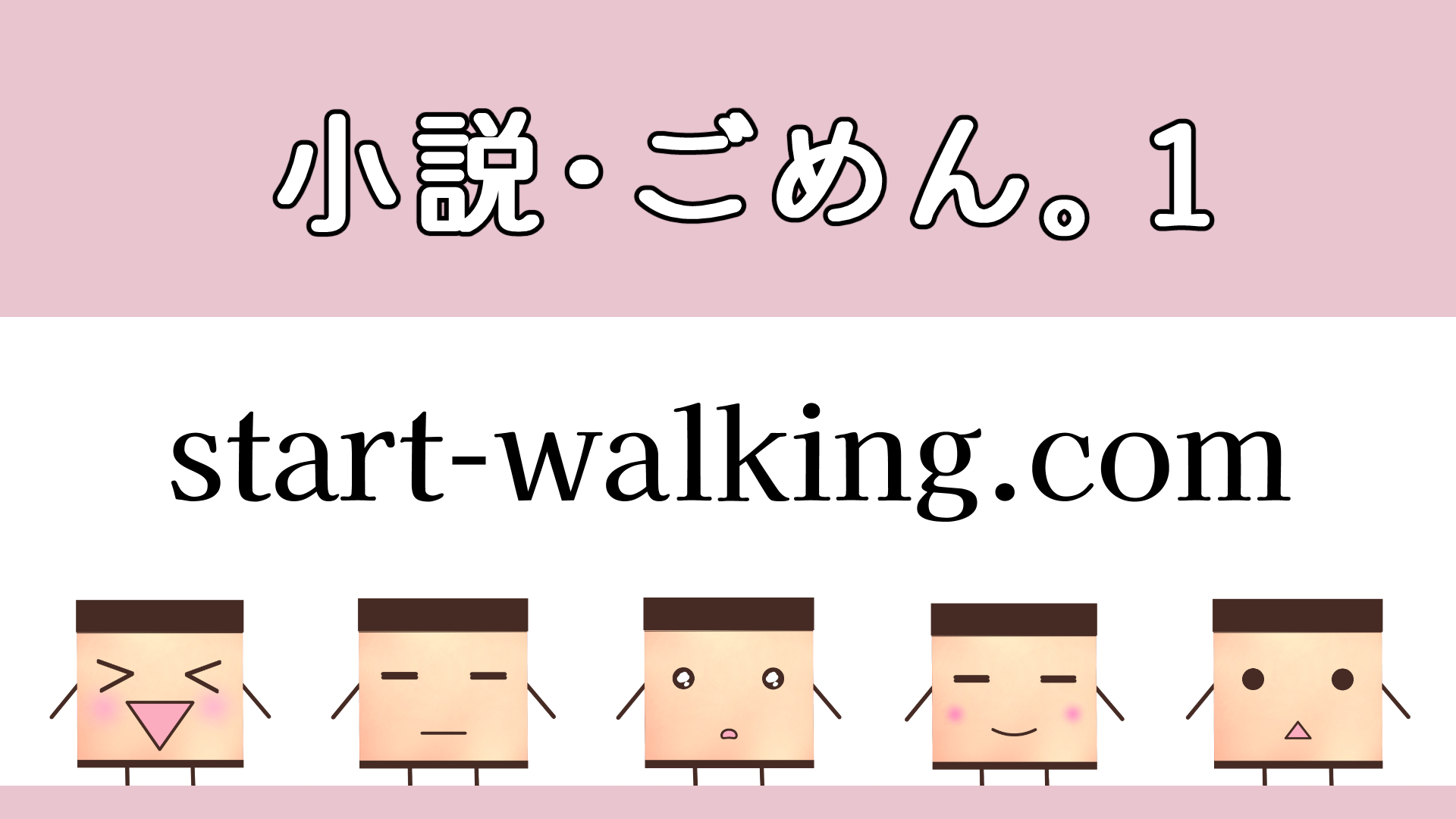第1話 どういうことでしょうか? レディル様?
サージェルタ王国、王城。
ライツ・ルザハーツが救世主の少女を連れてルザハーツ領へ帰ったその日の夕刻。
異世界召喚の知らせを受け、アレンジア領から馬車で駆けつけたルーシェ・アレンジアが登城した。
「ルーシェ!」
玉座の間。
国王ランドルフ・フォル・サージェルタに挨拶をすませたばかりのルーシェの元に、王太子レディル・フォル・サージェルタが姿を見せた。
婚約者であるレディルを視界に入れたルーシェの顔が微かに顰められる。
ルーシェはここに到着した時点で、王城にいるアレンジア家の手の者から報告を受けていた。
異世界から召喚された救世主の少女にレディルが暴言を吐き、救世主の不興を買ったということを。
そして、そのせいで救世主が姿を消し、未だ行方不明のままだということを。
実際は行方不明だった救世主はライツが見つけ出していたので、未だ行方不明というのは嘘だ。
しかし国王はライツに言われた(脅された)通り、救世主の居場所を公にしていない。
現在、表向き救世主に関して箝口令が敷かれた状態だ。
「……ルー」
レディルは不機嫌なルーシェの表情に気づき足を止めた。
そんな二人を見て国王が声をかける。
「レディル。国の非常事態というべきこの時だからこそ、王太子として婚約者と二人きりで話さなければならないこともあるだろう」
「……はい。ありがとうございます、父上」
今は王太子の仕事よりも婚約者へのいいわけを優先して来いということだ。
一礼したレディルはルーシェへと近づき左腕を差し出した。
ルーシェは無言でその腕を取り、レディルのエスコートで二人は退場していった。
無言のまま防音の魔道具が置かれた部屋に入室した二人。
扉が閉ざされるとすぐに手を離したルーシェがレディルへと腕を伸ばした。
閉じた扇子の先端がレディルの顔の正面でピタリと止まる。
「……どういうことでしょうか? レディル様?」
ルーシェに見つめられたレディルは、気まずげな顔で一歩後退した。
「……ルーシェ」
「二日前、初代国王であるロベリル様が禁止としていた異世界召還がこの王城の神殿で行われ、異世界から新たな救世主様が召喚されたと聞きました」
「……そうだ」
「召喚された救世主様は、わたくしたちと同じくらいの若い女性だったとか?」
「そ、そうだ」
「そうですか。……では、その救世主様にレディル様が暴言を吐き、怒った救世主様が姿を隠されたという話も……本当ですの?」
威圧的なルーシェの眼差しに、もう一歩後退したレディルがゴクリと喉を鳴らした。
第2話 少し大人になりました。
ルザハーツ城。
ここに異世界から召喚された少女、里上愛那(さとうえまな)が滞在している。
朝食前に城の最上階にある神の間へと足を運んだ愛那は、ニコニコとした笑顔で神へと語りかけた。
「おはようございます神様。とても良いお天気ですね。魔物を討伐するならこんな日が最適だとライツ様に聞きました。私も一刻も早く魔物討伐に参加するため、魔法を使いこなせるよう頑張りますね。…………神様! 私は救世主として神様の期待に絶対に応えて見せます! どうか! どうか安心して見守っていて下さいね!」
後半はどこか必死さを感じる語りかけではあったが、後ろに控えている愛那の護衛であるナチェルの表情は崩れなかった。
愛那がこの神の間で土下座をしたのが二日前。
昨日はルザハーツ家当主リオルートから、いつでもここに来ていいという許可をもらい、愛那は扉の契約者の一人となった。
勘違いで神様へ暴言を吐いてしまった愛那。
反省し神様に許しを請う愛那に、事情を知る皆は優しく協力してくれている。
(おじいちゃん、おばあちゃん。元気にしていますか? 愛那は異世界に来て、少し大人になりました。理不尽な思いをしたからと、すぐに感情を爆発させるのは利口じゃないと知りました。もし真実が違っていた場合、とんでもなく後悔することになるから……!」
神の間を出て階段を下る中、愛那がナチェルへと訊ねる。
「ナチェルさん。私がライツ様と一緒に魔物の討伐に参加出来るのって、どの位先になりますか?」
「マナ様の魔力と攻撃魔法は即戦力になりますので「すぐにでも」と言いたいところですが、魔物についてもう少し勉強していただく必要があります。それでもいきなり騎士団の討伐に参加というのは考えられませんが」
「え?」
愛那が足を止めてナチェルを見る。
ナチェルは真面目な顔で答えた。
「危険ですので」
「でも……」
「ライツ様が決めることではありますが、まずは危険の少ない弱い魔物を討伐することから始める必要があると思います」
「なるほど。そうやって徐々に強い魔物も倒せるようになるということですね!」
(そうよね。勇者のいるゲームの世界だっていきなり魔王に挑んだらすぐに死んじゃうわ! 初めは弱いモンスターから! レベルはないけどレベル上げしなきゃ! これぞ王道!)
「……それで、その弱い魔物ってどんな魔物なんですか?」
「そうですね。まずはスライムでしょうか」
それを聞いた愛那の目が大きく見開き、好奇心にあふれた笑顔を見せた。
「スライム!」
第3話 スライムって仲間にすることは出来ますか?
スライムと聞いて愛那が思い出したのは、漫画の主人公に懐いていたポヨポヨ動く愛らしいスライムの姿だ。
「ナチェルさん! スライムって仲間にすることは出来ますか?」
キラキラとした笑顔で愛那が訊ねる。
「は?」
ナチェルが戸惑いの表情を見せる。
「え? 仲間? スライムを、ですか?」
その戸惑いこそが答え。
(しまった! 漫画の世界をそのまま口に出してしまった!)
愛那は馬鹿なことを訊いてしまったとすぐに反省して手と首を振りながら「ごめんなさい、何でもないです」と謝った。
冒険者ギルトにあった攻撃魔法を吸収する魔道具はこの城にもあり、魔物を討伐するのに必要な攻撃力があることは、昨日証明してみせた愛那である。
その時、明日は実戦かとライツと共に魔物の討伐に出るつもりでいた愛那に、その前に確認しなくてはならないことがあるからと止められた。
今日はその確認とやらをするらしい。
朝食の後、ライツはハリアスとモランを連れ、騎士団の者達と共に魔物の討伐に出た。
ライツの騎士姿を見た愛那が見惚れてくれたことが嬉しかったのか、上機嫌で出かけていった。
城で留守番の愛那は、自分の部屋のソファにナチェルと並んで座っている。
「それで、何の確認が必要なんですか?」
「マナ様は、魔物と動物の違いがわかりますか?」
「……魔物と動物の違い?」
首を傾げ愛那は考えようと試みたが、ふと気づいてすぐに考えるのを放棄した。
わかるはずがない。
魔物なんて見たことないし、ここは異世界。動物でさえこの世界とあちらの世界で同じ認識なのかわからないのだ。
「わかりません」
愛那の答えにナチェルが頷いた。
「マナさまのおられた世界には、魔物が存在しないと聞いていましたので、この確認は必要だと時間を取らせていただきました」
「お手数をおかけします」
「とんでもありません」
そう言ってナチェルはテーブルの上に置いていた一冊の本を手にして開いた。
「こちらの絵が何かわかりますか?」
「……牛、ですね。隣が羊、山羊、豚、鶏」
本に描かれてある絵を指さしながら愛那が答える。
「そうです。これらは主に食用として育てられている動物です」
愛那はうんうんと頷く。
(よかった。あっちの世界と同じだわ)
「では、これは?」
ナチェルが違うページをめくり、その絵を指差し訊ねた。
そこには愛那が見たことがない生き物が描かれていた。
(牛みたいな顔に体はライオンみたい)
「見たことないです。えっと、動物か魔物かですよね?」
わからない。というのが正直な答えだ。
知らないだけで、あちらの世界にも似たような動物がいるかもしれないが。
「これはトビッカーという魔物です」
「魔物、これが……」
(そうか。困ったなぁ。魔物と動物の違いがわからないなんて。……でも、やらなきゃ!)
「わかりました。今日は私、頑張って魔物の姿形を覚えますからどんどん見せてください!」
「いえ、マナ様。覚える必要はありません。このような絵だけで判断するのは知識が無ければ私でも無理ですので」
ガクッと愛那は気勢をそがれた。
「え?」
「魔物は、近くに来ればわかります。魔物の気配を感じますから」
「えっ、気配? ……それって私もわかるんでしょうか?」
「それです。討伐の前にその確認が必要だとライツ様がおっしゃっていました。気配で察知する能力には個人差がありますが、この世界で出来ない者はいません。幼子でもわかります」
「そうですか……。試してみなきゃですね」
「はい。まずは危険の少ないスライムで試します。あれも魔物ですから」
第4話 歓迎されないことぐらい当然わかっている。
愛那とナチェルが魔物についての話をしていると、部屋の扉のノック音がした。
ナチェルが立ち上がり、扉を開き対応する。
「準備が整いました」
部下の女騎士からの報告に頷くナチェル。
「そうか。すぐに行く」
そう言って扉を閉じ、振り向いて愛那へと声をかける。
「ではマナ様。スライムが届いたようなので、部屋を移動しましょう」
「えっ! スライムが?」
(届いたって、宅配便ですか!?)
「研究所に手配して取り寄せました。魔物の中でもスライムだけは研究材料として生きたまま捕獲することを国が認めているんです。勿論許可された研究所のみの話ですが」
「へぇ。そうなんですね」
(そうかぁ……さすが異世界。やっぱり知らないことがいっぱいね)
当たり前のことを再認識した愛那は、ナチェルに促され、部屋を出てスライムのいる場所へと向かった。
その頃、王城を出てルザハーツ領へと向かう馬車の中に、レディル王太子の姿があった。
同乗しているのは神官長である。
レディルはいつもの王太子らしい格好ではなく、身分を隠すために神官の衣服をまとっていた。
「レディル殿下。やはりまずいのではないでしょうか? ライツ様もいい顔をされないと思いますよ? せめて一ヶ月、日を置いたら救世主様の怒りも少しは和らいでいるかもしれません。今からでも城に戻られた方が……」
「うるさい。歓迎されないことぐらい当然わかっている。わかってはいるが……」
レディルは自分の額を指で擦った。
今は残っていないが、ルーシェの扇の先端がレディルの額をグリグリと強く押さえてできた赤い跡は、なかなか消えなかった。
あの後、さんざんルーシェに叱られたことを思い出したレディルは、深く溜め息を吐く。
(気が重い。俺だって好き好んでルザハーツへ向かっているわけではないのだ!)
逃げられるものならこのまま逃げてしまいたい。
ライツはまだ怒っているだろうし、何より救世主の少女はいったいどうしたら許してくれるのか? ……いくら考えてもさっぱりで、まったくいい案が出てこない。
うつろな眼差しを神官長へと向けたレディルが口を開いた。
「だいたい神官長、そなただって私と似たようなものだろう」
あの時、異世界召喚を行った王と神官長も同罪だとライツは言って去って行ったのだ。
神官長は「いいえ」と首を振った。
同じにされては困ると言いたげに神官長は胸を張った。
「私には、新たな御神託を救世主様にお伝えするという、大切な役目がありますので」
第5話 これがスライム……。
「わぁ」
愛那が声を上げた。
視線の先は、テーブルの上に置かれた透明なケースの中にいるスライムだ。
ケースのサイズは縦横奥行き共に五十センチ位で、その中にいるスライムの大きさは約三十センチ。
そのからだは透き通った薄い水色で、その中心部分に青い石のようなものが見える。
「これがスライム……」
(綺麗。ゼリーみたい。柔らかそう。指でつついてみたい! ……だけど、そっかぁ。私が想像していたスライムと全然違う)
肩を落とし溜め息を吐く愛那。
(あの漫画のスライムみたいにピョンピョン跳ねたりしないのね。ナメクジとかカタツムリみたいな動きだわ。それになんといっても……顔がない!! この世界のスライムはのっぺらぼうなのね! これじゃあ表情がわからない! 私が期待していた愛らしいスライムはいませんでした! 残念!)
「マナ様。わかりますか?」
「え?」
声をかけられ愛那が横に立つナチェルへと顔を上げた。
「スライムの気配を感じますか?」
(そうでした!)
「ちょ……っと、待って下さいね」
愛那が目を閉じて気配を感じるよう感覚を研ぎ澄ます。
「…………?」
首を傾げて愛那がまぶたを開いた。
「よくわかりません」
「そうですか。わかりました。では」
そう言ってナチェルが手を上げると、布をかぶせた中の見えないケースが二つワゴンに乗せて運ばれてきた。
「この二つの内どちらかにスライムが入っていますので、マナ様にはそれを当ててもらいます」
(わ~。何だかクイズ番組みたい~。……って、違う! 魔物の気配を感じ取るために必要な能力なんだから真面目にやらなきゃ!)
愛那は二つのケースの間へと移動して目を閉じた。
(気配。……魔物の気配。……右? なんて表現したらいいかわからないけど、右の方に何かいる気がする。左は……ない)
「こっち、かな?」
目を開けた愛那が右を指さして言うとナチェルが頷いた。
「正解です」
二つの布が外されケースの中が見える。
片方は空で、愛那が選んだケースの中には薄い赤色をしたスライムがいた。
中心には赤い石のようなものが見える。
愛那は浮かない顔で正直に話した。
「ナチェルさん。今は当たりましたが、なんとなくといった感覚でしかわかりませんでした。自信を持って魔物の気配がわかるとは言えません」
(どうしよう。救世主なのに……)
そんな気落ちしている愛那へ、ナチェルは微笑を浮かべて「大丈夫ですよ」と伝える。
「魔物の中でもスライムの気配が一番感じにくいものなんです。危険な魔物は強ければ強いほどその気配を感じやすい。だから、大丈夫です」
その言葉に、愛那はホッとして笑顔を見せた。
「そうなんですね。よかったぁ」
第6話 魔石
ナチェルがスライムのケースが置かれているテーブルの後ろに立つ。
「魔物の気配感知については問題ないようですので、次は魔物の生態についてお話しします。マナ様はどうぞおかけください」
その言葉に「はい」と応えて用意された椅子へと座る愛那。
(なんだか学校の授業みたい)
ここはルザハーツ城の騎士専用会議室だ。
ナチェルの部下の女性騎士が空のケースを片付け、テーブルの上に二つのケースが並べられた。
「スライムはとても興味深い魔物として研究され続けています。マナ様。このスライムを見て気になることはありますか?」
「えっ? ……と」
(わかっています。「さわり心地を知りたい!」とか「何で顔がないの?」とかじゃなく、ですよね?)
「色の違いが何なのか? それと、中心部にある石について、ですね」
愛那の答えに頷くナチェル。
「はい。まずこの中心部にある石についてですが、これは魔石です。魔物の体内に必ずあるものです。魔物は命が絶たれると魔石だけが残ります」
「魔石だけ?」
「そうです。死んだ後、肉体は魔石に吸収されますので」
(肉体を吸収……? ということは、魔物を素材とした防具とかは存在しない? ……って、またあっちの情報が!)
漫画やアニメの異世界知識とつい比べてしまう癖が抜けない。
「つまり、魔物を討伐すると魔石だけが残る。ということですね」
「その通りです。強い魔物であればあるほど、石のサイズが大きく、その魔石の価値が高くなります」
(そっか。討伐した後、魔石だけ手に入れて遺体の回収なんか必要ないというのは楽でいいのかも)
「魔石は何に使われるんですか?」
「主に魔道具ですね。いろいろありますが、あそこにあるあれもそうです」
そう言ってナチェルが指し示した先には壁に掛けられたランプ。
「ランプに使用している魔石は、ちょうどこのスライムの魔石のように小さなものになります」
「なるほど、これがランプに」
そう言って愛那がスライムの中心にある魔石を見る。
「いえ、マナ様。この二匹の魔石はランプには使えません」
「え?」
「そこでマナ様が先程おっしゃっていた、色の違いについてです」
愛那が頷く。
「ランプには、光の魔力石である黄色いスライムの魔石が使用されています」
「魔力石……。つまり、それぞれの魔法の属性によって色が違うということですか?」
「そうです。マナ様はすでに、風・火・水・地・光・闇。これらの魔法を習得しておられます。この二匹のスライムがどの属性のものか、わかりますか?」
「え、っと」
(これは、見たままのイメージでいいんじゃない?)
「青が水。赤が火。ですか?」
ナチェルが正解という風に微笑みながら頷き(よし! 当たった!)と愛那が笑顔を見せた。
「風は緑、火は赤、水は青、地は茶、光は黄、闇は黒。そして……」
「そして?」
「聖は紫です」
「聖魔法って、怪我や病気を治療する魔法のことですよね?」
「はい。聖魔法を使うことの出来る魔法使いはとても少ないので重宝されています。同じように紫のスライムはめったに見つけることが出来ず、幻のスライムとも呼ばれています。研究所からの捕獲報酬額が金貨五百枚で、三年に一匹見つかるか見つからないかという珍しいスライムです」
「それは……宝探しみたいに夢のあるスライムですね」
(……なんて言ってみたけど、実際金貨五百枚ってどれだけの価値が? ……神様! 私この世界のこと、もっとたくさん勉強しますね!)
第7話 スライムは素手で触れてはいけない。
この日、昼まで愛那は魔物について勉強をした。
まずスライムは素手で触れてはいけないということ。
なぜならばスライムは攻撃はしてこないが、触れた箇所をジワジワと溶かし吸収するという危険な魔物だからだ。
スライムを捕獲したり触れたりするには特殊な手袋が必要ということで、直接触れてみたかった(つついてみたかった)愛那は、内心とてもがっかりした。
それから見た目だけで属性のわかる魔物はスライムだけということも教わった。
同種の魔物であっても属性が同じとは限らない。
討伐後手に入るのは風・火・水・地・光・闇という六種類の属性の魔力石。
聖の魔力石は紫色のスライム以外から発見されたことはないらしい。
魔物は従来、人の持つ魔力を警戒して人前に姿を現すことは少ないと云われている。
だが現在は、魔物の数が多くなっている異常事態。
山奥に住んでいた魔物たちが人前に姿を現し、中には攻撃魔法を使う危険な魔物も存在する。
一部だけだが、魔物による詳しい被害状況を知った愛那は、改めて身を引き締める必要があることを感じていた。
午後になったばかりの頃、討伐に出ていたライツ達が帰って来るという先触れに、愛那はナチェルと一緒に城の入り口へと向かった。
愛那はルザハーツ家の当主リオルートも認めたライツの恋人として、このルザハーツ城に滞在している。
そんな愛那に興味と関心を寄せる者は多いが、このルザハーツ城に務めている者達は、きちんとした教育を受けており、それをあからさまにする者はいない。
「あっ」と、愛那が遠目で騎乗したライツの姿を見つけた。
(あぁ……やっぱり格好良い……。じゃなくて、怪我はなさそう。大丈夫、だよね?)
愛那に気づいたライツが笑顔を見せる。
馬から下りたライツが、足早にまっすぐ愛那の所へと進み、ふわりとその身体を抱きしめた。
「ただいま、マナ」
一斉に浴びる周囲の視線に固まった愛那は、顔を赤くして動揺しながらも「お、おかえりなさいませ」と応えた。
ライツは愛那の両肩に手を置いたまま体を離し、愛しげに愛那を見つめる。
「俺が留守の間、何か困ったことはなかった?」
「いえ、なにも。それより、ライツ様や皆様方は大丈夫でしたか? 怪我などは?」
「大丈夫だよ。ありがとう」
そう言ってライツは愛那の頬に口づけを落とした。
(きゃあああああああ!)
声にならない悲鳴を上げた愛那を笑顔で見つめながら。よしよしと頭を撫でたライツは誰が見てみも上機嫌で、周囲を唖然とさせていた。
第8話 ルザハーツ騎士団団長
「ライツ様」
ライツの胸に頭を預けて羞恥に震えていた愛那はその声に顔を上げた。
そこには愛那が初めて見る騎士の男。
(制服の装飾から見て、騎士団の上の人? ライツ様より年上だろうけど、まだ二十代かな?)
「ああ、フォルフ。丁度いい。紹介しよう」
ライツに促されて愛那はそのフォルフと呼ばれた騎士と対面する。
「マナ。彼はルザハーツ騎士団団長、フォルフ・ダルソーランだ。フォルフ、彼女の名はマナ。家名は事情があって今は明かせないが、将来俺の妻になる女性だ。覚えておいてくれ」
その瞬間、ざわっ、とこの場に衝撃が走った。
(…………妻!?)
愛那もライツの言葉に衝撃を受けた。
(ちょっと待って……え? 決定事項ですか? プ、プロポーズは? いえ、もちろんイヤじゃないですよ? 当たり前じゃないですか! ライツ様と結婚して夫婦になるんですよね? 当然です! ライツ様の妻の座は誰にも譲らない!)
愛那は固まったまま頭の中でパニックをおこしていたが、こちらを凝視する視線に気づくとすぐに意識を切り替えた。
微笑んで片足を下げ、両手でスカートの裾を持ち腰を落とす。
「初めまして。マナと申します」
(よし! どんなに動揺していても淑女の挨拶だけは忘れない!)
フォルフは驚いた顔をハッと改め、胸に手を当て頭を下げる。
「失礼しました。お目にかかることができ光栄です。ルザハーツ騎士団団長、フォルフ・ダルソーランと申します」
ライツは一つ頷くと、マナの左肩に手を置きここにいる者全てに知らせるように声を上げた。
「皆には随分待たせてしまったが、俺もようやくこうしてマナという運命の女性に巡り会うことが出来た。残念ながら今のこの国の状況では、すぐに彼女との婚約を公表することは出来ない。だが、だからこそ一刻も早くこの国の平和を取り戻すべく、今まで以上に尽力することをここに誓おう。フォルフ、彼女は聖魔法を除いた六属性の魔法使いであり、俺との共通のスキル【供給】を持っている」
再び周囲がざわめいた。
目を見開いて驚きをあらわにしていたフォルフが口を開く。
「六属性に、供給……ですか」
「ああ。これから先、マナは俺と共に討伐に出ることになる。だが、マナは討伐が未経験だから、しばらく経験値を上げるための時間が必要だ。どちらにせよ俺はこの先ルザハーツ騎士団の本隊とは別行動することになる。もちろん緊急要請があれば合流するが、他の領地の応援要請に応えていくことが多くなるだろう。フォルフ。ルザハーツ騎士団の総括はおまえに預ける。頼んだぞ」
「はっ。承りました」
第9話 緊張するので私からもぜひお断りしたい!
その後、ライツと愛那たちは城内へ移動した。
謁見の間で訪問者の対応をしていたリオルートに、フォルフが討伐の戦利品である魔石を献上する。
その魔石の大きさは愛那の拳二つ分くらいあり、討伐したのがかなり強い魔物だったことが想像できる。
こうして騎士団が討伐した証しである魔石を領主に献上するのはある一定の大きさ以上の魔石と定められている。
これだけ危険な魔物が領内にいたことを知らせるためだ。
(色は青。水属性の魔物ね)
献上された魔石を見つめる愛那へとライツが声をかける。
「マナ。昼食を終えたら一緒に討伐に出よう。スライムなどがいる初心者向けの場所があるからそこへ」
「は、はいっ!」
(討伐! 今日行けるんだ! わあ~、ドキドキする!)
「ライツ様」
そこにフォルフが声を上げた。
「何だ?」
「その討伐、私も一緒に同行させてもらってもよろしいでしょうか?」
(え?)
愛那がフォルフへ視線をやると、フォルフは胸に右手を当てライツへと一礼する。
「ぜひ、マナ様の実力を拝見したく」
(ええっ!?)
「フォルフ。すまないが今日は遠慮してくれ。マナは本当に討伐経験がない初心者なんだ。実力を見たいというなら今日でなくてもいいだろう?」
(ライツ様! その通りです! 緊張するので私からもぜひお断りしたい!)
「討伐初心者であることは承知しています。多大な期待を押しつけるようなつもりはありません。ただ、六属性に供給と聞いて、その実力の片鱗だけでも見てみたいというのは騎士として当然のこと。それにそれがライツ様のお相手とならばなおさらのことです」
「……明日。また同じ時間に出る。その時本隊に問題なければ同行すればいい。だが少人数しか許可しない。おまえと、おまえの側近二人までだ」
ライツの言葉に微笑し「ありがとうございます」と再び胸に手を当てたフォルフが一礼した。
(と、いうことで、明日は騎士団長さん達も討伐に同行するそうです。……こうなったら明日のためにも今日やれるだけのことはやる!)
馬車の中で闘志を燃やす愛那。
現在ルザハーツ城を出て馬車で討伐場所へと移動している最中である。
馬車の中にはナチェルと二人きり。ライツ達は馬での移動だ。
(馬。そういえば私、馬に乗れるようになった方がいいのかな? もちろん何でも頑張るつもりではあったけど……)
「マナ様? どうかされましたか?」
愛那が考え込んでいたら、その様子を見て心配したナチェルがそう問いかける。
「あの、私も馬に乗れるようになったほうがいいのかな? と思いまして。私が馬で移動することができれば馬車は必要ないでしょうし。けど、今まで一度も乗馬経験がないので心配になって」
それを聞いたナチェルは「あぁ」と言って微笑んだ。
「そのような心配は必要ありません。もともと怪我人が出た場合に備えて魔物討伐に馬車は必須ですし、馬に乗る必要があれば二人乗りをすればいいのですから」
「二人乗り……」
「そうですね。一度も馬に乗った経験がないならば、不安でしょうから二人乗りの練習はしておいた方がいいかもしれません。私で良ければお付き合いいたします」
第10話 もしかして、からかっていませんか?
到着した馬車から降りた愛那が周囲を確認して首を傾げる。
(え? こんな見渡しのいい緑色の草に覆われた場所に魔物が?)
「マナ様。ここに彼等と馬車と馬を待機させ、私達は目的地まで歩きます」
そうナチェルに言われ、この草原に魔物が現れる想像が出来なかった愛那が(なるほど)と頷いた。
ナチェルの言う彼等というのは馬車の御者二名と六名の従者達。
馬を従者に任せたライツとハリアスとモランが、愛那とナチェルの方へ歩いてくる。
魔物討伐はこの五人で行くことになっている。
「マナ」
正面に立ったライツが愛那の両肩に手を置いて、顔を近づけ言い聞かせるように話し出す。
「ここから先は俺の傍から離れたらダメだ。魔物が出てきても指示するまでは何もしないこと。……わかった?」
「……はい」
どうにか答えて歯をぐっと噛みしめる。
(ライツ様! お願いだからもうちょっと離れて下さい! ときめくから! 心臓がもたないから!)
二人きりならともかく、周囲の目がある場所で取り乱したくない。
そんな平常心を装う愛那を見つめるライツの表情がフッと緩んで口元が楽しげに笑んだ。
「……ライツ様?」
愛那が疑いの眼差しを向ける。
「もしかして、からかっていませんか?」
ドキドキしているのに気づいていて面白がっている?
「からかう?」
ライツが思いがけないことを訊かれたとばかりに首を傾げた。
(あれ、違った?)
見つめる愛那の眼差しにライツが照れくさそうに笑う。
「ダメだな俺は。マナが傍にいるだけで幸せでどうしても口が緩んでしまう。今から魔物討伐だというのに……。すまない。気を引き締めるよ」
(ちょっと待ってください! 顔が! 顔が熱い!! 誰か! 誰か助けて!)
愛那が周囲に視線をやるが、おかしなことに誰とも目が合わない。
残念ながらここにいる面々は、この数日で甘い空気を振りまくライツに慣れつつあり、優秀な彼等は、こういう時にそっとその場の空気になる術を身につけていた。
「じゃあマナ、行こうか。疲れたら言ってくれ。無理しなくても俺が抱いて運んであげるから」
「体力には自信があるので大丈夫です!!」