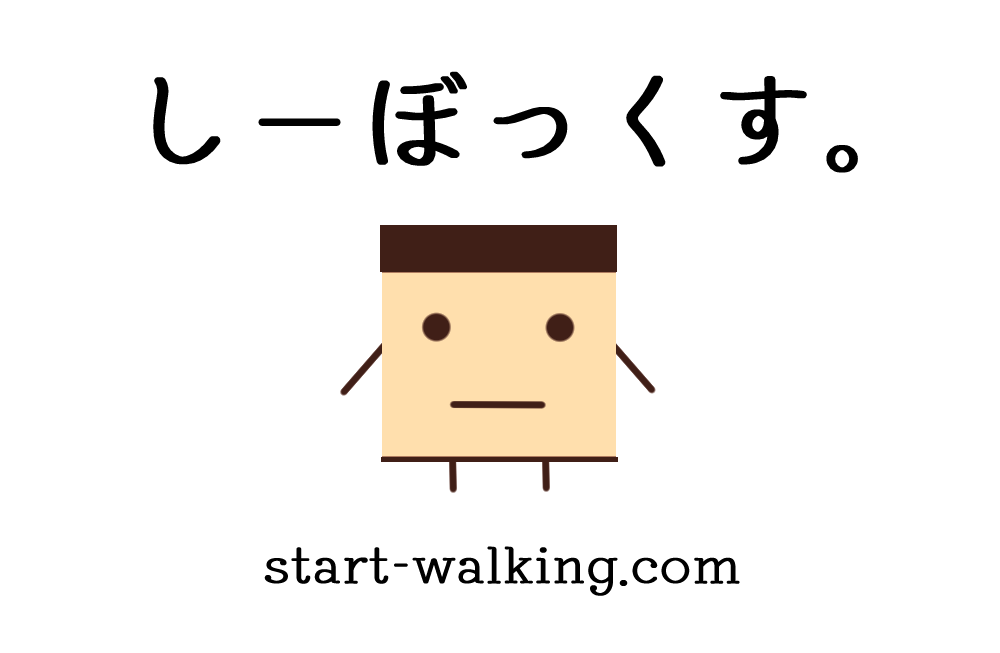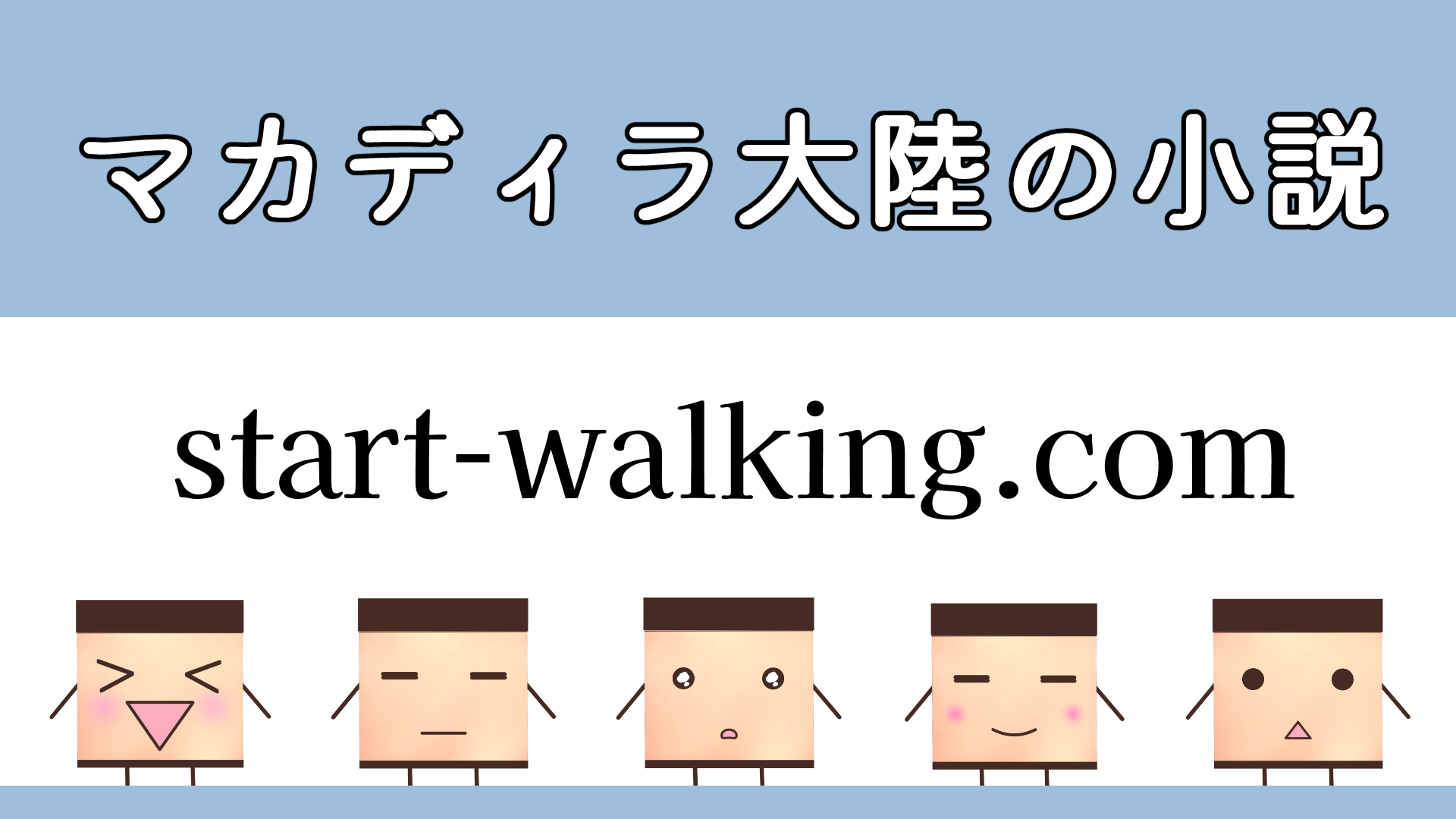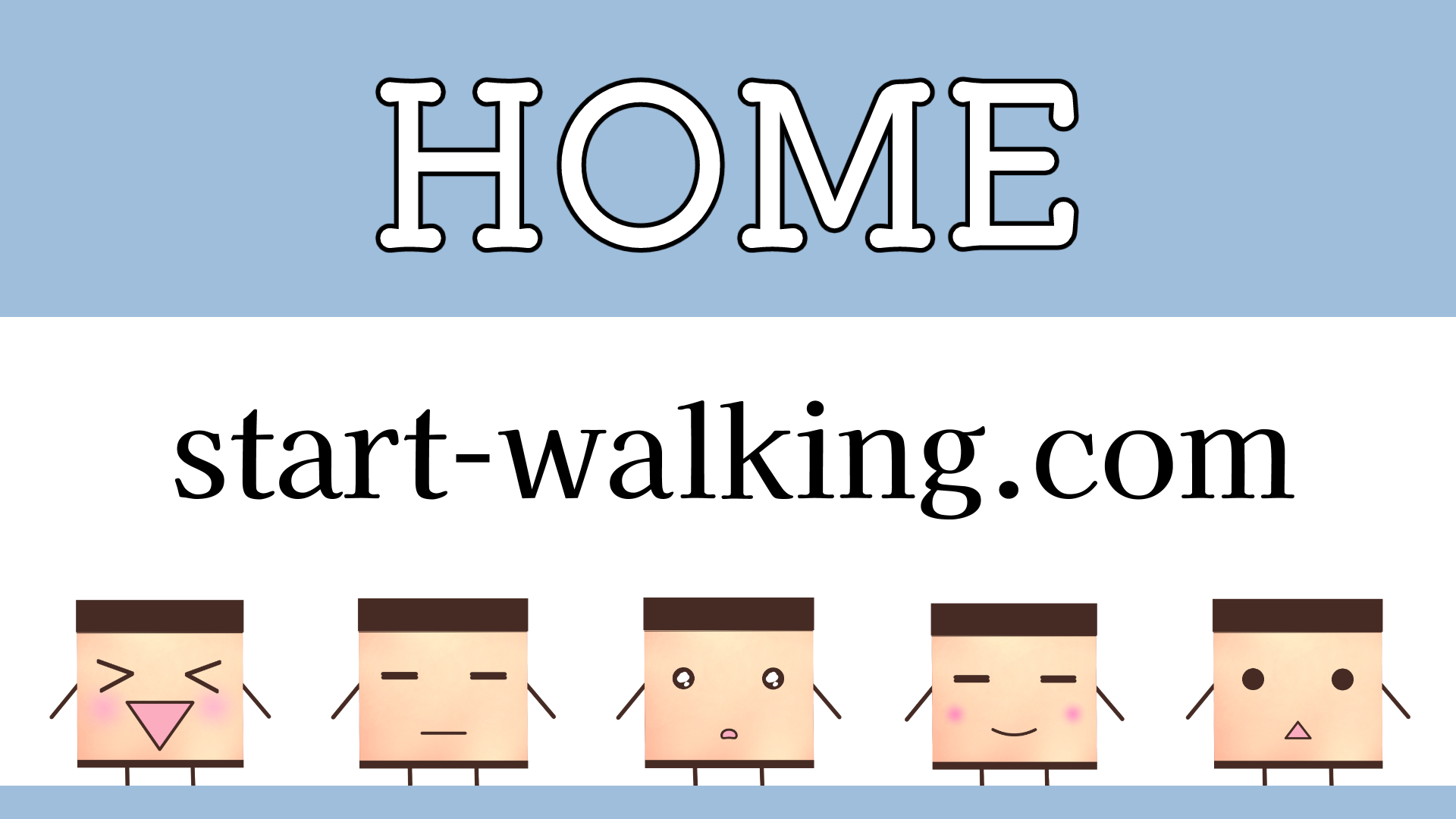1章-1
682年09月18日
青年はしゃがみこむと低く唸り声を上げた。
目の前にぶら下がっている鮮やかな赤い実。
見つめた先のその実に手を伸ばし、硬さを確かめる。
「これもまだ早い」
肩を落としながら溜息を吐いて、抱え込んでいるカゴに目を落とす。
そこには先程収穫したばかりの四つの赤い実。
「あと三つ……」
どうしようかと思案するこの青年の名をシキ・ナルダンという。
五人兄弟の長男で、今夜の夕飯に使う実を収穫に来ていた。
今朝、上の妹チェリエが畑の仕事から帰って来て、以前一度だけ作ったことのあるこの実を使った料理を食べたいと騒ぎ出した。
一人に一つの実を必要とするため、家族分となると、めったに作れるものではない。
「ちゃんと七つ食べ頃だったから」という言葉を信じ収穫を始めたが、二つ目を手にした時にシキは嫌な予感に顔を曇らせた。
緑から赤や黄などに色が変われば食べ頃という作物が多い中、実の硬さを確認しなければわからないのがこれだ。名をプリカという。
手に取った二つ目は、まだ食べ頃ではなかったのでシキは次の実に手を伸ばした。それは大丈夫だったので安心したが、残りの赤く色づいた実の数を見る限り不安は消えず・・・・・・。
結果、食べ頃の実は四つだけ。
「チェリエ……前にプリカの食べ頃は教えただろう?」
低い声でここにいない妹に言ってみるが、収穫を始める前に確かめなかった自分にも非はあると、責める心を抑える。
さて、どうしようか? いつまでもここにいては夕飯の時刻に間に合わない。
難しい顔をしたシキが立ち上がり周囲を見渡す。
この辺りは木々に囲まれた畑ばかりで人家はない。
人の姿がないことを確認すると、シキは再びしゃがみこんでまだ熟(う)れていないプリカへと両手を伸ばした。
優しく包み込む手。
その実を見つめる瞳。
しばらくして、そっと指で実に触れ、頷く。
「ありがとう」
シキは小さく呟き、熟れたその実をもぎ取った。
シキが食卓に皿を並べていると、学(がく)塔(とう)から帰って来た一つ年下の弟、15歳のカイが姿を見せた。
「ただいま」
「おかえり、カイ」
「おかえりなさい!」
フライパンで焼かれる肉の塊から目を離さずに声を上げたのは13歳の妹のチェリエである。
「シキ兄ちゃん! もういい? もう中まで焼けてるよね? いいよね?」
「焼けてるか判断する方法、前に教えただろ?」
「いじわる!」
シキはわざとらしく溜息を吐き、肩を落とした。
「俺がおまえの歳の頃には……」
「カイ兄ちゃん! シキ姉ちゃんがいじめる!」
「誰が姉ちゃんだ!」
蒸したプリカを皿に移しながらシキが吠える。
「おばちゃんたちが言ってたもん! この辺りで一番器量好しの人気者はシキ兄ちゃんだって。息子の嫁に欲しいって言ってた。やったね!」
「何がやったね、だ! 嬉しくないぞ!」
「兄さんは器用になんでもこなすからな」
「勉強はお前のほうが出来るだろ」
「どうかな? ……手伝うよ。お茶沸かそうか?」
「いいよカイ。疲れてるだろ? 学塔まで遠いからな。座ってろ」
「大丈夫」
そこにバタバタと騒がしい足音が聞こえてきた。
「あ! お帰りなさいカイ兄ちゃん!」
「おかえりなさい」
仲良く手をつないで姿を見せたのは、11歳の妹フェリエと末っ子の弟7歳のトズ。
「ただいま」
「ねえ! ちょっと! シキ兄ちゃん! 串で刺したけどわからない! 今回だけ! 今回だけだから! 次からは一人でやるから~!」
マカディラ大陸西部、ノンスーダン領7―6地区。
山間にあるこの地区は木材を加工し生計を立てている者が多い。
シキの両親も家具を作る組合に所属し、工場で朝から晩まで働く毎日だ。
その両親が帰宅し食卓に座れば、一家団欒の時間が始まる。
「うん、おいしい。蒸し加減も完璧。母さんシキにはもう料理の腕、負けちゃってるわね」
プリカの料理を口にして母コリエが言うと、シキは笑って応えた。
「何言ってんだよ」
「あ! 私がリクエストしたのよ! シキ兄ちゃんオリジナル料理。これ、前に食べた時すごくおいしかったから!」
チェリエが自慢げに言うと、フェリエが「うん、おいしい!」と言い、隣の席のトズも口いっぱいに頬張りながらコクコクと頷き賛同する。
シキは照れてしまった表情をサッと隠し、隣に座るチェリエへと言う。
「次はおまえ一人で作るんだぞ」
「え!? ちょっと待ってよ! シキ兄ちゃん!」
「今日手順は教えたし、レシピノートにも書いてあるから」
「え~」
「あらあら、相変わらずチェリエはシキに頼ってばかりなの?」
「そんなことないわよ、母さん! ちゃんと私だって頑張ってるんだから」
「俺は今日、おまえの教育係として心に誓ったことがある」
「え? 何をよ?」
「これからは、甘やかすことをやめる」
「なにそれ!? いつ甘やかしてくれたって言うのよ!」
「あまりの出来なさに兄ちゃん、ショックで教育方針を変えることに決めたんだ」
「ひどい!」
シキとチェリエ以外の、家族の笑い声が明るく響いた。
「フェリエが初(しよ)学(がく)塔(とう)を修了したら教育係はおまえなんだからな? 早く俺がいなくても大丈夫になってもらわなきゃ困る」
「わかってるわよぉ~」
料理・洗濯・掃除・裁縫に畑仕事など、家の仕事の大半は現在長男であるシキが担っている。
初学塔を修了後、チェリエはシキに家事の教育を受けている最中だ。
ふてくされた姉を見て、フェリエが「はい!」と大きく右手を上げた。
「わたしチェリエ姉ちゃんじゃなくて、シキ兄ちゃんに教えてもらいたいです!」
「ちょっと、フェリエ!?」
「だって、チェリエ姉ちゃんに教えてもらうなんてこわいもん。わたしの夢は完璧なお嫁さんになることなのに」
「ひ・ど・い……」
「兄さんは忙しいから駄目だぞ、フェリエ」
テーブルに懐いたチェリエを放っておいて声を上げたのはカイだ。
「チェリエに家のことを任せるようになったら兄さんは学塔へ行くんだ。本来年齢的にも学塔には俺よりも先に、兄さんが行くべきだったのに」
「それはちゃんと話し合って決めたことだろ? それにおまえが学塔で習ったことを家で俺に教えてくれてるから、俺が学塔に通う時は予習ばっちりで試験の時楽できるしな」
「兄さんに負担をかけ過ぎてるって話だよ」
「シキには甘えちゃって家のことすっかり任せちゃったからねぇ」
「そんなことないよ母さん。俺が言い出したことだし、ちゃんと家族みんなで協力してやってるだろ?」
「おまえは、本当にしっかりしてるな」
父親のジョウからもそんな言葉をもらい表情に困っていると、隣からふてくされた「いいお嫁さんになるわよぉー」という声が聞こえ、シキは声の主の足を蹴り上げた。
来客を告げる呼鈴の音が聞こえたのはシキとチェリエが皿洗いをし、食卓ではその二人を除いた皆が雑談を弾ませているところだった。
「こんな時間に誰かしら?」
チェリエが言うと「俺行くよ」とカイが立ち玄関へ向かう。
しばらくして戻ってきたカイを見たシキは眉を顰(ひそ)めた。
「父さん、母さん。区長が二人を呼んで来て欲しいって」
「え?」
「区長が来てるのか?」
慌てて玄関へ向かうジョウとコリエ。
チェリエが首を傾げた。
「区長が家に来るなんて、何かあったのかしら?」
シキは濡れた手をタオルで拭くと「見てくる」と言って玄関へ向かう。その後をカイが無言で続いた。
シキの家族が住むこの地区の区長であるデサネ・ヌーバは黒髭の恰幅のいい男だ。警備軍の制服を着た二人の男を後ろに従えている。デサネはシキの姿を一目見るとすぐに笑顔で話しかけてきた。
「やあ、君がシキ君だね。小さい頃会ったことがあるが、覚えてないだろうね。大きくなったものだ」
シキは頭を下げて訪ねる。
「何か、あったんですか?」
ジョウとコリエの顔は困惑気味で用件をまだ聞いていないようだった。
「いや、御両親に聞きたいことがあってね。こんな時間にすまないが、大事な話だから君達には一時間ばかり、留守番をお願いしたいんだ」
「留守番・・・・・・どこへ? うちで話すわけにはいかないんですか?」
「人に聞かせられない話でね。本当だったら私の家に招きたい所なんだが、ここからは少し遠い。仕方ないから駐在所の一室を借りることになっているんだ」
「駐在所・・・・・・」
駐在所なら家から歩いて五分もかからない所にある。
「シキ、とりあえず父さん達行ってくるから、留守番を頼む」
父親のジョウの言葉にシキは「わかった」と応えた。
見送った後の玄関先、振り返るとカイと目が合った。
硬い顔をしたままのカイにシキは小さく笑いかける。
「たった一時間の留守番だとさ」
そう言ってシキは自分よりも少しだけ背の高い弟の右肩に手を置いた。
「あ、シキ兄ちゃん。何だったの?」
戻ると皿洗いを終わらせたばかりのチェリエがさっそく聞いてくる。食卓の妹と弟も兄達を見ていた。
「何か聞きたいことがあるらしい。一時間くらいで戻ってくるからそれまでいい子に留守番しとけってさ」
「え~? 区長が来るなんてよっぽどよね。何なの?」
「さあな。・・・・・・よし! トズ、今日は初学塔で何を習ってきたんだ?」
シキが明るい声を上げ食卓の席に座る。
チェリエとカイも椅子を引いて腰を降ろした。
今年から初学塔へ通い出したトズは話を聞いてくれるらしい兄と姉達に嬉しそうにしゃべり出す。
「今日はね、紙芝居があった!」
「〝赤い目〟ですって」
すでにトズから聞いていたフェリエがそう言うと、チェリエが頬杖を突いて「ああ」と頷く。
「〝赤い目〟かぁ、懐かしいわね」
初学塔では読み・書き・計算の他に、この大陸で生きていくのに必要な知識、歴史などが教育される。〝赤い目〟はこのマカディラ大陸の過去の事実を元に創作されたといわれる物語の一つだ。
マカディラ大陸の最高権力者を血(けつ)族(ぞく)者(しや)という。
血族という一族から生まれる神の依り代だ。
その身を器とし、神を憑依させ、魔物の魂を消滅させることの出来る唯一の存在。
〝赤い目〟はそんな血族者の力を信じなかった怪力の大男ガルスが主人公だ。
山の中で育ったガルスは、二人きりで生活していた祖父が亡くなり山を下りた。
幼い頃から強くなることのみを考え、体を鍛えるばかりで勉強をせずにいたガルスは、体が大きく喧嘩も強いが、知らないことばかりだった。
この大陸で一番強いのは俺だと豪語するガルスを人々は嘲笑った。
「おまえは確かに強いが魔物を捕獲する力を持つ能力者には敵うまい」
「ましてやその魔物を消滅させる力を持つ血族者様に敵うはずもない」
だが、ガルスは魔物や能力者、血族者のことを見たことも聞いたこともなかったのでそれを信じなかった。
そんなガルスがある日、魔物と遭遇する。
北部の海に流れ着くという人を食い殺す魔物。ギョロリとした大きな赤い目。黒い体毛は長く、馬ほどの体の大きさで、牙をむく口からは涎がボタボタとこぼれ落ちている。
人々が恐怖に震え逃げ惑う中、ガルスは魔物を前にしても恐れることなく剣を手に取り立ち向かった。
そして・・・・・・。
ガルスは本当に強かった。見事に魔物を倒した。
ガルスは魔物の息の根を止めると勝利の雄叫びを上げ勝ち誇った。
しかし魔物の魂は屍と化した体から離れ地上を彷徨うといわれている。
魔物は殺さず生け捕りにして、血族者にその魔物の魂を消滅してもらわなくてはならない。そうしなければ魔物の魂は新たな肉体に取り憑き再び人を襲い始める。
それが、視える者にしかわからない真実といわれていた。
ガルスはその話を信じていなかったので魔物を殺してしまったのだ。
そんなガルスを人々はなんということをしでかしたのかと責め立てる。
ガルスは怒り、人々を嘲笑った。
「生き物など死ねば終わり。殺してしまえば終わりだ! 魔物の魂など俺の目には視えぬ! 俺は目に見えぬものなど信じない!」
しかし魔物の黒き魂は本当にその地を彷徨い始めていた。
突如目が赤く光り、歯をむき出しにして狂ったように暴れ出した馬がガルスを襲う。
ガルスは驚き、襲ってきた馬を殺してしまう。
そしてまた、黒き魂は新たな動物へと取り憑き、赤い目の魔物となって人々を襲い出した。
大きな獣や小さな獣。
何度殺しても現れる凶悪な赤い目の魔物。
ガルスは目に見えぬものは信じないと言った。
しかし魔物の魂は見えないが、その赤い目はガルスの目にも誰の目にも明らかだ。
おとなしかった動物が突然赤い目の魔物へと変わるのだ。
休む間もなく繰り返される魔物との戦いに、ガルスはとうとう疲れ果て怪我を負う。
そこに現れたのが魔物の話を聞きつけた三人の男。
戦闘能力者の男が風や水、炎を操り魔物を追い詰め。
音使いの男が光石で創られた笛の音色で魔物を眠らせ。
最後の一人、血族者が神の力で魔物の魂を消滅させた。
ガルスは目の前でそれを見て、これまでの自分の無知と思い上がりを恥じた。
しかし血族者にその強さを見込まれたガルスは、それ以後、戦闘能力者と音使いと共に、魔物の捕縛に力を注いだという。
「でも実際は、魔物の目が赤いなんて嘘って聞いたわよ。本当かしら?」
チェリエが首を傾げ言うとフェリエが驚いて声を上げる。
「え? 嘘なの?」
フェリエとトズが兄達を見る。
シキは首をすくめた。
「さあ? 見たことないからな」
「見たことがあったら大変だよ。学塔の書庫で読んだ。魔物にもいろんな種類がいるらしくて、赤い目のやつもいればそうじゃないのもいるってさ」
マカディラ大陸は、東部・西部・南部・北部・中央とで分けられている。
大陸を囲む海の浅瀬には光(こう)石(せき)と呼ばれる魔物を寄せ付けない不思議な光る石があり、その恩恵で人々は安心して暮らすことが出来るのだ。
だが、唯一魔物が海を渡り上陸する場所が北部にある。
そのため、北部は砦や高い壁に囲まれ、他の地とは隔離されている状態だ。
故にこの西部で魔物の姿を見ることはない。
もしあれば西部のみならず大陸中を脅かす大問題となるのだ。
「ねぇ、戦闘能力者カッコいいよね! 今も北部で魔物と戦ってるんでしょう?」
普段口数の少ない弟トズがシキの傍らに移動すると腕を摑んで興奮気味に訊いてくる。
シキはそんなトズを見て、ふと昔の記憶が蘇った。
幼い頃〝赤い目〟の紙芝居を見て自分もこんなふうに興奮していた。自分だけじゃなく、同じ年頃の男はみんな、自然を操り魔物を追い詰める戦闘能力者にあこがれたものだ。
そう懐かしく思い出しながら、シキはトズの頭をなでた。
「ああ、そうだ。〝赤い目〟の時代とは違い、今では魔物の捕獲は北部の警備軍に任されているからな。能力者の中でも、戦闘能力者は北(ほく)部(ぶ)五(ご)山(ざん)のトップの地位で魔物の捕縛を任されてるらしい」
「五山?」
トズが首を傾げる。
「北部の警備軍は五つ。白(はく)山(ざん)・赤(せき)山(ざん)・青(せい)山(ざん)・黄(こう)山(ざん)・緑(りよく)山(ざん)。合わせて五山って呼ぶんだ。土地も五つに分けられていて、それぞれその地を守ってるのさ」
「黒(こく)山(ざん)は?」
今度はフェリエが首を傾げた。
「それはここ西部の犯罪者が入れられる収容所でしょ」
チェリエが答える。
「黒山ができる前、犯罪者は誰もいない北の壁の中に放り込まれて、魔物の様子を見てくるように言われたらしいわよ~」
「え~、やだ。こわい~」
「ねえ! 僕、戦闘能力者になりたい! どうやったらなれるの?」
トズが瞳を輝かせて訊いてくる。
「ばっかね~、トズ。戦闘能力者になんてなれないわよ。能力者っていうのは、生まれつき普通じゃない力を持っている人のことをいうの。なろうと思ってなれるもんじゃないのよ」
チェリエの言葉にトズはがっかりした顔で肩を落とす。
「それに、もしトズが戦闘能力者の力を持ってたとしたら、私達とは会えなくなっちゃうんだからね」
「どうして?」
「能力者は家族と引き離されて光(こう)の塔(とう)へ連れて行かれるの」
「光の塔?」
「中央にある能力者の学塔のこと。能力者の力を正しいことに使うように警備軍に入れられて教育されるの。もし戦闘能力者が犯罪者になってごらんなさいよ。大変なことになるでしょう?」
「そうかぁ。じゃあ僕、戦闘能力者じゃなくていいや。みんなと一緒にいたいもん」
笑顔で言うトズの頭をもう一度撫でたシキがカイを見ると、気づいたカイの視線が逸らされる。
「・・・・・・」
そんな兄二人の様子に気づくことなくチェリエが妹と弟に言い聞かせる。
「いい? フェリエ、トズ。今の話は初学塔でこれから習うことだし、修了試験にも出るから覚えておきなさいよ」
「「はーい」」という下の二人の元気な声が上げられた。
玄関の物音に、勢いよく立ち上がったのはカイだった。
「・・・・・・あ、父さん達帰ってきたみたいね」
カイの様子に戸惑いながらチェリエが言う。
シキは座ったまま待つ。おそらく覚悟を決めなければならない。そんなことを思いながら。
カイは硬い表情で立ち上がったまま、動くことなく部屋の入り口を見ている。
「ねえ、どうしたの? 二人とも、変」
さっきまでと違う顔の兄二人にチェリエが首を傾げながら問うが、応えがないまま姿を見せた父親と母親を見て、口を閉ざした。胸の中を不安が押し寄せる。
フェリエとトズもわからないながらも神妙な顔で口を閉ざしている。
「おかえり、父さん、母さん」
「シキ・・・・・・」
唯一声をかけたシキ。
ジョウとコリエは真剣な顔でシキだけを見ていた。
「シキ、訊きたいことがあるの」
コリエが言うと、「うん」とシキは応えた。
「おまえ達、自分の部屋へ行ってなさい。父さんと母さんは、シキと大事な話がある」
ジョウがシキを除いた四人に言う。
「嫌だ。俺も話を聞くよ」
「カイ?」
真っ直ぐな目で父親を見るカイ。
「カイ? あなたまさか・・・・・・」
コリエが動揺した様子で口を手で覆った。
「チェリエ」
シキが名を呼ぶ。
「な、何?」
「フェリエとトズを連れて、部屋で待っていてくれ」
兄弟達は、シキとカイが同じ部屋を。チェリエとフェリエとトズが同じ部屋を自室として使っている。
「・・・・・・わかった」
チェリエは立ち上がり、言われたとおりに妹と弟を連れて自分達の部屋へと向かった。
「区長の話、何だった?」
「シキ。おまえ、父さん達に、隠してることがあるんじゃないか?」
「隠してること? ・・・・・・あるよ」
「シキ!」
「あるけど言わない。母さん、安心していいよ。カイにも言ってない。誰にも言ってないから」
「シキ・・・・・・」
「兄さん」
「俺からは言わない。だから、訊くよ。区長の話、何だったの?」
ジョウが大きく息を吐いた。俯いた顔を上げてシキを見る。
「おまえは、いったい何時から・・・・・・いや」
もう一度息を吐いて首を振る。
「座って話そう。母さん、カイ」
その言葉に二人は椅子に腰を降ろす。
ジョウも座り一息つくと、シキを真っ直ぐに見て口を開いた。
「密告があったそうだ」
「密告?」
「おまえが能力者ではないかと」
「・・・・・・そう」
「それで、調査員が来てここ数ヵ月間、おまえの動向を調べたそうだ」
「それは、気づかなかったな」
ここ数ヶ月、能力を使った数は、きっと五本の指で足りる。どれもそんなにたいした理由じゃない。そう思い返すとシキの顔に苦笑が浮かんだ。
「それで?」
「おまえを能力者として、光の塔へ連れて行くことが決定したそうだ」
その言葉にショックを受けた様子を見せたのはカイだけだ。
シキは無言でそれを受け止め目を閉じた。
「訊かれたよ。気づかなかったのかと。・・・・・・全く気づかなかった。親として情けないな」
コリエの口から小さなうめき声が漏れた。
母親の目から涙がこぼれ落ちるのを見て、心が沈んだ。
何度も、この日が来ることを想像してきた。何度も。何度も。
とうとう来てしまった。
想像じゃ無い。
・・・・・・今が、現実だ。
「シキ・・・・・・どうして?」
コリエの問いにシキは口を開く。
「どうして? 言わなかった理由? ・・・・・・そうだな、いろいろある。・・・・・・俺の能力は、どう考えても、何の役に立つんだろう? ってくらい、大したことないものなんだ。戦闘能力者みたいな力だったら、さすがに俺も言ったと思う。その力を利用しようとするやつが現れるかもしれないしね。けど、そうじゃなかったから、一生黙ったままでも問題ないかなって。・・・・・・それに、本当は何より、皆と離れるのが、イヤだったからだよ」
「言ってくれていたら、もっと、どうにか・・・・・・そう、こんなことにならずに、気づかれないように、出来たかもしれないのに」
「駄目だよ、母さん。能力者と知っていて隠すことは犯罪だ。そうと知っていて、言うわけないだろ?」
コリエが嗚咽混じりに問う。
「お金目当てに、私達があなたを売るかもなんて、そんなこと考えたりしなかった?」
「それで言わなかったなんてこと、ないよ。まあ、俺の能力にいくらの値段がつくかなんてわからないけど、お金に困るようだったら、すぐに光の塔へ行くつもりだったし」
「シキ・・・・・・おまえはいつ、自分の能力について知ったんだ?」
父親からの問いに、ぼんやりと遠い昔を思い出す。
「いつ、か。いつかな? 自分が能力者だってことを自覚したのは、初学塔で能力者について習った時だよ」
「兄さん、俺は」
「カイ、俺は一度だっておまえに俺が能力者だって言ったことはなかった。そうだろ?」
「・・・・・・うん」
「おまえがずっともしかしてって疑っていたとしても、言っていないんだから、おまえに罪はない。いいな?」
「・・・・・・」
カイは歯をくいしばり俯いた。
「父さん、母さん、それで? 俺はこれからどうなるの?」
「表に、調査員の方を待たせている」
「少しだけ、私達だけで話をさせて欲しいってお願いしたの」
「そっか。強制的に突然連れて行かれることだって想像してたんだ。ありがたいな」
「シキ」
コリエが立ち上がりシキに近づく。シキも立ち上がり向かい合うと、コリエはシキの体を強く抱きしめた。
「ごめん、母さん」
こうやって抱きしめられるのは、いつ以来だろう?
母さんの背を追い越す前のことだったかな?
久しぶりに感じる母親のぬくもりを、シキは大切に記憶に刻んだ。
シキは俯いて震えている母親の肩に手を置き、父親に問う。
「父さん、表に調査員の人を待たせてるんだろう?」
「ああ」
「これからどうするのか、聞かなきゃね」
シキは母親からそっと離れ、足を踏み出し玄関へと向かった。
1章-2
玄関の扉を開けると、そこには制服姿の男が三人立っていた。
その内の二人は区長が来た時にいた二人だと気づいて、調査員の人間だったのかと頭の片隅で驚く。
もう一人は初めて見る顔だった。
シキは年配のこの人が責任者だろうと見当をつける。
眼鏡をかけたその奥の目は嘘を許さない力強さを感じ、顔には深いシワが刻み込まれている。杖を持っているが、背筋が伸びたその立ち姿から足腰が弱いようには見えない。
「やあ」
男は言ってシキの方へと歩み寄る。
「私は、中央の光の塔から来たダリス・フェーダーだ。シキ・ナルダン君だね?」
「はい」
「長い付き合いになるだろう。宜しく頼む」
手を差し出され、シキはその手を取り握手をする。
ダリスは一つ頷く。
「君のこれからのことを話さなければならない。まずは、君の家族と一緒に話をしようか」
「・・・・・・わかりました」
シキが後ろを振り返ると、ジョウとコリエ、カイが不安そうにこちらを見ていた。
客間がないので、先程から使っている食卓の席へと招き入れた。
二人の男は護衛ということで椅子は必要ないとダリスの後方左右に立っている。
その威圧感がシキには居心地悪い。
ダリスは持っていた鞄からペンとインクとファイルをテーブルの上に取り出した。
「御両親から話があったと思うが、調査員が動きその結果君は能力者認定された。君の言葉でまず聞きたい。君は、能力者だね?」
「・・・・・・はい」
開かれたファイルにペンが走る。
「自分でどういった能力だと認識している?」
「植物の生長を促す能力だと、認識してます」
「たとえばどういった?」
「蕾の花を咲かせたり、食べるには早い果物や野菜などを食べ頃にしたり。小さなことです。・・・・・・正直、この能力があったからといって何の役に立つのかと、そう思ってきました」
「だから、能力者であることを黙ったままでいた?」
「・・・・・・すみません」
責める口調ではなかったが、シキは謝った。
「君は今、16歳だね。どんな能力であれ、18歳以上で能力者であることを自覚しながらそれを隠していれば罪となる。本人が黒山に連れて行かれることはまずないが、それなりの罰を受けることになる」
「はい」
「うん。初学塔で習うことだがね、詳しい罰は人それぞれ、能力によって違ったりもするが、一番知られているのは支給額が減らされることだろう」
「はい」
「それでも、黙ったままでいるつもりだったのかね?」
「それは・・・・・・正直、迷っていたし、どうするか、ずっと考えていました。ずるいかもしれませんが、18歳になるまで、猶予があると自分の中で思っていました」
「ふむ」
ダリスはペンを人差し指で軽く二回叩いた。
「君と同じようなことを考えていた子を知っているよ。彼も自分の能力のことを隠し18歳までは家族と共に過ごすつもりだったと言っていた。家族を大事にしていて、自分の置かれている状況を冷静に分析し、行動する能力に長けていた。彼はその時今の君よりも若かったが、うん。・・・・・思考が君と似ているか? いずれ紹介しよう・・・・・・あぁ、いや。私が紹介するまでもないか」
「?」
「・・・・・・話が逸れたな」
ダリスが緩く笑いそう言うと、今度はジョウとコリエに顔を向ける。
「御両親には先程も確認したが、改めて訊きます。あなた方は、息子さんであるシキ君の能力に気づいていなかった。間違いありませんね?」
「・・・・・・はい」
ジョウがそう答え、コリエは言葉もなく頷いた。ダリスも頷き、今度はカイへと顔を向ける。
「弟の、カイ・ナルダン君だね。君もお兄さんの能力に気づいていなかった?」
カイの表情が強張る。
「俺は・・・・・・」
「ダリスさん。能力者を隠すことが罪になることは知っています。俺は家族を愛しています。大切な家族の誰にもそんな罪を負わせる気はない。知られていたら、俺は今ここにはいません」
ダリスはシキを見て、そしてカイに視線を戻した。
「ふむ」
走るペンが止まり、ダリスがフッと笑った。
「形式的なものだよ。君の場合はね」
「え?」
「隠匿(いんとく)の罪は能力者の力を悪用しようとする輩から守るためのものだ。残念なことに、親や兄弟であっても、能力者を私利私欲に使おうとする者もいる。その判断は私達調査員に任されていて・・・・・・まぁ、自慢だが、私に嘘は通じないよ」
「・・・・・・」
ニッと笑うダリス。シキは身を固くして視線を落とした。
「ダリス殿」
「ん?」
護衛の一人が声を掛け、皆の視線がそちらへ向く。
「先程からこちらに」
護衛の男がそう言って部屋の扉を開けると、そこに硬い顔をしたチェリエが立っていた。
「チェリエ・・・・・・」
「妹さんだね」
「・・・・・・はい」
胸の前で指を組ませたその手はかすかに震え、ゆっくりと部屋の中へと足を踏み入れた。その視線はそらすことなくシキを真っ直ぐ見つめている。
「シキ、兄ちゃん」
震えた声。
「チェリエ・・・・・・駄目だろ? 盗み聞きなんて。フェリエとトズは?」
シキがいつもと変わらない調子で言うと、チェリエの身体の震えが止まった。
「部屋で本を読んでる・・・・・・寝かしつけようと思ったけど、まだ寝ないって言うから」
そう答えて、急激に感情が込み上げたのか涙目になってシキを睨んだ。
「シキ兄ちゃん!」
シキは立ち上がってチェリエへと歩み寄り、彼女の頭に手を置くと「ごめんな」と言った。
「初学塔に通っている二人のお子さんは構いませんが、ご存じの通り初学塔を修了した者にはこの大陸で生きる上で責任というものが生じます。先程の隠匿の罪にしても初学塔を修了している者のみに適応される罪状ですから。彼女にもこの場の同席をお願いします」
ダリスの言葉にチェリエは小さく頷いた。
シキの隣りの席でチェリエが今にも泣きそうな顔で座っている。
「チェリエ・ナルダンさん。君は兄であるシキ君が能力者であると気づいていましたか?」
ダリスの質問に横に首を振る。
「いいえ。気づきもしなかったし、疑ったこともなかったです。・・・・・・知らないそんなの! ずっと一緒にいたのに! それより・・・・・・私達、シキ兄ちゃんと会えなくなるんですか? いつですか? いつ連れて行っちゃうの? 今日ですか? 明日ですか? 明後日ですか?」
「チェリエ」
窘(たしな)めるシキに構わず言い募る。
「イヤ! そんなのひどい!」
「何も分かっていない子供のようなことを言うな」
「分かってるけど! 分かりたくないの!」
「馬鹿。すみません」
シキがチェリエに手を伸ばし頭を下げさせる。
「いや、構わないよ」
ダリスが微笑を浮かべ頷く。
「ここを出発する日はまだ決まっていないが、早くて明日」
それを聞いてチェリエは前のめりになって叫んだ。
「イヤです! 光の塔に行ったら私のお兄ちゃんじゃなくなるんでしょう? 本当に会えなくなるんですか? こちらから会いに行ってもですか? 何があってもですか?」
「そうだね。知っての通り能力者は形式的な意味で家族を失うことになる。君のお兄さんはシキ・ナルダンからただのシキと呼ばれるようになる。彼の努力次第で警備軍の一員として認められれば元の家名を取り戻すことも出来るが、そうなったとしても、今と同じ戸籍に戻るわけではない。会うことも難しい。能力者との接触は簡単ではないからね」
初学塔で習うことなので知識として知ってはいても、他人事ではない現実に胸が重い。
表情を無くしたチェリエを見て、シキは申し訳ないという気持ちが急激に膨らんだ。カイも父親も母親も顔色を失っている。
シキは背筋を正し、口を開いた。
「ダリスさん、お願いがあります」
「こちらの部屋には二人分の寝具が用意されています。どうぞお使い下さい」
「・・・・・・ありがとうございます」
会えばいつも気軽に挨拶を交わしていた駐在所の隊員に敬語で対応されたシキは戸惑いと居心地の悪さを同時に感じていた。
警備軍で能力者の地位が高いということを知ってはいたが、自分がそうなのだということを考えたことがなかった。だが、それは気が早いというものだろう。光の塔で警備軍の一員として認められなければ、自分にその価値はないのだから。
今シキがいるのは近くの駐在所。先程シキの両親が呼ばれた場所でもある。
あれからシキはダリスに「急なことなので家族の気持ちを落ち着かせる時間が欲しい」と頼み出た。ダリスは頷き「少なくとも明日すぐに光の塔へ出発することはしない」と約束した上で家族とは別にシキ個人に話すべき事があると場所を移動することになった。彼等は光の塔までシキを護衛しなければならないこともあり、シキは家に帰らずその場所で泊まることになったのだが。
「じゃあカイ、おまえはこの部屋で待っていてくれ。先に寝てていいから」
移動先にカイもついていくと言い出した時、シキは諦めさせようとしたが、ダリスが不安を抱える家族の思いをくみ取り、嫌な顔せずそれを了承した。
「眠れるわけないだろ。待ってる」
「・・・・・・わかった」
光の塔から来た警備軍の調査員は全部で五人。
先程シキの家に来た三名だけが部屋へと入り、残りの二人は交代制だから先に休んでおくようダリスに命じられた。
自分が警備軍の一員になるのだと意識し始めたシキは、改めて彼等に興味が湧く。
休むよう言われた二人は父さんや母さんと同じ位の年、またはもう少し上? そうシキは推測する。後のダリスを除いた二人は確実に彼等よりも若い。一人は長身で体格の良い二十代。もう一人は更に若い。自分とそんなに年が離れていないのでは? 訊いてみたいと思ったが、共通して彼等は仕事中だからか、ダリス以外無表情でいるので正直話しかけづらかった。
部屋のテーブルの席に着く。
ダリスの正面にシキ、ダリスの隣りに長身の男、シキの隣りに黒髪の若い男が座った。
「改めて紹介しておこうか。私の名はダリス・フェーダー。中央警備軍所属、光の塔で調査員をしている。先に休ませた二人は主に私の下で働いている。隣の彼は」
ダリスに促され口を開く長身の男。
「私は北部警備軍白山所属、ミグラ・ローディ。能力者付きの側近資格を持っている為、今回同行しました」
少し間を空けてシキの隣りの男が話し出す。
「俺はカルフェ・ノード。北部警備軍白山所属。その能力者付きの側近資格ってやつの試験中や」
「試験中?」
そう言ったシキが顔を向けるとそのカルフェと目が合う。
「ッ!」
その瞬間心臓が跳ね、シキはそんな自分自身に驚いた。
「まあ、俺のことより今は自分のことで訊きたいことがあるやろ?」
その喋りに北部の人間は訛りがあると聞いたが本当だったのかと頭の片隅で思う。
何故か高揚し始めた感情をシキは押さえつけようと改めて姿勢を正す。
「自分の、こと・・・・・・」
「まずは君の後見人について話そうか。何か質問があれば、いつでも訊いてくれ」
ダリスが書類をテーブルに置き、ペンを取った。
能力者と認定された者はそれまでの戸籍から外され親兄弟を失うことになる。
それ以降、警備軍から報奨金が能力者の後見人に支払われるが、その金額は能力者個人の価値やその働きにより変動する。
後見人は一般的に能力者の家族がなることが多い。しかし能力者本人が指名権を持っているので、家族ではない人物が後見人となる場合もある。
「では、君が指名する後見人は御両親と兄弟、六名でいいんだね?」
「はい」
書類に家族の名前が記入されていく。
最高十名まで指名できる後見人。支払われる報奨金はその後見人の数に分けられ、それぞれに交付される。
「後見人に報奨金が支払われるのは光の塔で能力の審査結果が出た後に一回。警備軍の資格を得た後に一回。正式に警備軍に入隊後に一回。計三回になる」
ペンを動かしながら説明するダリス。
「はい」
「能力者は他の隊員よりも地位が高く給与金額も高い。その特別扱いに不満を持つ者達もいるが、気にせず堂々としていればいい」
「・・・・・・はい」
「そういうのは大抵仕事の出来ない能無しが多い」
「え?」
「カルフェ」
ミグラが注意するように声を上げたが、名を呼ばれた本人は気にせず喋り出した。
「それより、光の塔へ行ったら頑張れよ? 能力者として警備軍の隊員になる資格無しと判断されたら、おまえの存在自体抹消されるんやからな」
「抹消?」
不穏な言葉にシキが声を上げるとダリスが口を開いた。
「血族領へ送られ、二度と出てくることはないと云われている。実際、私も血族領に送られた者を数名知っているが、戻ってきた者を見たことはない。血族領内のことを知る者は軍の上層部にも、いるかいないか・・・・・・」
「え? じゃあ北部で捕縛した魔物は? 血族領の血族者様の所へ届けなければならないのでは?」
ダリスの話にシキが疑問を投げる。
「血族領の二重の門の一の門を抜けた処で引き渡されます。なので我々五山の人間も血族領内に入ることはありません。その時に血族領の制服を着た者が数名出て来ますが、私語は無く、事務的な手続きのみです。抹消という響きは悪いですが、血族領に送られた者はその者達のように一生そこでのみ働き生きる、血族領の住人となる。そういうことなのでしょう」
引き渡しの任務に就いたことのあるミグラが答える。
普段聞くことの出来ない話にシキは好奇心が満たされるのを感じ、心が踊った。
シキがカイの待つ部屋に戻ったのは深夜十二時を過ぎた頃だった。
部屋に入るとカイがベッドに腰をかけ、両手の指を組んで床をジッと見ているのが目に入った。
「悪い、カイ。遅くなった」
カイは沈んだ表情のままシキを見た。
シキはカイの正面で話せるようにもう一つのベッドに腰掛けた。
「カイ?」
「兄さんは・・・・・・どうしてあの力を使ったの?」
責めるような口調に、シキは真顔になった。
「使わなければ、一生気づかれないままでいられたのに、どうして使ったの?」
「・・・・・・ごめん」
「兄さん、本当はこうなることを望んでたんじゃないの?」
「え?」
「18歳までは、って言ってたけど、本当は能力者として、早く光の塔へ行きたかったんじゃないの? だからバレるようなことを・・・・・・」
「違う! わざとバレるようなことはしてない! ・・・・・・俺が、甘かっただけだ」
「俺、気づいてたよ。兄さんがいつ家を出てもいいように準備してたこと。俺を学塔へ先に行かせたのだって、兄さんは最初から商学の資格を取る必要なんてなかったし、取るつもりなんてなかった。だって兄さんは光の塔で」
「カイ!」
強く名を呼ばれ、カイは口を閉じ奥歯を噛み締めた。
「ごめん。言いたいことや訊きたいこと、たくさんあったけど、俺、今はダメだ。もう、寝るよ。明日はまだ、行かないんだろ?」
「・・・・・・あぁ」
壁に掛けられた照明具に油が足され蓋がされる。
「二時に交代か。睡眠時間は四時間弱やな」
廊下に置かれた長椅子に腰を降ろすカルフェ。
ミグラはもう一つの照明具へと移動し、蓋を開けて油を足し始めた。
「寝てもいいですよ。何かあれば起こします」
「俺、試験中や。資格取らせんつもりか?」
「まさか、そんなことで落としたりしません」
そう言って小さく笑い、蓋を閉めると、手に持っている油差しを所定の棚に置いた。
「それにおそらく何も起こらないでしょう。ダリス殿がそう言ってましたから」
この廊下は四つの部屋と繋がっている。
現在、シキとカイが一室。ダリスが一室。光の塔から来た後の二人が一室。それぞれが扉の向こう側にいる。
「あの人の能力は曖昧やけど外れないていうからな。・・・・・・安心や」
ミグラがカルフェへと視線を移す。
「あいつを奪おうって輩がいないっちゅうことやからな」
口角を上げて笑うそれを見て、口を開いた。
「今のその顔、うちの大将そっくりですよ」
「!」
愕然としたカルフェがミグラを睨む。
「笑えん冗談」
「今回の同行も無理矢理でしたし、似てくるものだな、と感心していました」
「チッ・・・・・・」
舌打ちをして片手で顔を覆うカルフェ。
「・・・・・・まぁ、ええわ」
気を取り直して顔を上げたカルフェが、もう一度笑う。
「無理言って来た甲斐あった。あいつは・・・・・・俺がもらう」
1章-3
窓から明るい光が差し込み始めた。
ベッドに横になりながらも、結局眠れずにいたチェリエが上体を起こす。
「朝、だわ・・・・・・」
そう呟きフェリエとトズの眠っている姿をぼんやり眺める。
この子達はまだ知らない・・・・・・。
チェリエは奥歯を噛み締めて俯いた。
「それじゃあ、お願いね」
「あぁ。・・・・・・コリエ、君は少しでもいいから休んだ方がいい。シキが帰ってきたら心配する」
憔悴(しようすい)した顔のコリエが無理に笑顔を作る。
「冷たい水で顔を洗えば大丈夫よ」
ジョウは小さく笑うと、元気づけるようにコリエの頭を軽く二回叩き、玄関から出て行った。
見送ったコリエの背後から声がかけられる。
「母さん、おはよう」
「チェリエ」
「父さんどこ行ったの?」
「仕事休むから、それを伝えに」
「そっか・・・・・・理由はどうするの?」
昨夜ダリスからシキが能力者であることを周囲に漏らさないようにと言われていた。
「シキが中央の学塔へ行くことになって、お世話になる方が来ているということで、休ませてもらうことにしたわ」
「学塔って何の?」
部屋へと移動しながら二人は話す。
「あの子、料理が上手でしょう? だから、調理師の資格を取るためにって」
「そっか。調理師になるための資格が取れる学塔、この辺りじゃ無いものね」
「えぇ」
食卓に座る二人。
「カイ、あの子知ってたのね」
「うん。昨日父さんと母さんが帰ってきた時、様子がおかしかったもの。絶対知ってたわよ。・・・・・・ずるいんだから、二人だけで隠し事して。今だってカイ兄ちゃんだけ!」
ふてくされた顔でチェリエはテーブルを拳で叩いた。
「あの二人は初学塔を出るまで、ずっと一緒にいたものね。同じ年頃の子達とそんなに遊んだりせずにずっと一緒にあなたたちの面倒も見てくれたりして。シキは本当に小さな頃からしっかりした子で、母さん助けられてばかりだった・・・・・・」
涙が込み上げてきてハンカチを手に取るコリエ。目が赤いのは昨夜からずっとこんな風に泣いていたからだろうと、チェリエは元凶のシキを心の中で罵(ののし)った。
呼鈴が鳴りチェリエが顔を上げる。
「あ」
時計を見ると、いつもカイが学塔へ行く時間を過ぎていた。
「きっとバイルがカイ兄ちゃん呼びに来たんだわ。私行ってくる」
チェリエは立ち上がって玄関へ向かった。
カイの通う学塔は歩いて一時間半程かかる場所にある。
同じ学塔へ通うこの辺りに住む年頃の子達は、集まって一緒に行き来している。
「よお、チェリエ。おはよ」
「おはよう」
玄関を開けるとシキと同じ歳の幼馴染み、バイルが立っていた。
その後方に男の子二人、女の子三人の姿。カイ以外の全員が揃っている。
チェリエが彼等に手を振ると、笑顔や手を上げたりなどして返してくる。
「カイどうした? あいつが集合場所に遅れるなんて、今までなかったからな。具合でも悪いんじゃないかって、皆で話してたんだ」
「あ、うん。違うの。具合は悪くないんだけど、実は今大事なお客様が来ていて、しばらくの間、カイ兄ちゃん学塔休むから」
「休む? 何で? しばらくっていつまでだよ?」
「わかんない。けど二、三日は休むと思う。朝集合場所に来なかったら先に行っていいよ」
「ふーん? 今カイは?」
「シキ兄ちゃんとお客さんとでちょっと出かけてる」
「いないのか」
「・・・・・・うん」
学塔を休むような大事な客って誰なんだ? とバイルは疑問を持ったが口には出さず、ただ怪訝そうにチェリエの顔を見る。
「わかった。じゃあ。・・・・・・あ、そうだ! チェリエおまえ、そろそろ将来のこと決めたか?」
「え? 何よ急に」
「シキにも言ってんだけどよ、おまえらも一緒に学塔へ通わねぇかと思って」
「えぇ?」
「18までだったら補助金も出るし、何かしらの資格取るなら早いほうがいいだろ?」
「わかってるわよ~、そんなこと! けど、うちにはうちの事情があるの!」
「ちぇっ、おまえらも一緒だと楽しいのにな」
「それはどうもありがとう!」
そんな気のない返事をしながらチェリエはそろそろ行きなさいとばかりにバイルの背を押し出した。
「おい! 押すな! わかったよ。あぁ、ほら! おまえと同じ歳のサヨリだって通ってんだから考えとけよ!」
チェリエはそこに立つ同じ歳の女の子の一人、サヨリを見た。
「!」
目が合った瞬間逸らされる視線。
「?」
「じゃあな!」
「あ、うん。行ってらっしゃい」
「ただいま」
シキとカイが家へと帰って来た。
玄関で一番に出迎えたチェリエ。
「おかえり! シキ兄ちゃん、カイ兄ちゃん。・・・・・・あ、と。カイ兄ちゃん、バイル達が迎えに来たから学塔二、三日休むって伝えておいた」
「あぁ、そうか。・・・・・ありがとう」
「うん」
チェリエの後ろからコリエが姿を見せる。
「おかえりなさい、シキ、カイ」
コリエは息子達の後ろへ会釈して声をかける。
「おはようございます。今日はお二人ですか?」
そこにダリスの姿はなく、ミグラとカルフェの二人がいた。
彼等は昨日と違い、制服を着ていない。
「はい。ダリス殿より今日は御家族の邪魔にならないようシキ殿の護衛を仰せつかりました。私はミグラ、こちらはカルフェです。気になるでしょうが、我々のことはいない者として扱って下さって結構ですので」
そうミグラが言うと、コリエは「そんな、とんでもない」と困りながら皆を家の中へと促した。
チェリエが自室の扉を開く。
「フェリエ、トズ、部屋の掃除が終わったら作業部屋の片付けお願い」
「え、どうして? 初学塔へ行く時間に遅れちゃう」
箒(ほうき)で机の下を掃いていたフェリエが顔を上げて言う。雑巾で棚を拭いていたトズは手を止め黙ってチェリエを見ている。
「今日初学塔はお休みして」
「・・・・・・どうして?」
「後でシキ兄ちゃんから話があるから。お客様が来てるの。だから朝食は私達だけで作業場で食べるようにって。久しぶりに母さんの手作りパンよ。あとスープだけだから、テーブルの上、片付けて待ってて。私が運ぶ」
「・・・・・・わかったわ」
家の一番奥にある作業場には扉も仕切りも無く、廊下から階段三段分の高い造りになっていて、この場所だけ靴を脱いで使用している。他の部屋と違い低いテーブルが置かれてあり、床に直接座るようになっている。
木彫り用の木材がたくさん入っている大きな袋は部屋の隅に置かれ、彫刻刀などの道具は棚の置き場に綺麗に片付けられている。
テーブルだけで無く、床に散らばっていた細かい木くずなどを綺麗にしたフェリエは、やることがなくなると自分の身体を抱えるように座り込んだ。
「ねぇ、トズ」
浮かない顔の姉の傍らにトズが座る。
「わたし、シキ兄ちゃんの話、聞きたくない」
トズは不安を感じている姉に寄り添うように身体をくっつけると「うん」と頷いた。
自分達が食べるだけを大鍋から小鍋に移したスープ。それに溶き卵を流し混ぜながらチェリエは後ろから聞こえてくる会話に耳を傾けていた。
先程から主に話をしているのは、ミグラという名の警備軍の一人とジョウとコリエだ。
「では、シキ殿は調理師の資格を取るために中央の学塔へ行くということで話を合わせます。能力者であることを知られ、周囲が騒がしくなった場合、すぐにここを出発しなければなりませんので、言動にはお気を付け下さい」
能力者ということを知られてはいけないというのはどれだけ大事なことなんだろうかとチェリエはぼんやり考える。シキが能力者であることが知られたら? 昨夜の〝赤い目〟の話程記憶にないが、チェリエでも知っている能力者の物語がいくつかある。能力者が悪者にさらわれその仲間になる話や、能力者の親がその子供の能力を隠して金儲けに使う話。その中でもチェリエが一番不快な話が能力者の子供が欲しいがために幾人もの女に自分の子供を産ませる男の話だ。内容も不快だが、その話が原因で子供の多い家庭の子はからかわれることが多いのだ。あそこの家はあんなにたくさん子供を産んで、能力者の子供がそんなに欲しかったのかね、と。言う人間は軽口のつもりかもしれないが、聞き流すことが出来ずにチェリエは喧嘩を売るような口調で言い返したことが過去にあった。
小鍋を火から外し三人分の食器とスプーンをトレーに載せる。ミルクとパンも運ばなければならないので一度に運ぶのは無理。三回に分けて運ぼうと思ったところでシキの声が聞こえチェリエの手が止まる。
「ミグラさん、下の妹と弟に話をしてきていいですか?」
「ああ、勿論。・・・・・・カルフェ」
名を呼ばれたカルフェが立ち上がる。そしてシキに言う。
「邪魔はしない。だが、悪いな。おまえから目を離すわけにはいかへんねん」
「はい」
わかっていますと小さな笑顔を返したシキも立ち上がる。
「チェリエ、運ぶの手伝う。・・・・・・カイもいいか?」
「・・・・・・うん」
作業場でチェリエを待っていたフェリエとトズは、姉と兄達の姿と共に現れた見知らぬ青年に気づくと不安気に瞳を揺らした。
シキは運んできた朝食をテーブル置き、廊下に立つカルフェへと声をかける。
「カルフェさん、改めて紹介しておきます。弟のカイと妹のチェリエ、そして下の妹のフェリエと、下の弟トズです」
シキの兄弟達が会釈をするのを見てカルフェは姿勢を正して一礼する。
「北部警備軍白山所属、カルフェ・ノードだ。現在君達の兄、シキ殿の警護を任されている。宜しく」
改まった口調のカルフェに少々戸惑いつつ、シキが口を開く。
「あの、カルフェさん」
「ん? 何や」
砕けた態度に戻ったカルフェに何となく気が抜けたシキが続ける。
「ずっと気になっていて訊けなかったので、訊いていいですか?」
「?」
カルフェが首を傾げる。
「歳、幾つですか? 俺とあまり変わらないような気がしていたので」
「あぁ、一応俺の方が上やで? 665年3月生まれやからな。おまえは666年1月やろ?」
「はい」
カルフェが声を上げずに笑う。
「そんなことより、話すべき事があるやろ? せっかくのスープが冷めるで?」
「あ、はい。すみません。・・・・・ごめんな、お腹すいただろ?」
シキがフェリエとトズに声をかけると二人は大丈夫と顔を振る。
「シキ兄ちゃんとカイ兄ちゃんは?」
三人分しか無い食器の数を見てフェリエが訊く。
「あぁ、俺達は食べてきたから」
「今日は久しぶりに母さんがパン焼いてくれたのよ。いっぱいあるからパンだけでも一緒に食べよ?・・・・・・あの、よければカルフェさんもいかがですか?」
チェリエがカルフェにそう声をかける。カルフェは少し驚いた顔をして、その後すぐに口元を笑んで見せた。
「ありがとう。けど、気持ちだけもらっとくわ。残念ながら護衛中は決められたもんしか口に入れちゃあかんっていう決まりがあるから」
「へぇ、そうなんですね」
「せやから気を遣わんでええで? 邪魔したくないしな。俺のことはおらんもんとして扱ってええから」
そう言ってカルフェは廊下の壁に背を預け、腕を組んで目を閉じた。
朝食が並ぶテーブルを五人兄弟が囲う。
「フェリエ、トズ。初学塔休ませてごめんな。話は後でするから、まずは食べよう」
どこか怯えた様子のフェリエとトズ。昨夜から暗い顔をしたままのカイ。いつもと変わらないように見せているチェリエ。
どことなく暗い空気の中、シキは皆の顔を見回して微笑む。そして手を伸ばしてパンを二つ取ると、カイへと一つ手渡した。
「じゃあ、いただきます」
シキがパンにかぶりつく。それを見た弟妹達も食べ始めた。
「うん、母さんのパンはやっぱり味も形もいいし、ふんわりとして柔らかいな」
「ちょっとシキ兄ちゃん、それは私の焼くパンが硬くて、味も形も悪いって言いたいの?」
こんな時、場を活気づかせるチェリエの存在は本当にありがたいと、シキはフッと笑った。
「俺の焼くパンと比べてってことだよ」
「ふうん。けど、シキ兄ちゃん、私のパン褒めてくれたことないじゃない」
拗ねて口を尖らせる妹に苦笑するシキ。
「そりゃあな、おまえ本当は手先器用なのに、興味がないことにはいいかげん、というか、雑になるから」
「え?」
「チェリエ姉ちゃんって、器用なの?」
フェリエが首を傾げて訊いてくる。それは仕方ない。チェリエの料理や裁縫などの残念具合を日々数多く見てきた妹である。
「ああ」
シキは立ち上がって棚へと移動し、そこの引き出しから手の平サイズの花の木彫りを一つ手に取った。
「ちょっ、シキ兄ちゃん?」
チェリエが腰を浮かせて声を上げる。シキは席に戻るとテーブルの上にそれを置いた。
「チェリエが彫ったものだ」
「わ、すごい!」
細かく彫り上げられた花形のそれは、確かに不器用な人間が仕上げられるものではない。
この作業場にある袋に詰められた木材は、両親の働き先の家具に使われる木彫り飾りとなるものだ。手の平サイズの木材に花形の図案を写し彫刻刀で彫り上げる。仕上がった出来の良い物は買い取ってもらえるので、兄弟達のちょっとした小遣い稼ぎとなっていた。
「飽きっぽいお前が、難しい図案を選んでは、細かい作業を真剣な顔で続けてるんだからな。木彫りが好きなんだろう?」
「う、うん」
チェリエが頷く。
「前にここで二人で一緒にやってた時、冗談交じりに仮面彫ってみたいって言っていたよな?」
「もう、シキ兄ちゃん。・・・・・・うん。前に一度仮面劇観に行ったことあったでしょう? あの時いろんな仮面を見て、自分でも彫ってみたいって思ったの」
「じゃあチェリエ、おまえ将来は木彫り職人になりたいと考えているのか?」
シキに真っ直ぐに見つめられ、チェリエは背筋を真っ直ぐにして小さく頷いた。
「やってみたいって、思ってる」
「だったら早めに動いた方がいいんじゃないか? 道具だってここにあるものとは違うだろうし、本気でやりたいんだったら弟子入り先も見つけなきゃいけないだろう?」
「それは、うん。でも、やりたいだけじゃ・・・・・・才能ないと難しい世界でしょう? だからまず自分を試すために、花形の木彫りを・・・・・・それにもうちょっと、家事が出来るようになってから相談しようと思ってたの」
「まあ、家事はともかく」
「ともかくって何!?」
噛みつくように叫ぶチェリエ。それを無視してシキはチェリエの花形の木彫りを手に取って少しずつ角度を変えながら言う。
「才能とかわからないけど、単純に俺はこれをすごいと思ったんだよ。おまえまだ13だし、やりたいなら尻込みせずに挑戦してみろよ」
「シキ兄ちゃん・・・・・・うん。ありがとう」
ちょっと照れくさそうに笑う妹に微笑し、シキは下の妹と弟に目をやり声をかける。
「お前達、手が止まってるぞ」
言われて手と口を動かし出す二人。
会話が止まり、チェリエが朝食を食べ終える。するとフェリエが拗ねた声で話し出した。
「・・・・・・チェリエ姉ちゃんが将来のことちゃんと考えてたなんて」
「何その言い方? 私が何も考えてないみたいに」
「だって・・・・・・」
「フェリエは完璧に家事をこなすお嫁さんになるのが夢なんだろ? いいじゃないか」
シキが口を挟む。
「何かチェリエ姉ちゃんに負けた気がしてイヤ」
パンの残りを口に入れ、膨れた頬で租借(そしやく)するフェリエにシキが笑う。
「何よそれ~」
「やりたいと思えることに出会えて挑戦できるっていうのは幸せなことだと思うぞ? 素直に応援してやれよ。フェリエだってまだ先のことはわからないだろう? おまえだってまだ11歳なんだから」
「うん。そうよね・・・・・・ちゃんと応援するわ! トズみたいに、応援できない無理な夢を見ちゃう場合もあるんだし!」
「え?・・・・・・あ、あぁ」
「僕?」
「トズは昨夜戦闘能力者にはなれないって言われたばかりでしょ?」
フェリエが弟の頭を撫でてそう言うと、トズはしょんぼりとした顔で頷いた。
「うん。僕の初めての夢だったのになぁ・・・・・・」
食事を終えテーブルの上の食器を全てトレーの上に片付ける。
無言となったこの場の空気に下の二人は姿勢を正した。
そしてシキが口を開く。
「フェリエ、トズ。今から大事な話をするから、聞いてくれ」
真面目な顔の長兄に身を固くしながら二人は小さく頷く。
「俺は、この家を出ることになった」
声を上げず驚くフェリエとトズ。
「調理師の資格を取るために、中央の学塔へ行くことになったんだ」
「シキ兄ちゃん?」
チェリエの声を無視して話を続ける。
「調理師の資格はこの辺りの学塔では取ることが出来ないから、家を出て中央の知り合いに世話になることになった。と、・・・・・・俺がいなくなる理由を誰かから訊かれたらそう答えてくれ」
「え?」
首を傾げるトズ。
「・・・・・・本当は、違うんでしょう? どうして?」
フェリエが訊いてくる。
「これから話すことは、秘密にしておかなくてはならない。初学塔をまだ終えていないからって、俺はお前達に嘘を吐きたくないし、お前達ならちゃんと理解し行動出来ると信じてる」
それを聞いていたカルフェは目を閉じたまま〝上手いな〟と小さく笑んだ。信頼している相手からの「信じている」という言葉は、それに応えたいという感情を生むものだ。
シキは二人の顔を見て頷く。
「俺は、光の塔へ行く」
「え?」
「光の塔?」
「昨夜、話しただろう? 能力者が行く学塔だ」
1章-4
「父さん、母さん。今から俺達、畑に行って来る」
シキが食卓の部屋へと戻りそう声をかける。
「ええ?」
「あ、勿論カルフェさんも一緒に付いてきてくれるけど」
後ろに立つカルフェが頷く。
チェリエとカイは出かける前に朝食の片付けを済ませるため皿洗いを始める。
「そうじゃなくて! こんな時まで畑仕事なんていいわよ!」
「いや、畑のことで教えておきたいこともあるし」
「シキ、おまえなぁ」
シキはジョウに近づくと声を潜めて言う。
「父さん、俺達帰ってくるまで母さん横にして休ませてあげて」
「・・・・・・」
相変わらずできた息子にジョウは乾いた笑い声を漏らし、シキの頭に手を置き力強く撫でた。
「ミグラさんは」
シキが問うとミグラは席を立ち上がった。
「私も同行します」
「じゃあ行ってきます!」
玄関を出るとシキの右手をフェリエが、左手をトズが握ってきた。
自分が能力者だという話をしても取り乱すことなく大人しく受け入れた様子の二人だったが、こんな普段しないことをしてくるのは、一緒にいられる残りの時間を大切に思ってくれているのだろうと、シキは二人の手を握り返した。
青空の下、七人は家から歩いて十分程の距離の畑へと向かう。
「兄弟全員で畑に行くのは久しぶりね」
チェリエが笑みを浮かべ言う。
「そうだな」
シキが空を見上げ微笑む。残りの時間を暗く過ごしたくない。カイは昨夜からずっと暗い表情のままだし、フェリエとトズの表情も硬い。雨じゃなくて良かった。この日差しの暖かさが、気分を明るくさせる手助けをしてくれているようでありがたく思えた。
「あれっ?」
突然チェリエが声を上げた。
足が止まりチェリエへと皆の視線が集まる。
「どうした?」
「ん・・・・・・ちょっと・・・・・・ごめん、見間違いかも」
チェリエの視線の先は後方左の小屋。そこには誰の姿もない。
「誰かいたのか?」
「んー。でも今ここにいるわけないし、きっと見間違いね。ごめん。行こ」
そう言って歩き出すチェリエにそれ以上は問わず、シキは視線をカルフェとミグラに移す。ミグラがその視線に問題ないと言うように頷くと、シキは安心して頷き足を踏み出した。
畑に着くとチェリエが小屋の鍵を開け、道具を取り出した兄弟達が動き始める。現在畑は学塔へ行っていないシキとチェリエが任されていたが、他の兄弟達も時間があれば手伝っていたのでやるべきことはわかっている。
葉に付いた虫をシキが取り除いていると、トズが水の入ったバケツを左右一つずつ手に持って歩いて来る。重たいのを頑張って運んでいる姿は見ていて微笑ましい。
「トズ、力がついたな。前一緒に来た時は二つ同時は持てなかっただろう?」
シキに声をかけられトズは笑顔で答える。
「うん! 男だからね! 僕もっと力持ちになるよ!」
「そうか」
「シキ兄ちゃん! これ! この虫も取らなきゃダメ!?」
その声にシキは移動してフェリエの隣りにしゃがみ込む。
「ああ、これもそうだな」
そう言ってシキがその虫を指で摘まんで袋に入れるとフェリエが悲鳴を上げる。
「いやあ! 素手でさわった~!!」
「この虫は直接触っても問題ない。でも中には危ない虫もいるから、おまえはちゃんとその棒で取り除くようにしろよ? 刺されて痛みが出たり、腫れたりもするから」
「言われなくても気持ち悪くて直接なんて絶対さわらない!」
「ハハッ。その気持ち悪い作業をちゃんとやってるんだから、偉いな、フェリエは」
優しく微笑むシキにフェリエは顔を赤くして顔を背ける。
「シキ兄ちゃんが褒め上手なせいよ!」
「シキ兄ちゃん! 堆(たい)肥(ひ)どうする~!?」
今度はチェリエの声が聞こえてきてシキは立ち上がった。
「シキ兄ちゃんが作ったこの堆肥、もう使えるんでしょう?」
「ああ、大丈夫なはずだ」
「兄さん、堆肥まで作ってたの?」
カイが驚いた声を上げる。
「畑名人のナグスのおじさんに訊いて挑戦してみたんだ。金かからないからな」
「これはシキ兄ちゃんが一人でやってたから私わからないよ。作り方教えてよね」
「堆肥の作り方は一応ノートに書いてるけど・・・・・・。これまで通り堆肥は必要な時に売ってるものを使うといい。俺は時間があったからやってただけだし、これからは、俺はいなくなるんだから、無理する必要はない」
その言葉に兄弟達の顔が強張った。
グッと歯を食いしばったチェリエが叫ぶ。
「もう! シキ兄ちゃんの馬鹿! いなくなるなんて言われたら涙出てくるじゃない!!」
言葉通りにチェリエが目を潤ませ睨んできてシキは焦る。
「悪い」
思わず謝れば下の方から呻き声が聞こえてきて、見ればフェリエとトズも今にも溢れんばかりに目に涙を溜めている。二人の呻き声が徐々に大きくなると、とうとうトズが声を上げて泣き始めた。
「すまない。・・・・・・ごめん。ごめんな?」
シキが屈んでフェリエとトズの肩に手を置くと、二人はシキの身体にしがみついてきた。チェリエは流れ落ちた涙を手の甲で拭い、カイは目を伏せ口も閉じたままだ。
シキが途方に暮れた思いでいると、しばらくしてカイの口が開いた。
「お前達、いつまでも泣いてると、兄さんといられる残りの時間が勿体ないぞ」
「カイ・・・・・・」
カイの言葉に二人の泣き声が止まり、シキはホッと息を吐く。
「そうね。・・・・・・どうする? この堆肥、使っちゃう?」
チェリエが場の空気を変えるように訊いてくる。
「そうだな・・・・・・。じゃあ、今日ザクラを全部収穫するか。それでそこに新しく土作りして、クワの種を植えよう」
それを聞いたフェリエがシキの服を握りねだるように言った。
「シキ兄ちゃん、ザクラ収穫するなら前に一緒に作ってくれたザクラの炒め物、また一緒に作って」
フェリエの泣き顔にシキは二回頷き返した。
「そうだな・・・・・・わかった。帰ったら一緒に作ろう。足りない材料は買って帰ろうな」
「うん」
「ザクラの炒め物作るんだったら、プリカもいるんじゃない?」
チェリエがプリカが植えてある所へと移動する。
「ああ、出来れば二つ欲しいな」
「残念、一つ赤いけど、後はまだ赤くなりきれてないものばかりよ」
その言葉に反応したのはカイだった。
「赤くなっただけじゃ駄目だろう」
「え?」
「プリカは硬さを確かめないと」
カイに言われチェリエはしばらく黙ったままだったが、ハッと思い出して手を叩く。
「そうだった! あれ? シキ兄ちゃん、昨日の、大丈夫だったよね?」
顔を強張らせ、不安そうに訊いてくるチェリエにシキは苦笑いを返す。
「大丈夫じゃなかったよ」
「嘘!」
「嘘吐いてどうする」
「なるほどな」
急に割って入ってきた声にシキが驚いて振り向く。
「カルフェさん」
「おまえ、昨日使ったやろ? 能力」
「ッ! 見てたんですか? え!? どこで?」
「あそこ。あの木の上や」
カルフェが指さす方向に目をやる。
「あんなところから?」
「あぁ。おまえが能力使いそうな場所ってここくらいやったし」
「えっ!? じゃあもしかして、昨日シキ兄ちゃんがここで能力使ってなかったらバレずに済んだってことですか? 」
チェリエが声を上げる。
「いや、昨日は俺が単に確認したかっただけや。使う可能性は低かったけどな。こいつが能力者かどうか調査したのは俺達とちゃうし。数ヶ月かけた調査結果が出て、俺達が来たんやから、関係ない」
「兄さんここで能力使ってたのか」
カイの口から漏れた言葉にシキは答える。
「そんな頻繁には使ってなかったんだけどな。どうしても数が欲しい時とか・・・・・・。それに、力を使う時は周囲に人がいないかちゃんと確認していたし、こんな見晴らしの良い場所だから、気付かれるわけないって思ってた」
「実際、調査は大変やったらしい。俺が昨日見たあの場所からだって、動きが怪しいと思っても、本当に能力を使っているかなんて、確認取れへんしな」
「・・・・・・じゃあ何で気付かれたんだろう?」
カイの疑問にチェリエが口を開く。
「植物の生長を促す力? シキ兄ちゃん、もしかして種をそのまま成長させちゃったの? ニョキニョキ~って。それだったら遠目でも気付かれちゃうんじゃない?」
「そんなことしてない。俺も出来るだけ能力は使わないようにしていたんだ」
「だったらどうして・・・・・・カルフェさん、密告があったんですよね? だから調査員が来たんでしょう?」
「・・・・・・そうやな」
「誰ですか? この地区に住む誰かですか?」
真剣な目のチェリエにカルフェではなく横にいるミグラが応える。
「それは教えられません。トラブルを避けるためです。ご理解下さい」
「シキ兄ちゃん、心当たりないの?」
チェリエがシキへと向き直って訊くとシキは目をそらして答えた。
「・・・・・・ない」
「もう! 密告者って誰よ! 絶対許さない!」
憤るチェリエにシキは諭すように言う。
「やめろチェリエ。能力者と気づいたなら当然そうするべき行動だ。密告した相手は何も悪くない。責められるのは隠していた俺だろう」
しかしチェリエはシキの言葉を無視して続ける。
「密告者にはお金が支払われるのよね」
「やめろって!」
「シキ」
虚を突かれるタイミングでカルフェに名を呼ばれシキは戸惑いながら応える。
「はい」
「ちょうどいい。おまえの能力見せてくれ」
「え?」
「カルフェ!」
ミグラが咎(とが)めるように声を上げた。
「ええやん。ここには俺達しかおらん。それに、この子らも見ておきたいんやないか? 兄貴の能力を」
「むやみに能力を使うことは禁止されています。あなたもわかっているでしょう」
「こいつの力はそんな危険なものやないやろ。何かあれば俺が責任取る。大丈夫や」
その会話にシキと兄弟達は二人の関係性に疑問を感じたが、口には出さなかった。
「あ、大きくなってる」
「色も変わっていく! すごい!」
「魔法みたい」
緑色から真っ赤に変化するプリカに、兄弟達は目を輝かせて声を上げる。
シキが触れていたプリカから手を離す。
「チェリエ、触ってみろ」
「え、うん」
言われた通り触れるチェリエ。
「まだ硬いだろ?」
「うん」
「私もさわる!」
「僕も!」
シキは下の妹と弟に場所を譲って触れさせる。
「ん、じゃあもう一度」
そう言ってシキがプリカに触れ、しばらくしてその手を離した。
「見た目変わってない」
下三人の兄弟達が再びプリカに手を伸ばす。
「あ、軟らかくなってる!」
「ホントだ!」
「うん! すごい!」
「このくらいになったら食べられるからな、憶えておけよ?」
「はーい!」
「うん」
「わかった」
シキはもぎ取ったプリカを手に後ろで見ていた三人に目をやる。するとカルフェが手を差し出してきたのでその手にプリカを乗せる。
「すごいな」
カルフェはプリカを見つめ、そう漏らした。
「そんな、たいした能力じゃ」
「いや・・・・・・凄い。なあ、これ、採った後やとその能力効かへんの?」
カルフェの問いにシキは小さく首を傾げた。
「種類によって違うでしょうが、採る前に比べると効きが悪い、といった感じでしょうか? あまり試したことはないんですが」
「・・・・・・そうか」
カルフェは手にしたプリカを見つめ、ゆるりと笑った。
1章-5
少女は両手で握りしめた麻袋を胸に押し当て、自分の部屋で立ちすくんでいた。
昨日届けられたこれを気づかれない場所へ隠さなければならない。
(これがもし、父さんに見つかったら・・・・・・)
父親と少女だけで暮らすこの家。今の時間父親は仕事に出ている。
これが父親に見つかっていないか不安になり、学塔へ向かう途中お腹が痛いからと嘘を吐いて家へ戻ってきた。娘の部屋を勝手にあさるような父親ではないが、万が一ということがある。自分がしたことを父親が気づいているかもしれない。しかしその心配は杞憂で、自分の机の引き出しの奥へ隠していた麻袋を手に掴み、少女はホッと息を吐いた。だが、安心したのも一瞬で、また不安が押し寄せる。どこがいい? どこなら見つからない? ここじゃあすぐ見つかるかもしれない。そう思い別の場所を探し隠す。そしてまた不安になっては取り出し、違う場所を探す。その繰り返し。
麻袋の中には十万ラントが入っている。少女が持つには大金だ。
昨日中央から来たという警備軍の男に受け取りのサインを求められ、密告料として手渡されたものだ。
お金が欲しかったわけじゃない。
少女は誰にでもなく言い訳をしたくなった。
お金はあって困るものではない。だが、お金がなくて困ったと感じたことはなかった。金持ちというわけではないが、周囲と比べても父親の収入で充分不自由のない生活が出来ている。母親がいなくなってからは余計に父親は娘に気を遣うようになり、好きな物を買い与えていた。少女は贅沢な暮らしに興味はなかった。それよりも仲が良くて優しい父親と母親、そして兄弟が欲しかった。そんな暮らしが欲しかった。
お金じゃ買えないもの。
「そうよ、こんなお金なんかじゃ買えない」
――買えないけど、あの家族から奪うことは出来たじゃない。
――あなたの望み通りに。
――このお金は、その報酬よ。
聞こえてきた心の声に、少女は声にならない悲鳴を上げ、手の中のそれを投げ捨てた。
麻袋が壁に当たって床へと落ちる。
彼は近日中に光の塔へ行くと教えられた。
私のせいで。
少女は首を振る。
「私は悪くない」
そう呟くと同時に鳴る家の呼鈴。
少女は身体を震わせた。
シキ達は畑仕事を終わらせ、買い物をして家へと戻った。
コリエの顔色が少し良くなっていることに安心したシキは、フェリエの希望通りに収穫したばかりのザクラを使った炒め物を作ろうと準備を始めた。すると、家族から他にもあれが食べたいあれを作ろうと声が上がり、家族全員が調理にとりかかり、にぎやかに時を過ごすこととなった。チェリエが材料が足りないと買い足しに家を出る。そうこうしている間にも普段はしない出来立てを立ったまま食すという形となり、次々と料理が作られ食べられていく。カルフェとミグラが視覚と嗅覚をくすぐられ、目の前のおいしそうな料理を口にすることが出来ないことを残念に思っていると、家の呼鈴が鳴った。
「誰かしら?」
玄関へと向かうコリエにミグラが声をかける。
「交替の者かもしれません。そろそろ時間なので」
「あら、そうなのね」
そんな会話を耳にしたシキが手を洗って玄関へと向かう。その後ろをカルフェとミグラが続く。
玄関の向こうに交代予定の男が一人で立っている。
「ちょうど良かった。あんなおいしそうなもん目の前にして食べれへんとか、なんの我慢大会や思うとったんや」
「決まりとはいえ、空腹時には少々辛かったですね」
カルフェとミグラが苦笑して言うと、コリエが首を傾げて訊いてくる。
「仕事時間外だったらいいのかしら? 料理詰めますので、ちょっと待ってもらっていいですか?」
「え? いや、それは・・・・・・」
止める間もなくコリエが台所へと戻る。
「いいじゃないですか。たくさんあるし、お腹壊すようなものは作っていませんから」
シキが言うと「それはわかっていますが」とミグラが頭を掻いた。
「それより、申し訳ないんですが、少し付き合ってもらっていいですか?」
「え?」
ミグラとカルフェに持たせるための料理を詰めて玄関へ向かったコリエ。そのコリエが一人で部屋へ戻ってきたのを目にしたカイが問う。
「母さん、兄さんは?」
「買い足したいものがあるらしいの。ミグラさん達にお願いして一緒にちょっと出て来るって。・・・・・・一人で行動出来ないって大変ね」
止まない呼鈴に、少女はとうとう玄関に立っていた。
まるで、留守じゃないことを知っているかのように呼鈴は鳴り続けていた。
何なの?
家へ入る所を誰かに見られたのかもしれない。
もしかしたら緊急な用事かもしれない。
父さんに何かあったのかもしれない。
少女はおそるおそる口を開いて問う。
「誰?」
呼鈴の音が止まった。
「やっぱりいた」
玄関の向こうから知った声が聞こえてきた。
「開けて、サヨリ」
家を出てしばらく歩くと周囲に人がいないことを確認し、シキが立ち止まる。
シキの傍にいるのはカルフェとミグラのみだ。後の一人はつかず離れずの距離を保っている。
「すみません。訊きたいことがあって」
「へぇ? 買い出しは口実やったんか? 何?」
「チェリエの帰りが少し遅いのが気になって。何事もなければいいんですが」
「?」
「あの・・・・・・俺の密告者って、サヨリ・ランデですか?」
少女、サヨリ・ランデは逃げ出したい気持ちで一杯になっていた。
しかしここはサヨリの家の中。逃げ出すことは出来ない。
「開けて、サヨリ」
もう一度力強い声が聞こえてくる。
どうして?
彼女がこの扉の向こうにいる理由は一つしかないように思えた。
しかし、そんなはずはなかった。密告者が誰であるかは公表されないはずだし、昨日の警備軍の人間もそう言っていたのだ。
そうだ、何か別の理由があって訪ねて来たに違いない。
現実逃避をするような思考がサヨリの手を動かした。
鍵が外され玄関の扉が開く。
そこにはチェリエが真っ直ぐサヨリを見据え立っていた。
「その問いに答えることは出来ません。密告した者を守る義務が警備軍にはある」
「わかっています。けど・・・・・・。俺はいいんです。誰が密告者であっても恨むのは筋違いだと思っています。相手に何もするつもりはないし、何も言うつもりもなかった。けど、家族は・・・・・・密告した者を知ることで嫌な思いを互いに抱え込んでもらいたくない。俺がいなくなった後じゃ何も出来ない。もしサヨリちゃん、あの子が密告者なら、特にカイとチェリエに知られるのが心配で・・・・・・」
「シキ、何でその子が密告者やて思うん?」
「あの子しか心当たりがないからです。調査がここ数ヶ月間であるならおそらく、知られたのは年始めの祈願花(きがんばな)の時だろうと」
「チェリエ・・・・・・どうしたの? 何の用?」
サヨリはどうにか笑顔を作った。
「ねぇサヨリ。朝、会ったわよね?」
学塔へ行くバイル達の中にサヨリはいた。
「う、うん。でも今日は学塔行く途中、お腹痛くなって休むことにしたの」
幾分早口で答える。
「へえ? その後、私達のこと、見てたわよね」
「え?」
虚ろな笑顔のまま固まる。
「私達が畑に行く途中、いたでしょう?」
「偶然・・・・・・見かけた、だけ」
「そう。カイ兄ちゃんもいたし、気になった?」
「・・・・・・何で、そんなこと。ホントに偶然、だったし」
「私、知ってるわよ」
「・・・・・・何を?」
「サヨリ、あなた・・・・・・カイ兄ちゃんのこと好きでしょ」
サヨリの顔がカッと熱くなった。
チェリエはそんなサヨリを冷たく見つめる。
「それなのに、ねぇ? あんたでしょ、密告者」
シキの住むこの地区では年始めの風習として、祈願花が行われている。
蕾の花に願いをかけ、その花の世話をし綺麗に咲いたら願いが叶うと云われているものだ。
使われる花の種類は地域によって違うが、この辺りの祈願花はチーという白い花だった。しかし、昔より数が減ったと云われている花で、ここ数年は特にチーの蕾の花をみつけるのは大変で、手に入れられない場合は他の花で代用する者も多かった。それ故に年明けにチーの蕾の花を見つけることが出来た者には羨望の眼差しが向けられる程だった。
今年の年明け早朝、チーの蕾の花を探すためにサヨリは一人家を出た。
父親は昨夜年終わりの酒の席に呼ばれ帰りが遅かったので、まだ眠っている。
チーの蕾の花をどうしても手に入れたいサヨリは走り出した。
目的の場所は幾つかある。ここ数日サヨリはチーの花の場所を探し回っていた。年明け前に摘んでも願掛け効果はないと云われているので、蕾のチーがあるだろう場所を前もって探しておくというのは毎年チーの蕾の花を手に入れている者から伝え聞いた話だ。
「あら、サヨリちゃん」
声をかけられサヨリは立ち止まった。
「そんなに急いで、祈願花探し?」
「はい」
そこにいたのはかつて母親が親しくしていた二人の女性。
「そう。私達も行ってきたのよ。チーはやっぱり見つからなかったから早々に別の花摘んできちゃったわ」
手に持った薄ピンクの蕾の花を持ち上げ見せる。
「サヨリちゃんはチーを探すの?」
そう問われサヨリは頷いた。
「そう。気をつけて。危ないところへは行かないようにね」
「見つかるといいわね」
優しい表情で、優しい声をかけられる。
サヨリは小さく「はい」と答え歩き出す。
しばらくするとサヨリの耳に聞こえてくる会話。
「若いわねぇ。私もあの年の頃は意地でもチーを見つけてやるって探し回ったものよ」
「あの頃よりチーの数減ったから大変らしいわよ。子供が言ってたわ」
「サヨリちゃん、何を願うのかしら? お母さんのことかしらね、やっぱり」
「願った所で今更戻って来ないわよ、あの人は。可哀想にね、サヨリちゃん。お母さんに捨てられて」
サヨリは走り出した。
父親と母親が別れるという話を聞いたのは、サヨリが初学塔を修了した祝いの席だった。
母親の作ったサヨリの好物ばかりが並べられた食卓。
すまなそうな顔をした父親。
笑顔の母親。
その母親が言った。
「あなたが初学塔を修了するのをずっと待っていたのよ。母親として、初学塔を出るまでは責任があると思ってそう決めていたの。私の新しい旦那様になる人も理解のある人でね、・・・・・・優しい人なの。お母さん、幸せになるから、あなたも幸せな人生歩みなさいね」
「あの女のことなんて、何も望んでないッ!」
あんなことがある以前からサヨリは母親のことが好きではなかった。先程の二人とよく父親の悪口を言っているのを知っていた。サヨリにとって、そんな母親よりも少し頼りなくて気が弱いところがあっても、優しい父親のことが好きだった。
苛立つ感情を持て余しながら目的の場所まで走りきったサヨリは息を整えチーを探す。
「ない。・・・・・・採られてる」
そこには蕾のチーの花はなかった。幾つか採られた形跡があり、サヨリは急いで次の場所へと走り出す。
(私がチーに願うのは・・・・・・)
サヨリが心の中で呟くと、一人の青年が脳裏に浮かび頬を染めた。
「あんたが密告者、そうなんでしょ?」
チェリエが確信を持った声で言う。
「し、知らな・・・・・・」
サヨリが一歩下がる。チェリエが玄関の扉を片手で押さえ一歩前へ出る。
「朝もそうだった。何で目を逸らすの? 後ろめたいことがあるからでしょ?」
サヨリは追い詰められ混乱しはじめる。
少女は密告者は守られるという常識を盲信していた。
(嘘つき! どうして!? 密告のことは知られないようにするって言ったくせに! 何かあれば守ってくれるって!)
チェリエに知られたということは、彼の家族全員に密告者が誰か知られてしまうということだ。否、すでにもう知られているのかもしれない。
逃げ場の無い場所へ追い込まれたサヨリは目の前が真っ暗になった。
カルフェはしばらくシキの顔を見続けた後、口を開いた。
「当たりや」
「カルフェ」
「確信持ってるんやから隠してもしょうがないやろ」
ミグラは小さく苦笑する。
「仕方ありませんね」
「それで? カイとチェリエに特にバレたくないって・・・・・・何で?」
「それは・・・・・・」
「言えんことなん?」
「いえ、あの・・・・・・今は先にチェリエを探していいですか? 買い出しで遅くなっているならいいけど、もしかしたら・・・・・・」
「私は悪くないッ! だって仕方がないじゃない! 初学塔で習ったでしょう!? 能力者を見つけたら警備軍へ知らせなきゃいけないって! だってそれが義務なんだから!」
ヒステリックに叫びだしたサヨリの体を押して、チェリエは家の中へと入り、玄関の扉を閉める。人に聞かれたら面倒なことになる。興奮しているサヨリを見て、チェリエは冷静になる。怒りは静かに消さないままで。
「義務? そうね。それでも・・・・・・私があなたなら、密告なんかせずに直接話したと思う。能力者であることを知ってしまったこと。知られた上でどうするか。訊くと思う。親しいとはいわないまでも、知らない関係じゃないんだし、その相手の家族のことも知っていて、その家族の一人を奪うことになるとわかっていて、密告なんか、私ならしない」
「あなたと私じゃ違うの! 私はあなたみたいに簡単に誰とでも親しくしたり話したり出来ない!」
「お金が欲しかった? 密告料貰えたんでしょう? ねぇ、いくら貰えたの? 教えてよ」
「いらないお金なんて! いるなら全部あげるから! もう、帰って! お願い!」
「私だっていらないわよ、シキ兄ちゃんを売った、そんな金」
冷たく言い放たれると、サヨリは顔をぐしゃぐしゃにしてしゃがみ込み泣き始めた。
そんなサヨリを眺めながらチェリエが訊く。
「サヨリあなた、カイ兄ちゃんに嫌われるようなこと、何でしたの?」
「・・・・・・え?」
「普通しないわよね、好きな相手に嫌われるようなこと。・・・・・・わからない。何で?」
――カイさんに、嫌われる。
サヨリは口を薄く開けたまま動かなくなった。
あの日、年明けのあの日。
結局、目を付けていた場所全部走り回ったが、チーの蕾の花を見つけることは出来なかった。落胆しながら林の奥の木の下で休憩していたサヨリは、近づいてくる足音に気づき、そちらを見た。そこにはシキが一人でこちらの方へと歩いてくる姿。慌てて木に隠れたサヨリは見つからないように身を縮めた。顔見知りではあったが、まともに話をしたことがない相手。そして勝手に苦手意識を抱いている相手でもあった。顔もスタイルもいい。その上いつも笑顔で人当たりも良く、しっかりしていて働き者だと近所で評判の高い青年だ。そんなシキに好意を抱いている女性は多いが、サヨリはシキではなく、彼の弟、カイのことが好きだった。学塔へ通う時間を一緒に過ごすことが出来るのがサヨリにとって今一番の楽しみだった。カイはシキのように人当たりが良い方では無く、サヨリは彼の笑顔を見たことがない。しかしシキに劣らす容姿も素敵だし、真面目で頭も良い。人に愛想をふりまかない所が格好良いとサヨリは思っていた。だから、シキの高い評判に隠れて、カイの良さが皆わかっていないと不満にも思っていたのだ。
シキを苦手に思う理由はそれだけではない。
母親もその母といつも一緒にいたあの二人も、シキのことをやけに褒めていた。自分の子供と同じ年頃の青年に「私がもっと若かったら」などと言っているのを聞いて呆れたものだ。
身を潜めていると、シキが先程サヨリが確認したチーのある場所へと向かってるのがわかった。
(あの人もこの場所を知ってたのね。だけど、残念ながらそこにチーの蕾はないの)
シキの落胆した顔が見れるかと、ちょっとワクワクしながらサヨリはこっそり様子を伺う。
「?」
そんなに広い範囲にあるわけではない。一目見たら蕾の花がないことはわかるはずなのに、シキはそこから動かない。サヨリはまた隠れると首を傾げた。しばらくしてもう一度覗き見ると、シキがチーの場所へと手を伸ばしていた。
(え?)
サヨリは信じられないものを見て呆けたように口を開いた。
シキの手にチーの蕾の花が握られていた。
(嘘・・・・・・)
サヨリが見た時はそこにチーの蕾の花はなかった。
(私、見落とした?)
絶対に手に入れてやると意気込んでいただけに、悔しくて唇を噛みしめる。
しかしサヨリはすぐにそうじゃないことに気づくことになる。
(違う・・・・・・違う・・・・・・)
シキが去ってしばらくした後、立ち上がったサヨリはフラフラと歩き出した。
あれからシキは幾本もチーの蕾の花を手にしていた。きっと家族分だろう。あそこは五人兄弟で家族が多いから。
――魔法のようにチーが成長して蕾の花が現れた。
(あれ、あの力・・・・・・普通じゃない。普通出来ない、あんなこと。・・・・・・普通じゃ無い力・・・・・・そうだ・・・・・・あの人・・・・・・能力者だ)
1章-6
シキはサヨリの家へと急ぎながら、今年の年明けの日のことを思い出していた。
年明け早朝、兄弟全員祈願花を探しに出るのはナルダン家では毎年恒例で、シキとカイは一人で、チェリエとフェリエとトズの三人は一緒に家を出た。
年下の三人が探す場所は、足場が悪くない子供でも安全な所ばかりなので競争率が高いためにチーの蕾を見つけることが出来ずに終わることが多い。
しかしシキとカイが毎年家族分を見つけてくるので、ナルダン家ではチーの蕾の花を欠かしたことがなかった。
シキはずいぶん歩き回ったが、チーの蕾の花を見つけることが出来なかった。
(全部採った跡ばかりだ。やはり皆、祈願花の風習、大事にしてるんだな)
実を言えば年明けのこの日、チーの蕾の花を多くの人が手に入れられるようにと、不自然に思われない程度に、シキは年末能力を使ってチーの成長を促していた。
(来年はもう少し数を増やそうかな)
そんなことを考えながらシキは林の中へ入る。
この奥にあるチーのある場所はわかりにくいのでおそらく知る者は少ない。
あそこで家族分のチーの蕾の花を手に入れよう。
なければチーを蕾の花まで成長させる。ずるいやり方だが、祈願花は蕾の花を見つけることに意味があるわけではなく、蕾の花に願いをかけ、綺麗に咲かせることに意味があるので罪悪感はなかった。
家に帰り着くと、先に戻っていたカイがチーの蕾の花を一本花瓶に挿していた。
「見つけたのか、カイ」
「自分の分くらいはと思って。兄さんは今年も家族分見つけてきてくれたの?」
「あぁ」
おそらくカイは、シキが能力を使っていることに気づいていて黙ってる。
そう思いながらシキは作った笑顔で答えた。
「ただいま~!!」
「ただいま!」
玄関からフェリエとトズの声が聞こえてきた。
賑やかに姿を見せた三人、最後に部屋に入ってきたチェリエが声を上げる。
「ただいま! あ! シキ兄ちゃんカイ兄ちゃん。どう? 見つかった?」
「あぁ、今年も家族分あるぞ」
「ほらやっぱり! シキ兄ちゃんチーの秘密の場所をいくつも隠し持ってるのよ! 可愛い妹がいくら訊いても教えてくれないんだから、ホントに意地悪な兄貴よね!」
「可愛い妹?」
首を傾げるフェリエに「わ・た・し、のこと」と答えるチェリエ。
「馬鹿なこと言ってないで、今年はどうだった?」
「全滅!」
「そうか。俺とカイとのを合わせると一つ余るんだ。今年は誰に譲ろうか」
「あ、だったらサヨリがいいんじゃないかしら? 帰りおばさん達が話してたのよ、朝から一人で探しに出たのに、見つからなかった様子だったって」
「そうか」
シキとチェリエが視線を合わせ含みを持った視線をカイに投げる。
「カイ、おまえサヨリちゃんに届けてこいよ」
「・・・・・・何で俺? 余分に採ってきた兄さんか、同い年のチェリエが行けばいいじゃないか」
「俺はあの子と話をしたこともないからな」
「私一本も見つけられなかったし、そんなに仲良いわけじゃないしね。カイ兄ちゃんは学塔の行き帰りほとんど毎日顔合わせてるでしょう?」
「俺もまともに話したことなんか・・・・・・」
「行ってきなさいカイ」
台所で年明けの料理を作っていたコリエが声をかける。
「母さん」
「祈願花を探しに一人で出てたって事は、叶えたい願い事があるってことでしょう。サヨリちゃん、きっと喜んでくれるわ」
カイがチーの花をサヨリの所へ届けに行っている間、シキとカイの部屋で内緒話をするシキとチェリエの姿があった。
「どう思う? あれ」
「まだ気づいてないんじゃないか」
「そうよね、私もそう思う」
サヨリがカイに恋をしていると教えてきたのはバイルだった。
学塔の行き帰りが一緒なので、サヨリのカイに対する目線や行動を見てすぐわかったと話してきたのだ。
「確かにカイと一緒にいるサヨリちゃん、端から見ててわかりやすいよ。カイばっかり見てるし」
「そうそう。あれで気づかないとか、カイ兄ちゃん、鈍いのかな?」
「・・・・・・そうだな」
(そういうおまえも鈍いけどな)
バイルがチェリエに気があることを知ってるシキは緩く笑う。
「恋愛事には興味無いって感じだしね。兄ちゃん達、男同士でそういった話しないの?」
「・・・・・・したことないな、そういえば」
「シキ兄ちゃんはどうなのよ、モテるくせに誘われても断ってばかりじゃない。もしかして、隠れた恋人でもいるの?」
「おまえ、俺にそんな時間あると思うか? 俺の人生計画で恋人なんて、当分ないよ」
「人生計画? 何それ。兄弟揃って恋愛音痴なの?」
あの日以降のことだった。
シキがサヨリの様子がおかしいことに気がついたのは。
カイに恋している子として、シキはサヨリを気にかけ見続けていたので気づいたといえる。カイと一緒の時はカイばかりを見ていたサヨリの視線が、シキに向くことが多くなった。だが、カイに向ける視線とは確実に違っている。
「何だろうな、あの子のあの視線。もしかしたら、カイを好きなこと、俺達にバレたって気づいたのかもしれないな」
あんなことチェリエに話さなければよかった。
密告者が誰か考えた時、シキはサヨリ以外思いつかなかった。
「どうして私が、カイさんに恨まれなきゃならないの?」
サヨリの、か細い声。
「それ、本気で言ってる? 当然でしょう。カイ兄ちゃん、シキ兄ちゃんのこと昔から大好きなんだから」
「・・・・・・え」
「シキ兄ちゃんといつも一緒にいる私のことも、きっと内心面白くないって思ってる。もちろん私や下の二人のことも兄弟として大事に思ってくれてるだろうけど、なんていうか、カイ兄ちゃんにとって、シキ兄ちゃんは特別なのよ。きっとシキ兄ちゃんがいなくなること、うちで一番ショックを受けてるの、カイ兄ちゃんだわ」
密告書を送ってしばらくした後、サヨリは徐々に後悔していった。
能力者を密告するという正しいことをした。
そう自分に言い聞かせながらもサヨリはずっと不安に襲われていたのだ。
密告したことで、どういうことになるのか、考えると怖くなった。
父さんに相談すればよかった。
あの時の私はどうかしていた。
シキが能力者だと知り、家に戻ったサヨリは祈願花のことも忘れ、浮かれるような、不安なような、よくわからない感情を持ったまま、これからどうしたらいいのか悩んでいた。
能力者の数は少なく、希有な存在だ。
過去、この辺りに能力者がいたという話は聞かない。
もしかしたら、警備軍によって情報を隠されていただけなのかもしれないが。
こういった場合、どういう行動を取ることが正しいのか。
「能力者は光の塔に行かなくてはならない。何故ならば・・・・・・」
初学塔で教えられたことをサヨリは呟く。
そんな時だった。カイがサヨリにチーの蕾の花を届けに来たのは。
「うち、一つ余ったから。・・・・・・見つからなかったんだろう?」
サヨリは舞い上がった。
願い事は〝片思いの相手と両思いになれますように〟
この年頃の恋する少年少女達が願う内容として珍しくもない。
サヨリはこの日、そう祈願花に願うつもりでチーの蕾の花を探し回っていたのだ。
シキのことが衝撃で忘れかけていたが、手に入れられなかった悔しさを思い出した。
しかしそれが片思いの相手であるカイによって届けられたのだ。
「ありが、とう」
震える声と手で受け取ったサヨリに一つ頷いただけでカイはすぐに帰っていった。
サヨリはしゃがみ込んでその場からしばらく動けなかった。
自分のためにカイがと思うと鼓動の速さが止まらない。
サヨリは立ち上がるとさっそく花瓶に水を入れてチーの蕾を挿した。
今日はなんて日だろう!
カイは誰彼構わず親切にしたり優しくしたりはしない。
もしかしたら片思いじゃなくて、両思いだったの・・・・・・!?
そう思うとそわそわと落ち着かない。
だったらどうしよう。
カイと恋人になるのなら、彼の家族とも仲良くしなくちゃいけない。
彼の両親は近所でも評判の仲の良さでサヨリが理想とする夫婦だ。
そんな二人の子供であるカイのお嫁さんになれるかもしれないなんて、なんて幸せなんだろう。
まだ初学塔へ通う下の二人も良い。兄弟が欲しかったサヨリは弟か妹が出来るのを夢みていた時期があった。しかもあの二人は礼儀正しくおとなしい印象だから、私でもきっと上手くやれる。
不安なのは同じ年のチェリエだ。彼女は喜怒哀楽がハッキリしていて常に彼女のいる所は人が集まり明るく楽し気だ。引っ込み思案のサヨリは正直苦手だった。長兄のシキと同じく年配の人ともよく話をしていて好かれている。
サヨリはチーの蕾の花に〝カイと恋人になれますように〟と願いながら、すでにカイの恋人となった自分を妄想していた。
チェリエは苦手ではあるけど今まで喧嘩したこともないし、どうにかなるだろう。
問題はシキだ。
能力者であることを隠しているなんていけないことだ。
人の良いフリして皆を騙してるんだわ。
能力者が普通に近くにいるなんて危ないじゃない。
家族になる私がどうにかしてあげなくちゃ!
そんなことを思って密告書を送ったなんて恥ずかしいこと、誰にも言えない。
あれからサヨリはカイの態度で自分に関心がないことに気づく度、夢から覚める思いだった。
「何黙ってるの」
「・・・・・・」
上手く呼吸が出来ない。
密告したことがカイの家族に知られたら、嫌われてしまうかもしれない。
怖くて考えないようにしてきたことが今、現実となっている。
父に知られたら、優しい父のことだ、カイの家族に頭を下げに行くだろう。
私のせいで。
間違ったことはしてないはずなのに、私が浮ついた心で行動したせいで。
密告書を送ってから数ヶ月経ち、何の返答もなく、シキがいなくなることもなく、大きな変化のない日々を過ごしていると、密告書が光の塔へ届かなかったのではないか、と思うようになっていった。もしくはシキが能力者というのは私の間違いだったのかも、そうであればいい、と願い、日々を過ごしてきた。
なのに、今頃になって・・・・・・。
「ごめんなさい・・・・・・嫌わないで。言わないで、ごめんなさい、お願い・・・・・・」
震えて縮こまっているサヨリを見下ろしチェリエは溜め息を吐いた。
その時、背後の扉の向こうに数人の気配を感じ、チェリエが振り返る。
鳴る呼び鈴の音。
チェリエがノブに手を伸ばす。
やっぱり来た。
誰かはわかっていた。
開かれる扉。
シキと対峙(たいじ)するチェリエ。
「私が悪いことは解ってる。怒られるのは覚悟の上よ。ひっぱたいてくれて構わない。でも、言いたいことを言ったことに後悔はしてないから」
シキはそう言い切ったチェリエの向こうで、体を小さく抱え込んで泣いているサヨリの姿が視界に入り、眉を顰めた。
「説教は後だ」
そう言って両手でチェリエの頭を摑(つか)み、そのまま後ろのミグラとカルフェへと押しやる。
「すみません、これ、お願いします。後、少しだけ時間下さい」
そう言ってシキは返答を待たず、扉を閉めた。
二人きりになってサヨリはどうしたらいいのかわからず固まった。
シキはそんなサヨリの傍へ行くとしゃがみ込んで声をかける。
「すまない。チェリエが何を言ったか知らないが、サヨリちゃん、君は何も悪くない。当然のことをしただけだ。俺は君に対して申し訳なく思っている。・・・・・・年明けの、林の中だよね?」
サヨリは顔を伏せたまま頷く。
「やっぱりそうか。俺がもっと気をつけるべきだった。大した力じゃないということをいいわけにして、18まではと、家族と共にいる時間を延ばしたかっただけなんだ。誰も傷つけずに、迷惑をかけずにと思っていたのに・・・・・・この数ヶ月の間ずっと、君を気に病ませてしまったね」
優しく語りかけるシキの声にサヨリは顔を上げる。
涙がこぼれた。
シキはサヨリに小さく微笑み頭を下げた。
「ごめん」
サヨリは何度も首を振って「私こそ、ごめんなさい」と、か細い声で謝った。
「・・・・・・カイさん、怒ってますよね?」
「カイ? 大丈夫。カイはまだ何も知らない。気づいたのはチェリエだけだ。心配しなくて良い。チェリエには口止めするし、君を泣かせたことも叱っておくから。・・・・・・反省して謝ってきたら、聞いてやって欲しい」
「無理です。きっと私のこと、一生許してくれない」
そう言ってまた小さくうずくまるサヨリに「大丈夫だから」と言って、彼女の頭を優しく撫でた。
1章-7
「え? あの子達、駐在所にいるんですか?」
ナルダン家に交代に来た警備軍の男が再び訪れていた。
買い出しに行ったはずのシキとチェリエが二人共帰って来ないので心配していた所だった。
「シキ殿から伝言で『チェリエに話しておきたいことがある。それが終わればすぐ戻るので心配しないで欲しい』とのことです」
「本当ですか? 光の塔へもう連れて行ったなんてことは」
ジョウが問う。
「緊急なことが無い限り、そんなことはしません。ダリス殿も現在こちらの区長の所でシキ殿の戸籍など、書類や変更手続きの最中ですし」
そう聞いても皆不安な気持ちが消えないことが表情でわかる。
カイが口を開いた。
「俺、迎えに行ってくる」
「おまえ、女の子を泣かせるな」
「恨み言の一つや二つや三つや四つ、言ってやりたかったの!」
「悪いのは俺だって言っただろう? 俺が泣かせたみたいで心が痛くなったぞ」
「サヨリはシキ兄ちゃんと過ごす私達の時間を奪ったの! 怒って当然でしょう?」
二人が言い合う一室の端のテーブルでカルフェとミグラは昼食をとっていた。
「仲ええな、あの二人」
「まあ、言いたいことを言い合えるというのは仲がいい証拠ですからね」
「ん、うまい」
「俺は怒ってないし、むしろ申し訳なく思ってる。俺の不注意が原因で、結果年下の女の子を追い詰めて泣かせてしまったんだから」
「・・・・・・私が泣かせたんだから、シキ兄ちゃんは関係ないじゃない」
「関係ないわけないだろう。俺のせいだ。・・・・・・チェリエ」
シキがチェリエの頭に手を乗せる。
「おまえはしっかり者で面倒見も良い。俺がいなくなった後、前向きで明るいおまえがいると思えば安心できる。頼りにしてるんだ」
「・・・・・・煽(おだ)てたって謝らない」
「煽ててない。本当のことだ。・・・・・・サヨリちゃんは今年の年明けからずっと不安だったと思う。正しいことをしただけなのに。俺が謝っても聞き入れてはくれなかった。あの子が罪悪感を抱え込んだままこれからも生きていかなきゃならないことが俺には辛い。・・・・・・チェリエ、頼みたいことがある。おまえがあの子を支えて欲しい」
「・・・・・・え?」
「おまえの出来る範囲で構わないから、俺がいなくなった後、俺の不始末の面倒を見て欲しい。頼む」
頭を下げるシキにチェリエの顔が泣きそうに歪む。
「ずるいのよ、シキ兄ちゃんは」
「密告のこと、誰にも言うな。特に、カイには」
「・・・・・私、カイ兄ちゃんのことがあるから、余計裏切られた気持ちになったのかもしれない。何となく、うまくいけばいいなって思ってたから」
「サヨリちゃん、お父さんはいい人だけど、お母さんのこともあったし、うちと違って兄弟もいないから、心配なんだよ」
「・・・・・・いいわよ。わかったわよ。誰にも言わないし、もう責めないし、文句も言わない」
「チェリエ」
「だけど、今回のこともあるし、もともとサヨリ私のこと苦手みたいだったから、フォロー上手くいくかわからないからね? カイ兄ちゃんとのことも、正直、無理だと思うけど、どう転んでも私の感情は挟まない。ただ見守ることにする。それでいい?」
「あぁ。ありがとう、チェリエ」
シキが安心した顔でチェリエに微笑んだその時、部屋の扉が開いた。
「何の話?」
その声にシキとチェリエが青ざめる。
振り向くとそこにカイが立っていた。
「カ、カイ。何でここに?」
「迎えに来た。言っておくけど、このまま戻って来ないんじゃないかって不安になったのは、俺だけじゃ無いから」
「え?伝言は」
「伝えました」
カイの後ろから伝言を頼んだ警備軍の男が姿を現す。
「あ、すみません」
「いえ」
互いに頭を下げる二人。
「チェリエと二人で話すだけなら家でもいいはずだろ? けど、余程俺達に聞かれたくない話だったってわけか」
「いや、あの・・・・・・」
「サヨリの名前が聞こえた。つまり、そういう話か」
「?」
もしかしなくても、密告者がサヨリということを知ってしまったのかとシキとチェリエが身を固くする。
しかし、続いた言葉は二人にとって思いもしないものだった。
「兄さん・・・・・・サヨリのこと、好きなんだろう?」
「「・・・・・・はぁ!?」」
「・・・・・・違うの? シキ兄さん、あの子のこと、前から随分気に掛けていたから」
「ち・が・う! そうだけど! ち・が・う!」
気持ちは同じだったが、脱力しながらそう返答したのはチェリエだ。
「・・・・・・違うのか。だったら何でサヨリの名前が?」
「買い出しの途中で偶然会ったのよサヨリに!」
「?」
チェリエがもっともらしい嘘を吐き始める。
「体調悪くして学塔から一人で戻って来たって言うから、家まで送っていったの! シキ兄ちゃんも途中で会ったから一緒に! ね?」
チェリエに応え、シキが頷く。
「ああ」
「・・・・・・へえ」
納得したのかしていないのかわからないカイの表情に、その嘘だけじゃ足りないと、続けてシキがチェリエの嘘を付け足す。
「その帰りにこの駐在所に昨日泊まった話になって、チェリエが中がどうなっているのか見てみたいっていうから、頼んで入らせてもらったんだ」
シキが端にいるカルフェとミグラへと声をかける。
「ですよね?」
嘘に付き合わせるのは申し訳ないが、警備軍にとっても密告者が誰か知られるのは好ましいものではないはず。
ミグラが「はい」と微笑んで答える。
顔には出さずにホッとしたシキが続けた。
「で、そうこうしていたらチェリエとの話が止まらなくなって、長くなりそうだったから伝言をお願いしたって訳だ。心配かけて、すまなかった」
「・・・・・・俺は別に。兄さんがまだいるなら」
「カイ・・・・・・」
「それより。・・・・・・それなら俺も、兄さんと二人で話す時間が欲しい。昨夜、ちゃんと話せなかったこと、後悔してたから」
デサネ・ヌーバの屋敷。
区の役員を務める40代の男が二人、部屋へと入ってくる。
「区長、ノンスーダン家からの使者の方、お帰りになりました」
「そうか」
頷くデサネと同じテーブルの席には光の塔からの来客、ダリス・フェーダーと側近一人の姿がある。
「これで先程使者に手渡した書類がノンスーダンの領主の元へと届き、しかるべき処理がされれば、管理所で扱うシキ君の戸籍・預金の変更手続きは完了となります。デサネ区長には今度彼に関することで問題が生じた場合、警備軍、光の塔へ緊急報告、特に問題が無くても定期の報告書の提出は忘れぬようお願いします」
「お任せ下さい」
胸を張って答えるデサネが和やかに話し出す。
「いやしかし、能力者が私の区内にいるとは、驚きでしたよ。区長会に出席して、まれに話に聞くことはありましたが、本当に数が少ないようで」
「デサネ区長は喜んでおいでのようですが、能力者の存在が面倒と捉える区長もいらっしゃいますよ。トラブルの元だとね。実際残された家族や親戚同士の金銭面の争い、能力者について調べる怪しげな組織もある。そういった対応に手を焼いている区長も中にはいます。だからこそ、その報酬として区の予算に特別手当が付くわけですが」
「いやあ、お金の面はともかく、私は子供の頃から能力者に憧れを持っていましたから」
「あぁ、そういった方も多くいますね」
ダリスが微笑し答える。そこに、一人の男が入室してくる。
「どうした? まだ警護の時間だろう」
今の時間、シキの警護を任されている男が姿を見せたことに首を傾げたダリスが問う。
「シキ殿の警護は、現在ミグラ達が」
「そうか。それで、何があった?」
「シキ殿と、彼の妹、チェリエさんに密告者が誰であるか知られました」
「何!?」
デサネが声を上げる。ダリスが話の続きを促す。
「その件は一段落しているのでご安心下さい。ここ数ヶ月密告者の様子がおかしかったことで、お二人は気付いたようです。買い出しから戻らないチェリエさんに不安を感じたシキ殿が、他の家族の方には気付かれないよう密告者の家へ向かい、その場を収めたといった所でしょうか。その後、駐在所で妹さんの怒りを静め、密告者が誰であるか他言しないように約束させたとのことですので、我々の出番はないようです」
「そうか」
ダリスが頷き、デサネが得意げに話し出す。
「なるほど! ナルダン家の長兄であるシキ君は頭も良く、家族想いで働き者だとこの辺りでは評判でね、噂に違わぬといったところですな」
「その後、弟のカイ君がシキ殿と二人で話がしたいと希望され、昼食休憩を終えたあの二人が引き続き警護を買って出てくれましたので、お任せしてきました」
シキは夕食の時間までには戻ることを伝えるよう言ってチェリエを家に帰した。
そしてシキはカイを外へと誘った。
駐在所を出て、どこへ行くのか問わないまま、無言でカイはシキの行く道を歩く。
その後方、距離を取ってカルフェとミグラが続く。
しばらくすると、カイはシキがどこへ向かっているかに気付いた。
「・・・・・・懐かしいな」
カイが言うとシキが「ああ」と応えた。
初学塔へと続く道だ。
初学塔は何歳になったら行かなくてはならないという決まりがあるわけではない。
一般的には7歳から。そして16歳までの間に終える。
必須授業を全て受け、全ての試験に合格すれば修了となる。
シキが7歳になった時、近所で同い年のバイルが一緒に初学塔へ行こうと誘ってきた。
しかしその時ナルダン家は、父のジョウが働きに出て、母のコリエが家で四人の子供を抱えている状態だったので、長兄であるシキは母親の手伝いをするからとそれを断った。
「カイ、おまえが7歳になったら一緒に初学塔へ行こうな」
「うん!」
シキはカイと一緒に家の手伝いをし、妹達の面倒も見た。
カイは兄のことが大好きだったので、遊ぶ時間が少なくても文句も言わず、シキの後を笑顔で追いかけていくような子供だった。
カイが7歳になって一緒に初学塔へ通い出すと、二人だけで過ごす時間が多くなった。
初学塔からいつもより早く帰れる日は内緒で寄り道をすることもあった。
山は危険なので行くことを禁じられていたが、手頃な遊び場となる林があり、そこで二人は虫を捕まえたり、果物をみつけて食べたりしていた。
遠目に初学塔が見える。シキは立ち止まってその建物をしばらく眺めた後、初学塔へと行くのとは違う道を歩き出した。カイも後を続く。二人で寄り道して遊んだ林へと続く道だ。
その日、初学塔の帰り、いつもの林に寄り道をしていた二人は、お腹がすいていたので手分けして果物捜しをしていた。
「兄ちゃ~ん!」
シキが自分を呼ぶ声の方へ行くと、木を見上げ指し示す弟の姿。
「あれ、前に食べたのと同じやつ?」
「そうだな、あれはおいしかった」
「うん! おいしかった!」
この頃、シキの方が背が高く力もあったので、カイには危ないからと木登りをさせていなかった。
カイの期待する目に促され、シキはその木を登り始める。
問題なく登り、目的の実をもぎ取ったシキは、下にいるカイへと実を一つずつ落とす。
二つ受け取ったカイはシキが降りてくるのを笑顔で待った。
「カイ。これ、少し硬いからまだ早いかもしれない」
降りてきたシキがそう言うと、カイは「え~」と声を上げながら悲しそうな顔で果物を見つめる。名前は知らないが、熟れていたらとても甘く美味しい果物だった。
カイのその顔を見て、シキは元気づけようと声を上げる。
「じゃあ、食べる前に応援してみるか?」
「おうえん?」
「ほら、母さんが料理作るときによく言ってるだろ? がんばれがんばれおいしくなーれ! って。応援すると、料理がおいしくなろうって、がんばってくれるんだって」
「応援! やる!」
カイの瞳が輝き、シキは笑った。
「よーし、じゃあやるぞ!」
「うん!」
シキは果物の実を両手に包み上下にゆらゆらと揺らし始めた。
「がんばれがんばれ、おいしくなーれ!」
すると、カイもシキの真似をしながら応援し始める。
「ガンバレガンバレ、おいしくなーれ!」
「がんばれがんばれ、おいしくなーれ!」
「ガンバレガンバレ、おいしくなーれ!」
「・・・・・・よし、おいしくなったか食べてみよう」
「みよう!」
二人は顔を見合わせ頷いた。
同時に手にしている果物に齧りつく。
「んっ!」
「ん!!」
「おいしい!」
シキは驚きの声を上げる。
「うえええっ」
だが隣りのカイは口の中のものをペッペッと吐き出した。
「あれっ? 大丈夫か、カイ?」
「おいしくない~」
涙目で兄に訴える。
「兄ちゃんの食べろ、甘くておいしいから」
そう言って自分の実をカイに食べさせる。
「・・・・・・! ホントだ! おいしい!」
口の中で広がる甘みに笑顔になるカイ。
シキはカイの実を少しかじり顔をしかめた。
「確かに、カイのやつは渋くておいしくないな」
色や硬さは同じだったのに。本当に応援が効いたのだろうかとシキは首を傾げる。
するとカイは「僕の応援がダメだったのかな」と肩を落とした。
「そんなことないさ、こいつは俺のやつより、もっとがんばらなきゃおいしくなれなかったんだよ」
「じゃあ、もっと応援したらおいしくなるのかな? 兄ちゃん! 僕のそれに応援してあげて? 兄ちゃんが応援したらがんばっておいしくなってくれるかもしれない!」
純粋な弟の期待の瞳に、シキは頷いた。
「そうだな、じゃあ応援してみるか」
自分が応援して本当においしくなるか不安だったが、弟の期待に応えないわけにはいかない。
「がんばれがんばれ、おいしくなーれ! がんばれがんばれ、おいしくなーれ!」
先程と同じように実を両手で上下に揺らしながら(本当においしくなれ!)と願う。そして応援し終えたシキが手の中の実を見た。
(あれ? なんだかさっきよりも赤く色が変わってるような気がする)
力を入れて握ってみると、硬さもさっきより軟らかくなっている気がする。
「兄ちゃん、兄ちゃん、食べてみて!」
「あ・・・・・・ああ」
シキはその実を少しかじった。
「・・・・・・甘い」
「えっ! ホント!? すごい!!」
カイが手を伸ばしてシキの手にある実をかじる。
「ホントだ! おいしい!! すごい! すごい兄ちゃん!!」
興奮して飛び跳ねて喜ぶカイに笑顔を見せながら、シキは内心首を傾げていた。
そのことがきっかけで〝応援〟がカイの中で遊びの一つとなった。
自分が応援してもおいしくならないが、シキが応援するとおいしくなる。
カイは単純に「兄ちゃんすごい!」と喜んでいたが、シキは何かおかしいと頭を悩ませていた。
寄り道をしていることは内緒だったので〝応援〟のことは二人の秘密にした。
カイは大好きな兄ちゃんと秘密を持つことも喜んでいるようだった。
シキはある日、一人でいる時に土から芽が出ているのを見つけ、近づいて指先で触れてみた。そして小さな声で「がんばれがんばれ、大きくなーれ」と言ってみた。すると、その芽が変な動きをして形を変えた。シキは驚いて指を離す。周囲を見回し、誰もいないことを確認する。そしてもう一度おそるおそる指で触れた。少し考えて、今度は両手を伸ばして芽を包むようにしてみた。
そしてもう一度、応援の声をかける。
それからシキはカイに頼まれても〝応援〟をしなくなった。
〝応援〟を頼まれるのを避けるために寄り道もしなくなった。
理由を聞いても教えてくれない。
カイはがっかりしながらも、それ以外はいつも通りの優しくて頼もしい兄の後を変わらずついて回った。
1章-8
もう何年も来ることがなかったこの場所は、シキにはあまり変わっていないように思えた。
(そんな訳ないか)
思わず笑みを零す。
実際は木の幹は太くなり、丈も高くなっている。
上を見上げれば、あの頃より空の青が見える面積が少なくなった気がする。
「カイ、そういえばあの果物、今の時期、ちょうど生っているんじゃないか?」
「・・・・・・ナルジェ、っていうんだよ」
「あの果物の名前か? へぇ」
店にも置いていない果物の名前を知る機会はシキにはなかった。
カイはどうやって知ったのだろう。
二人はナルジェを見つけるために林の中を歩き出した。
「あ、あった」
「・・・・・・うん」
ナルジェの木を二人は見上げた。
ずいぶん上の方に、たくさんの実が生っている。
「・・・・・・あれから八年経つか」
「・・・・・・うん」
「ごめんな、カイ」
「何?」
「一緒に通っていた初学塔で、能力者のことを教わった日の帰り道、おまえは俺の手を強く握って、イヤだって言った。泣きながらイヤだイヤだってさ・・・・・・」
「・・・・・・兄さんは、俺の願いを叶えてくれた。兄さんがいなくなるのはイヤだっていう、俺の願いを」
シキは違うというように首を振る。
「俺も、恐かったんだよ。家族と一生会えなくなることが恐くて、大切なものが全て奪われる気がして。けど、それがこの世界で生きる上での決まり事なら、そうしなきゃいけないんだと思って。・・・・・・でも、おまえがイヤだって泣くから、おまえのために、黙っておこうって決めた。本当は、自分のためのくせに、おまえをいいわけにして、兄貴ぶって格好つけてた」
「ずっと、何も言えなかったし、何も訊けなかった。口に出したら、兄さんがいなくなると思って、恐くて」
「ずいぶん長い間、二人して知らないふりをしていたな」
「うん」
二人は木を見上げたまま会話を続ける。
「準備期間は長かったと思うんだ。俺なりに考えて、俺が急にいなくなっても大丈夫なようにしてきたつもりだ」
カイが小さく笑う。
「ノートにいろいろ書き残してたよね」
「そう。料理のレシピや、買い物のお得情報、ここ数年の畑の記録。どこに何を片付けているとか。・・・・・・あ、手紙は残してないぞ。いつか書いたの取り出して読み返したら、恥ずかしくて、思わず燃やしちまったからな」
間を空け、二人して吹きだす。
「何だよそれ」
おかしそうに笑いながらカイはシキを見る。
目が合ったシキが嬉しそうに微笑んだ。
「久しぶりに見た気がする」
「え?」
「カイのそんな笑顔。・・・・・・おまえ、あまり笑わなくなったから。俺のせいだなって、ずっと思ってた」
「兄さん・・・・・・」
「昨夜、カイに言われたこと、少しだけ当たってるよ。わざとバレたわけじゃなかったけど、本当に気付かれないようにしたけりゃ、全く能力を使わなければよかったんだ。でも、隠し事は正直苦手だからな。ずっと悪いことをしている気がして、落ち着かなかった。これから先のことを考えると、どうするのか決めきれないままでいる自分にも嫌気がしてたし、俺ももう16だ。本気でやりたいこと、興味があることを見つけて、早く自分の力を試してみたいって気持ちも持ってた」
「・・・・・・兄さんは、光の塔に行くこと自体は嫌じゃないんだな」
「そうだな。不安もあるけど、嫌ではないのかもしれない。俺の能力なんて、大して役に立たないだろうけど、どんな世界なのか興味はある。警備軍に入ることも悪くないと思う」
「けど、俺達とは一生会えなくなる」
カイが泣き笑いのような表情を浮かべ言うと、シキは悲しそうに笑った。
「そう。それがなければな」
「おい!」
突然離れた場所から声がかけられ、二人は驚いて振り向く。
そこにはカルフェとミグラが立っており、声をかけたのはカルフェの方だった。
カルフェが二人の方へと歩き出すと、ミグラもその後を続く。
「悪い。邪魔しないようにと思ってたけど、聞こえちまったからな」
兄弟の前に立つカルフェ。
「あのな、能力者やから一生会えなくなるなんて、わからんからな?」
「え?」
カルフェがナルジェの木を見上げる。
その彼の右手がゆっくりと上がり、指先が素早く空を切った。
「カルフェ!」
ミグラの諫める声。
強い風の音。
思わず見上げたシキとカイの瞳に映ったのは、実を二つ付けた枝が、何かに切られ落ちる瞬間だった。
更に強い風が吹き、落ちてきたその枝をカルフェが摑む。
口を開けて呆けている兄弟に向かってカルフェは言った。
「俺も、能力者や」
驚いて言葉も出ない兄弟の前でミグラが声を上げる。
「カルフェ! 無駄に能力を使うことは」
「禁止されとるな。わかってる。もうせえへん」
全く反省の色が見えないカルフェにミグラは溜め息を吐いた。
「まあ、ちゅうわけで、能力者の先輩として話させてもらう」
シキは呆然としたまま「はい」と声を出した。
「俺が今能力者付き側近の試験の最中やって話、昨夜したやろ?」
「はい」
「能力者が能力者付き側近の資格を取ろうっていうのは、知らん者からしたらおかしな話に聞こえるやろうけど、この資格を取ることで俺の自由がだいぶ変わるんや」
「自由」
「そう。外での行動範囲が広がったり、ある程度なら一人で行動することも許される。能力者は基本、いつも監視の目がついているようなもんやからな」
「今の君の状態がそうだ。俺達の監視の目がついている。ついでに言うと、このカルフェの監視も私がしているという面倒な状態でもある」
「・・・・・・なるほど。そうなんですね」
ミグラの言葉に頷くシキ。
「自由を得るために、俺もそれなりの努力はしてきた。〝不可能を可能にする努力をしないまま諦めるな〟って言葉がある。おまえも、このまま一生家族に会えないなんて、最初から諦めるなよ」
「・・・・・・努力をすれば、可能なんでしょうか?」
「水を差すようですが、簡単ではありませんよ」
「おまえなぁ」
カルフェがミグラを軽く睨む。
「あなたと同等の資格を彼が努力の末得たとしても、難しいものは難しい。簡単とはいえません」
「頭固いな、努力で足りない分は頭使ったらええんや」
「は?」
カルフェがシキに向き直り、口の片端を上げた。
「シキ、おまえに提案がある。取引、ともいうな」
「取引?」
シキは先程からの話の流れに頭がついて行けないでいた。
大体、この人の能力は何だ? 風を操ったように見えた。風。自然を操る力。
まさか・・・・・・。
――戦闘能力者?
シキの体がブルリと震えた。
カルフェが真剣な顔でシキを見る。
「俺は、おまえの能力が欲しい」
「えっ?」
「俺がここに来たのも、おまえの能力のことを偶然知って、無理矢理同行させてもらったからや。そんな我が儘が通るくらいの力が俺にはある。俺が偉いというより、俺の持つ能力が偉かっただけやけどな。戦闘能力者は能力者ランクの上位。いずれは北部五山のどれかの大将を任されることになるやろうって云われとる」
「大将・・・・・・。やはり、戦闘能力者、なんですね」
「シキ。おまえは、おまえ自身の能力を過小評価しているようやけど、俺にしてみれば、俺の能力と取っ替えて欲しかったくらいや」
「は?・・・・・・え、どうして」
「俺は、ガキの頃、薬師(くすし)になるつもりやった」
「薬師・・・・・」
「薬師としてみれば、おまえの能力はとんでもなく魅力的なんや。最も効能の高い状態の薬の原材料を採取することが出来るんやからな」
「・・・・・・」
シキは自分の能力がそんな風に役立つことが出来るのかと驚く。
カルフェは手に持った枝を揺らしながら話を続けた。
「俺の死んだ母親が薬師やったんや。主に薬の原材料を採取する仕事をしていた。俺も物心つく頃には母親の仕事を手伝ってて、薬師を一生の仕事にするつもりやった。せやから、能力者やからって、俺が決めた仕事を取り上げられるのは我慢ならんかった」
そこでミグラがカルフェを軽く睨みながら口を挟んだ。
「だからといって、当時11歳だった子供が逃亡なんかしないで下さいよ。捜索部隊の面々がどれだけ苦労したか」
「「逃亡!?」」
シキとカイが同時に声を上げた。
「戦闘能力者の力を持つ子供が逃げ出したんです。極秘で捜索という、厄介で面倒なことをこの人はしでかしたということです」
「うるさいなぁ、昔の事をいつまでも。・・・・・・けど俺としては結果悪くなかったんや。逃亡した先の北部で、俺と同い年で、同じ能力を持つあいつらに出会えたんやからな」
「とんでもない話ですけどね」
ミグラが小さく息を吐く。
シキとカイはとんでもない話過ぎて言葉が見つからない。
「ああ、そうや。そいつらがシキ、おまえみたいに能力のこと隠して、18になるまで家族のもとで過ごそうとしてた奴らや。昨日ダリス殿が話してたやろ? 俺が紹介したる」
「あ、はい。・・・・・・ありがとうございます」
シキはそう答えながらも(ということは、その二人も北部五山の大将となる人達なのではないだろうか?)と混乱しそうな頭を指で支えた。
「で、結局いろいろあって、そいつらと一緒に光の塔へ行くことになったんやけど。その時、北部での捜索部隊の隊長やった奴に言われたんや。物事のマイナス面ばかりをみていると、前に進むことが出来ないぞ。ってな。薬師になりたいのに能力者だからそれが許されない? そこで思考を止めるな。能力者だからこそ出来ることがある。おまえの場合、まずはやるべき事をやって周囲を認めさせろ。そうすると自由と力と金が手に入る。そうしたら、それを使ってやりたいことをやればいい。・・・・・・馬鹿にした言い方やったから、その時はむかついたけど、言われたことは間違ってなかったからな。それから俺は真面目にやるべき事をやった」
「薬師に、なるために?」
「いや、薬師の資格は去年もう取った」
「え?」
「俺はいつか、北部に薬の研究所を作る。金と力があればそれが出来る」
「・・・・・・研究所」
「狙ってるのは緑山や。あそこの山々は誰の手も入っていない自然の宝庫。薬師達の間でも稀少な原材料が採れるやろうと云われてた。が、場所が場所やからな。ただの薬師には危険過ぎる」
「戦闘能力者であるカルフェさんなら、大丈夫ということですね」
「まだ先の話やけどな。うまく緑山の大将に収まることが今の俺の目標や」
「・・・・・・すごいです」
感心した様子のシキに、カルフェは手にしていた枝を突きつけた。
「え?」
「やる。まだ実が硬い」
受け取ったシキが実に触れる。確かにまだ硬い。
「というのが、俺がおまえを欲しがってる理由や。いつか、おまえを俺の側近の一人として迎えたい」
「側近・・・・・・」
「ま、待って下さい! 北部に行くということは、魔物の捕縛にも参加させられるということですか?」
カイが思わず声を上げた。
カルフェは緩く笑って「いや」と否定する。
「シキみたいな能力者を、そんな危険なことに参加させへん」
ホッと息を吐くカイ。
「あ。けど、能力の他に、料理の腕がいいっていうのは、ありがたいな。食べたいもんをすぐ作ってくれる側近なんて、理想やないか」
「・・・・・・あなたは、側近に何を期待してるんですか?」
ミグラの低い声が問う。
カルフェはそれを笑って流し、シキを見る。
「という訳で、俺はおまえを、他に取られないうちに、まずは本人の許可を取り、俺のもんやって前もって手を打つために来た。そこで、取引や」
カルフェがニヤリと笑う。
「能力者とその家族が会いたいと言っても、それは通らんやろ。規則やからな。けど、そんな正当な方法やなければ、頭使ってどうとでもなる」
シキとカイが目を合わせる。そんな簡単な話だろうか?
「俺もおまえも、力つけてからの話やで? たとえばカイ、学塔で商学について学んでるらしいけど、生産者と消費者をつなぐ流通業ってあるやろ? おまえがその辺りの資格を持ってれば、俺が欲しい商品をおまえに直接持って来させることも可能や。そん時に俺の側近と会って話すことなんて、なんの問題もないやろ」
「・・・・・・」
カイは自分の中に、新たな道が真っ直ぐ引かれたのを感じた。
「妹のチェリエが言ってた木彫りの話も、あの子がその世界で名を上げれば、俺が興味を持って直接本人に会って話がしたいと言っても不自然やない」
カルフェの語る未来が、シキとカイを強く惹きつける。
「他にも考えればいろいろ出てくるやろ。シキ。おまえが望むなら、俺は協力は惜しまん。おまえの能力を俺が自由に使うための取引や。・・・・・・悪い話やないやろ?」
その通りだ。悪い話ではない。
悪い話どころか、自分の能力をそんな風に役立てるなんて願ってもないことだ。
ましてや、別れたら二度と会うことが出来ないと思っていた家族と会うことが出来るなんて。
だが、そこに行き着くまで、簡単ではないだろう。
どれだけの年月が必要なのか。
それぞれが、それぞれの道で頑張って、結果を出していかなければその未来は来ない。
目の前に立つ青年の瞳は自信に満ちていて揺るがない。
きっと沢山の経験と努力をしてきた人なのだろう。
一つしか歳が違わないのにと、シキはひどく出遅れた気持ちになる。
この焦る気持ちは、向上心がある証拠だ。
シキは自分自身をそう分析し、背筋を正した。
カルフェを真っ直ぐに見据え、頭を下げる。
「宜しくお願いします」
1章-終
シキが光の塔へと旅立ち三日経った。
カイは自室で独り勉学に励んでいた。
明確な目的が出来ると、こんなにも集中出来るものなのかという発見があった。
今までどこかぼんやりとしていた自分の未来に、はっきりとした目標を置いた。
その目標を達成すれば、また次の目標が待っている。
手にすると決めた資格がいくつかある。
――〝いつか〟のために。
一区切りついたところでカイが顔を上げる。
視線の先には木の枝が大事に飾られてある。
その切り口はまるで刃物で斬ったかのようだった。
シキに頼んで譲って貰った、あの時のナジェリの枝だ。
実の方はあの日シキが能力を使って二人で食べた。
八年ぶりの味だった。
〝応援〟を声に出すのはこの歳ではさすがに恥ずかしいから勘弁してくれと言った兄を思い出し、カイはクッと笑った。
あの日の夜、ダリスより手続きを終えたので明日出発したい旨が伝えられた。
しかしシキがもう一日だけ時間が欲しいとカルフェにお願いし、それが受け入れられた。
カルフェの正体やシキとの取引の話は他言無用ということで、残された家族の中でカイのみが知ることとなった。
カイは誰にも言わないことを彼等に誓った。
これから先、世話になるカルフェを相手に、信頼を失うような馬鹿なことはしない。
林から戻ってきたシキとカイの様子がおかしいことを、家族は敏感に感じ取って戸惑いをみせた。
二人の悲観的な空気が薄まっている。
長い間、暗く重たい想いを胸の奥に隠してきた二人は、ようやく心から言いたいことを言い合い、心から笑い合えていた。
チェリエが「何があったのよ!? もう! また私達に隠し事して! ホントに兄ちゃん達、ずるいんだから!」と怒り出したが、最終的にはどこか安心した顔で兄達を見ていた。
シキは私物の整理や近所への挨拶と忙しく、バイルには何を言ったか知らないが「あいつはホントにガキの頃からずっと変わらず兄馬鹿だよな」と後日ぼやいているのをカイは聞いた。どうやらチェリエのことで釘を刺されたらしい。
家族とそれぞれ話す時間も作り、あっという間に残りの時間が過ぎてシキはこの家を旅立っていった。
「死に別れるわけじゃないんだ。生きていればいつかまた会える・・・・・・かもしれないだろう?」
扉のノック音の後にトズの声が聞こえてくる。
「カイ兄ちゃん、夕飯の準備もうすぐ出来るって」
「ありがとう。すぐ行く」
カイは部屋を出るために立ち上がる。
シキと二人で使っていたこの部屋は、いずれトズと二人で使うことになるだろう。
今はまだ、必要以上の生活環境の変化は誰も望んでいなかった。
シキがいなくなったことで、コリエは仕事を辞めて家の仕事に戻ろうと考えていたみたいだが、チェリエがしばらくは今まで通りさせて欲しいと言い出した。シキの残したノートとにらめっこしながら頑張るチェリエを、フェリエとトズが今まで以上に手伝うため走り回っている。
シキが去った次の日には学塔へ行くカイの姿があった。
学塔から帰ってきたカイに、チェリエが声をかけてきた。
「サヨリ、元気だった?」
少し気まずげに訊くチェリエに「あぁ。・・・・・・体調は悪くなさそうだったぞ」と答える。
「そう。・・・・・・よかった」
「・・・・・・」
シキとチェリエは似ていると、カイは以前から思っていた。
社交的で、明るい。そして、隠し事が苦手で、嘘が下手だ。
おそらく、シキの能力の密告者はサヨリなのだろう。
シキとチェリエとサヨリの間にあの日何があったか、大体の想像はついた。
おどおどしながら様子を伺ってくるサヨリに、カイは何も気付かないふりをした。
一時期シキがサヨリをすごく気にかけているようだったので、あの子に恋心でも抱いているのかと疑ったが、それは本当に違ったようで、おそらく妹を心配する兄のような感情だったのだろう。
密告者のことをシキが知られたくないというのなら、カイはその願い通りにするだけだ。
「ちょっとチェリエ姉ちゃん! 何これ!? 形が崩れてるじゃない!」
「ちょっとの形の崩れくらい大目に見てよ! シキ兄ちゃんじゃないんだから完璧には出来ませんー!!」
「何その開き直り~!?」
「あ、トズ、これ運んで?」
「うん!」
「お帰り、父さん母さん」
「ただいま、カイ」
「ただいま。あ、そうだカイ。おまえに訊かれた木彫り職人の件だが・・・・・・」
賑やかな食卓の中央には花瓶が置かれてある。
そこには季節外れのチーの花が七本綺麗に咲いていた。
シキがこの家を出る前に残していったものだ。
蕾だったその一本一本に、彼がどんな願いを込めたのか、今は誰も知らない。