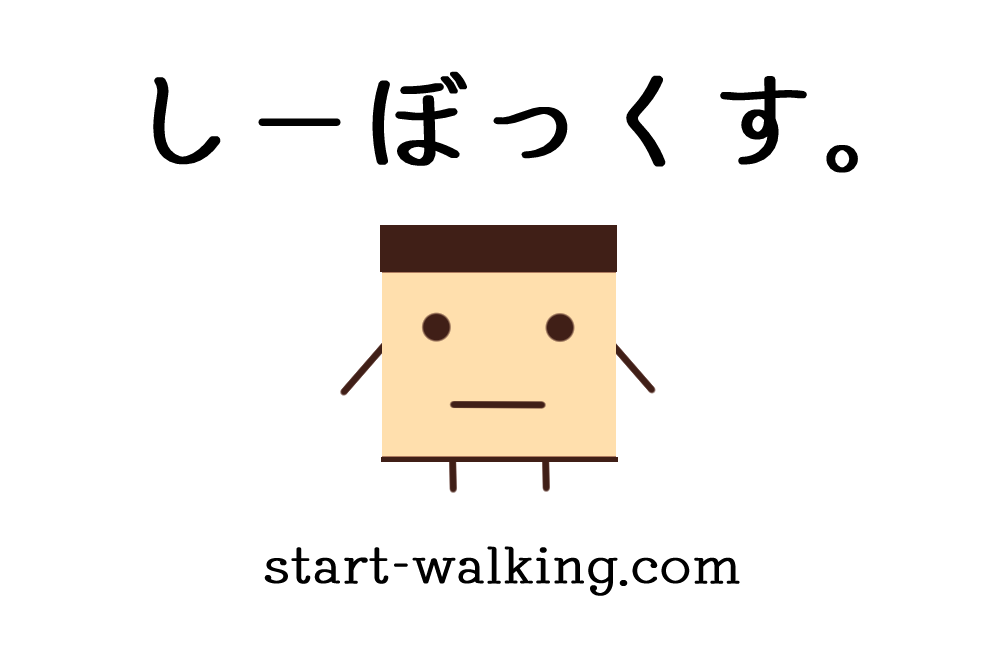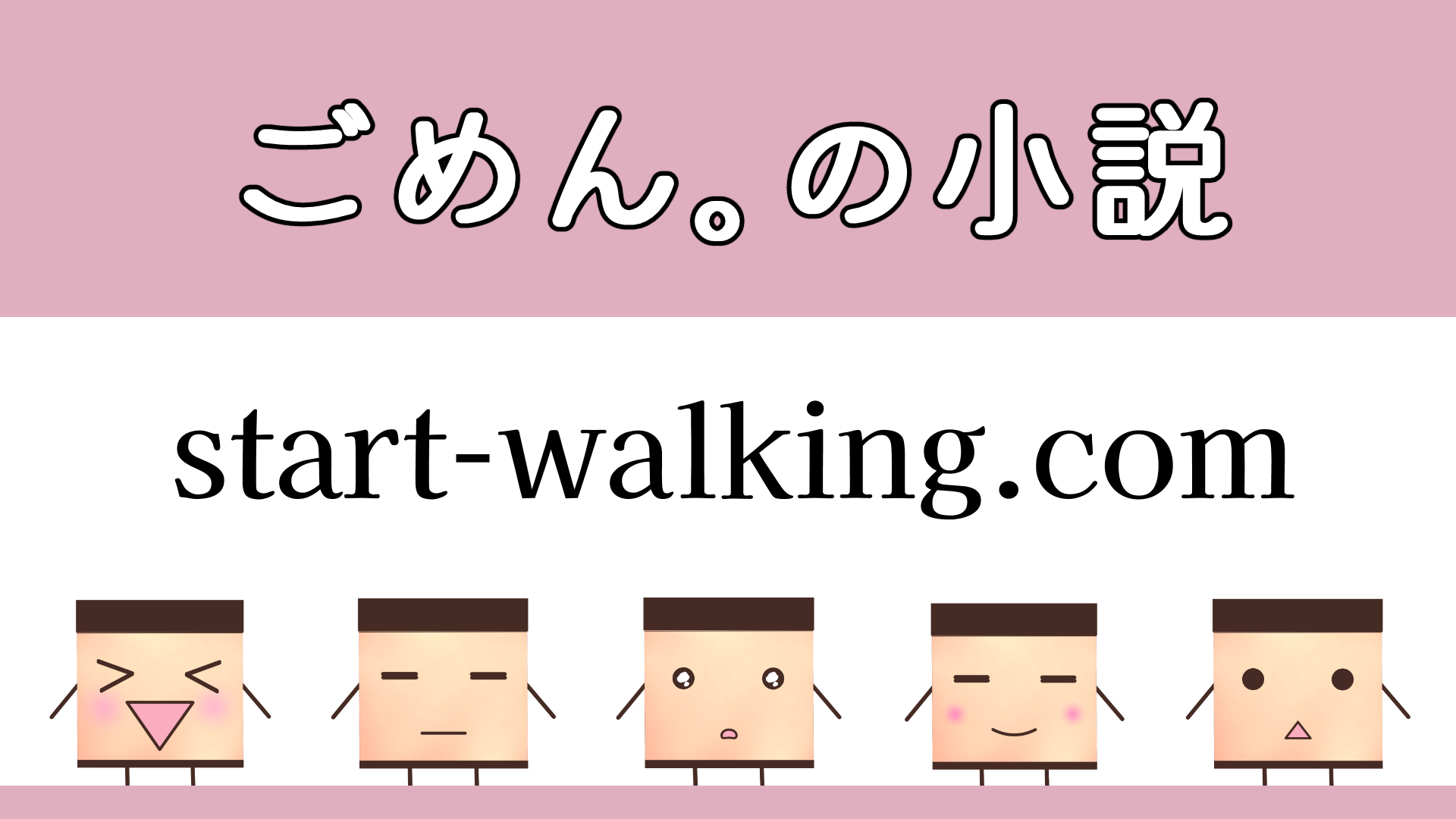第91話 マリエル・バリンドル
(ライツ様には特別な女性はいないと聞いて安心していたのに、よりによって警戒すべきバリンドル家の令嬢がライツ様を狙ってるって、全然安心出来ないから!)
愛那は正面に座るナチェルから語られる情報をジッと待つ。
いきなり話題を変えた愛那に動じることなく「わかりました」と言ってナチェルは話し始めた。
「最初に、今からする話に王太子殿下が登場することをお許し下さい」
愛那がすぐに頷く。
王太子のことなど忘れたい、考えたくないと言っていた愛那を気遣ってのことだったが、愛那にとって今はライツのことが気になって、王太子のことなどどうでもよくなっていた。
「マリエル・バリンドル公爵令嬢。学生時、マリエル嬢はレディル殿下と同じ学年。本来ならば王家との繋がりを得たいバリンドル家ですから、マリエル嬢が狙うのはレディル殿下となるはずでした。しかし、レディル殿下がアレンジア公爵家のルーシェ嬢に幼い頃から片思いをしているというのは有名な話で……」
「? 片思い? 婚約者なのに?」
愛那が首を傾げる。
「その当時はまだお二人は婚約していませんでしたので」
「へぇ、片思い……」
(しかも子供の頃から? え~。そんな人とようやく結ばれて婚約したっていうのに、私の登場で別れさせられそうになったってこと?)
眉間を寄らせて愛那が小さく唸る。
「レディル殿下には、端から相手にされないということはわかりきった状況で、もう一人、一学年上にバリンドル家にとって魅力的な相手がいた。その人はレディル殿下と変わらぬ血筋と大きな魔力量を持つ人物。しかも特別な女性はいない」
「それが、ライツ様」
第92話 王太子候補
「そうです。ルザハーツ家の次男で、しかもその頃のライツ様は王太子候補のお一人でもありました。バリンドル家がほっとくはずがありません」
「王太子候補? え?」
(どういうこと? 王太子って普通に王様の息子であるあの王子がなるんじゃないの?)
「王子であるレディル殿下は成人を迎える18歳までに自身が次期国王に相応しいことを国民に示さなければなりませんでした。この国では魔力が大きい方こそが王に相応しいとされています。学生時の成績などで評価されたライツ様が候補として上がるのは当然のことでした。ライツ様ご本人は次期国王になることを望んではいませんでしたが」
「本人が望んでいなくても候補になっちゃうんですか」
「そうです。魔力の大きさを正確に知ることが出来るのは、初代国王が持っていた幻のスキル【鑑定】のみ。ですのでお二人には決闘という形でどちらが王太子として相応しいかを決めることになり、今から一年程前、レディル殿下が王太子に就任されたというわけです」
「え、じゃあライツ様はその決闘で負けたということ?」
(あの王太子、ライツ様よりも強いの? そっか【強き者】ってそういうことか)
ナチェルは少し困った顔をして「そうですね」と答えた。
「その決闘に関しての真実はマナ様がライツ様ご本人にお訊ね下さい」
「?」
首を傾げる愛那。
「話が逸れましたが、マリエル嬢のライツ様へのアプローチは他のお嬢様方と比べてもすごかったです」
「……」
(他のお嬢様方?)
「彼女は男からみてとても魅力的なのだと話に聞きました。可愛らしい顔立ちで甘え上手なんだとか。実際何人もの男達が彼女のいいなりになっている姿をみかけたことがあります」
「へぇ……そうなんですかぁ」
もやもやとした感情を抱えた愛那が半目になってそう相づちを打つ。
(そんな子がライバルになるのか。やだなぁ……。ああもう! さっきからライツ様に群がる女の子達の姿が脳裏から離れない! 胸のむかつきが重症です!)
第93話 胸のむかつき
(あぁ……これが嫉妬というやつね)
愛那がギュッと目を瞑り拳を胸へと押し当てる。
(恋人じゃないんだからそんな権利、私にはない。だけど、嫌だって言いたい。あの優しい笑顔を他の女の子に見せたりしないで欲しい)
「ライツ様は……優しいから女の子達が期待しちゃうんでしょうね」
(そう。あの格好良さで! 家柄も良くて! 女の子に優しいってどういうこと!? もう! そんなの女の子がコロッといくに決まってるじゃない! 私なんか家柄なんか関係なくコロッよ!)
「優しい? ライツ様がですか?」
「え?」
ナチェルの声に愛那がまぶたを開く。
「学生時代、私はライツ様に振られたり、冷たくされたりして傷つかれたお嬢様方をたくさんお慰めしてまいりました」
どこか遠いところを見つめながらナチェルが微笑を浮かべている。
「え?」
視線を愛那に戻したナチェルの瞳が優しく微笑む。
「ライツ様のあの優しくて甘い表情はマナ様だけに見せるものですよ? マナ様が特別なんです。私もモランも初めて見たときは驚いたくらいです」
「そう……なんですか?」
(それは……嬉しい、な。私だけ? 本当に? 優しくて甘いライツ様が? え? 冷たいライツ様なんて想像出来ないけど。……素直に喜んでいいのかな? ん? あれ? 胸のむかつきが治まってる。あははは。……ああ、でもそれってようするに)
「つまり、それって……」
「ええ」
「ライツ様が私の保護者だから……。救世主特権ってやつですね」
「……」
愛那が笑顔を作ってそう言うと、ナチェルは微妙な顔をして首を傾げた。
第94話 もう一人の要注意人物
(ライツ様のこと。私の憶測で話をしてマナ様のお気持ちを振り回すことは出来ない。今は余計なことは言わないでおこう)
ナチェルがそう心に決める。
「マナ様」
「はい?」
「あとこれは絶対に覚えておいて下さい。そして警戒して下さい。……バリンドル家には、もう一人要注意人物がいます」
「え?」
愛那の顔が曇る。
「マリエル嬢の兄、ダッセル・バリンドル」
「兄……どういう人なんですか?」
「バリンドル公爵家の跡継ぎで、女の敵です」
「え……」
(女の敵?)
「昔からバリンドル家の当主は正妻以外に愛人をたくさん囲ってきました。そしてそれは今でも続いています」
(……それは物語に出てくるハーレムとか後宮とかの話ですか?)
「気に入った女性は無理矢理にでも手に入れようとする男です。マナ様の存在を知れば確実に接触してこようとするでしょう」
「それは……」
(やだ。……ようするに、女癖の悪い男ってことよね? ダメよ! 私はライツ様以外の男なんていりません!)
「ナチェルさん……その男からも、私を守って……くれますか?」
愛那が不安な瞳でナチェルを見つめながらそう訊ねると、ナチェルはすぐに手を胸に当て「必ず」と答えた。
(ううっ。頼もしい! だけど、やっぱり守られてばかりじゃダメよね。そうよ私は救世主! 自分の身は自分で守らなきゃ!)
第95話 新たなお城
その話以降、愛那は魔法についての講義をナチェルに希望し、道中の長い時間を過ごした。
馬車の扉が開き、微笑むライツが愛那へと手を差し伸べる。
「到着したよ、マナ」
「は、はい」
(え、笑顔がまぶしいッ)
頬を染めた愛那が立ち上がってその手をとる。
「お疲れ様。馬車に乗り続けるのも疲れただろう?」
「ありがとうございます。平気です」
(馬での移動の方が大変そうです)
そう思いながら答え、馬車から降りて見上げたそこには……。
(お城!?)
青空の下、巨大な城がそびえ立っていた。
口を開けて目の前の光景を見渡す。
(なんて大きくて立派なお城。おかしいな? お城から逃げてきたのに新たなお城が現れたぞ?)
「ここが兄が居住しているルザハーツ城だ」
(……そうでした。お勉強しました。御三家の一つ、ルザハーツ公爵家は元王家でしたね)
あはは、と乾いた笑いをもらす愛那。
「どうしたマナ?」
「い、いえっ。何でもないです。あまりに素敵なお城なのでびっくりしちゃって」
「そうか」
ライツが硬い顔をした愛那の手を引いて歩き出す。
「今から紹介する兄も、その家族も、優しくていい人達だから安心して欲しい」
「はい」
(気遣ってくれてありがとうございます。でも、こんなに好きな人のご家族に会うのに緊張は止められない!)
第96話 リオルート・ルザハーツ
ライツと愛那たちが城内を歩き進む中、騎士や城勤めしている者達が道を空け端に寄って丁寧に礼をしていく。
「……」
(これから先、立場的にこういった対応に慣れなきゃいけないんだろうなぁ)
愛那は背筋を伸ばし、視線はよそ見せずに真っ直ぐするなどを心がけながら歩く。
(今の私じゃ救世主としての実績もないし、敬われることに抵抗を感じちゃうな。……庶民の感覚はそう簡単に変えられません!)
到着を伝えるため、先に城内にいたハリアスが、大きな扉の前でライツたちを待っていた。
「こちらでお待ちです」
ライツが頷きハリアスが扉を開く。
「マナ。行こう」
愛那はライツの視線を受け止めコクリと頷く。
開かれた扉の向こう側には温かみを感じる広い部屋があった。
壁には絵画。床に絨毯。本棚とソファにテーブル。全ての色合いが茶系の落ち着いたもので、置かれてあるさまざまな小物などにも愛那は親しみを覚える。
(あれとか可愛い。……なんだか、お城の中だし、もっと冷たいイメージがあったんだけど)
「お久しぶりです、兄さん」
ライツのその声に愛那はハッとなる。
右手の奥。一人掛けのソファから立ち上がり、こちらを見ている人物。
リオルート・ルザハーツ。
ルザハーツ公爵家当主。25歳。
(銀髪。……ライツ様とは髪色が違うのね)
胸の鼓動を落ち着かせながら、愛那はライツと共にリオルートの近くへ向かう。
その間、微笑を浮かべているリオルートの視線が愛那へと注がれ続けている。
(そんなに見ないで下さい~! 顔が強ばっちゃうから~!)
顔だけでなく、体の動きもぎこちない愛那に気づいたライツが立ち止まって愛那の頭を撫でた。
(ええっ!?)
この状況でそんなことをされた愛那が固まる。
「兄さん、そんなにマナを見ないで下さい。彼女の緊張に拍車がかかってしまう」
その言葉にリオルートは声を上げて笑った。
「ライツ、おまえが女性を気遣うなんて初めて見た」
「からかわないで下さい」
「からかいたくもなるだろう」
そう言って改めてリオルートは愛那へと視線を移し微笑んだ。
「初めまして、可愛らしいお嬢さん。私の名はリオルート・ルザハーツ。君の手をとっているその男の兄だよ」
第97話 丁寧な挨拶
愛那はライツに声をかけて手を離してもらい、リオルートに向かい微笑んだ。
そして右足を後ろに下げて両手でスカートの裾をつまみ、少し持ち上げ膝を曲げて腰を深く下ろす。
「初めまして。マナ・サトウエです。ライツ様のお兄様にお会いできて嬉しく思います」
(だ、大丈夫だよね! ナチェルさんに習った通り、うまく出来たと思う!)
「丁寧な挨拶をありがとう。私もライツの大切な女性に会えて、とても嬉しく思うよ」
笑顔でリオルートが挨拶に応えてくれて愛那は安心する。
(ん? え~と、私はお兄様にどういう認識をされているのかな?)
救世主だと知られているのだろうかと愛那が悩む。
(なんだかライツ様の彼女みたいな紹介になっていませんか? 嬉しいけど違いますよ?)
「私の妻と子供たちに紹介する前に、三人だけで話がしたいな」
そう言ってリオルートが傍にいる自分の側近へ目線をやる。
するとその側近が頷き、リオルートとライツ、愛那を残してこの部屋にいた者全てが退出していく。
(ああ、ナチェルさん、ハリアスさんとモランさんも行っちゃった)
扉が閉じて三人だけになると、微笑んでいたリオルートの顔が真面目なものになり、スッと片膝をつき愛那に向かって頭を下げた。
(ええっ!?)
「救世主様。遠きこの地までようこそいらっしゃいました。ルザハーツ家当主として、貴方様を心より歓迎いたします」
第98話 淑女の正解がわからない
愛那はとっさにリオルートへと走り寄って膝をついた。
「やめて下さい!」
驚いた表情のリオルートと間近で視線を合わせ、愛那は(あ、ライツ様と同じ目の色)と思ったが、それどころではない。
「あ、あ、あの。救世主だからとかそういうのは……その、普通に接してくれると嬉しいです」
徐々に声を小さくしながら愛那が伝える。
(わあああん! とっさに体が動いて淑女らしく出来なかった~! ていうか淑女の正解がわからない~)
泣きたい気持ちの愛那に、ライツが歩み寄って手を差し伸べる。
「とりあえず二人とも立とうか?」
そうライツに促され、リオルートが微笑を浮かべ立ち上がる。
それを見た愛那も、ライツの手に右手をのせて立ち上がった。
「当然だけど、マナはまだこちらの世界に慣れていないんだ。恐縮してしまうから普通の令嬢に接するくらいの対応で丁度いいんじゃないかな?」
ライツの言葉にコクコクと愛那が頷く。
「わかりました。救世主である貴方様がそうお望みならばそうしましょう。では、マナ嬢とお呼びしましょうか?」
「いえっ! マナでお願いします!」
元気よくそう返答してしまった愛那。
(ごめんなさいナチェルさん! 淑女について勉強し直します!)
「では、マナ。伝えておきたいことがあるので、座って話をしようか?」
促され二人掛けのソファに愛那とライツが座る。
一人掛けのソファへ腰を下ろしたリオルートが口を開いた。
「マナ。君が救世主であることは、しばらくの間伏せておいた方がいいと判断し、皆の前で先程のような対応をしてしまったことを許して欲しい。ここにいる間は、ライツの恋人として周囲に認識してもらうことにしたので、よろしく頼む」
第99話 そんなこと言うのは反則です!!
(よろしく頼むって、恋人!? え!? 私とライツ様で恋人のふりをしろってこと!?)
愛那が戸惑う。
「救世主であるマナがここにいることを知られたら、各地から大勢の者たちが、この地へ押し寄せてくるだろう」
リオルートの言葉に、愛那がゆっくりと頷いた。
(それは勘弁して欲しい。まだ救世主として活躍出来るかどうかもわからないのに、そんな人たち相手に、どう対応したらいいのかわからないもの)
「魔物の討伐を期待して、マナを奪い合うような騒動に発展するかもしれない。それを避けるためにも、マナの正体を伏せておく必要があるんだ」
今度は二回大きく頷く愛那。
(ありがたく救世主であることを伏せさせていただきます!)
「ライツ。当分の間、お前の屋敷には帰らずマナと共にここにいてくれ。その方が安全だ」
兄の言葉にライツが頷く。
そしてライツは隣の愛那に声をかけた。
「マナ。予定と違ってしまったが、魔法を学ぶ設備に関しては、ここにも揃っているから大丈夫だ」
「はい。私、がんばります!」
救世主として魔法を使いこなし魔物を討伐する。
自分の力を試したい。早くそれを実現したいと愛那は強く思っていた。
そんな強い意志が愛那の顔に表れていて、それを見たライツが微笑んで愛那の頭を撫でた。
(!)
再び愛那が固まる。
(ライツ様はなんでそんなに私の頭を撫でたりするの!? 何で? あれですか? いい子いい子ってやつですか? ようするに子供扱いってことですか!?)
ぐるぐるとそんなことを頭の中で考えていると、そんな二人を見ていたリオルートが面白そうな顔をして頷いた。
「その調子で周囲に仲のいい恋人同士だと見せつけてくれ。マナを隠すためにライツが少々独占欲が強いくらいに思われた方がいいかもしれないな」
(!? そうでした。ライツ様と恋人同士のふりをしなきゃいけないんでした。……嬉しいけど口説くのはまだ先の予定だったのにどうしたらいいの? ……それに、ライツ様は私と恋人を演じることをどう思ってるんだろう)
不安になってチラリと愛那がライツの様子を窺うと、ライツも愛那を見つめていたので心臓が跳ねた。
「……マナ。俺が恋人だというのは嫌じゃないか?」
「ッ!」
愛那が衝撃に体を震わせた。
(ライツ様! その顔で! その声で! そんなこと言うのは反則です!!)
ぐっといろいろなものをこらえて愛那が口を開く。
「嫌じゃ……ありません」
その答えにライツがほっとした表情を見せ「そうか」と言って微笑んだ。
第100話 偽りの素性
(恋人のふり、か。おそらく兄さんは、ハリアスから俺たちのことを聞いて気を利かせてくれたんだろうな。マナも嫌じゃないと言ってくれたし、ずるいかもしれないが、マナに俺のことを恋人として意識してもらういいきっかけになるかもしれない)
ライツが隣に座る愛那の手の指先に触れて指を絡める。
すると動揺した愛那が恥ずかしげに顔を赤くして俯いた。
(マナ。そんな可愛らしい反応をするから、君に好かれているんじゃないかと、馬鹿な男が誤解してしまうんだ)
ライツが苦く笑う。
愛那の好きな男がどんな人物だったのか、ずっと気になっていた。
(マナの好きな相手と声がそっくりだということは、俺にとってマイナスでしかない。これから先ずっと、俺の声がその男のことを思い出すきっかけになり続けるのだから。……声以外はどうなんだろう? マナはその男のどういった所に惹かれたんだろうか?)
「ライツ?」
リオルートに呼ばれハッと顔を上げた。
こちらを見ている兄へとライツはごまかすように笑顔を作り「すみません」と言って言葉を続ける。
「それで、マナの偽りの素性については、どういう設定にするおつもりですか?」
「あぁそれなら、マナはドーバー伯爵夫人の、遠い親戚のお嬢さんという風に紹介するのが一番だろう」
「なるほど。ハリアス経由で知り合ったというのであれば、不自然さは感じないでしょうね」
「ああ」
そんな兄弟の会話に愛那が首を傾げて「あの……」と訊いてくる。
「ドーバー伯爵夫人というのは?」
微笑を浮かべたライツが愛那へと答える。
「マリス・ドーバー伯爵夫人。ハリアスの奥さんのことだよ」